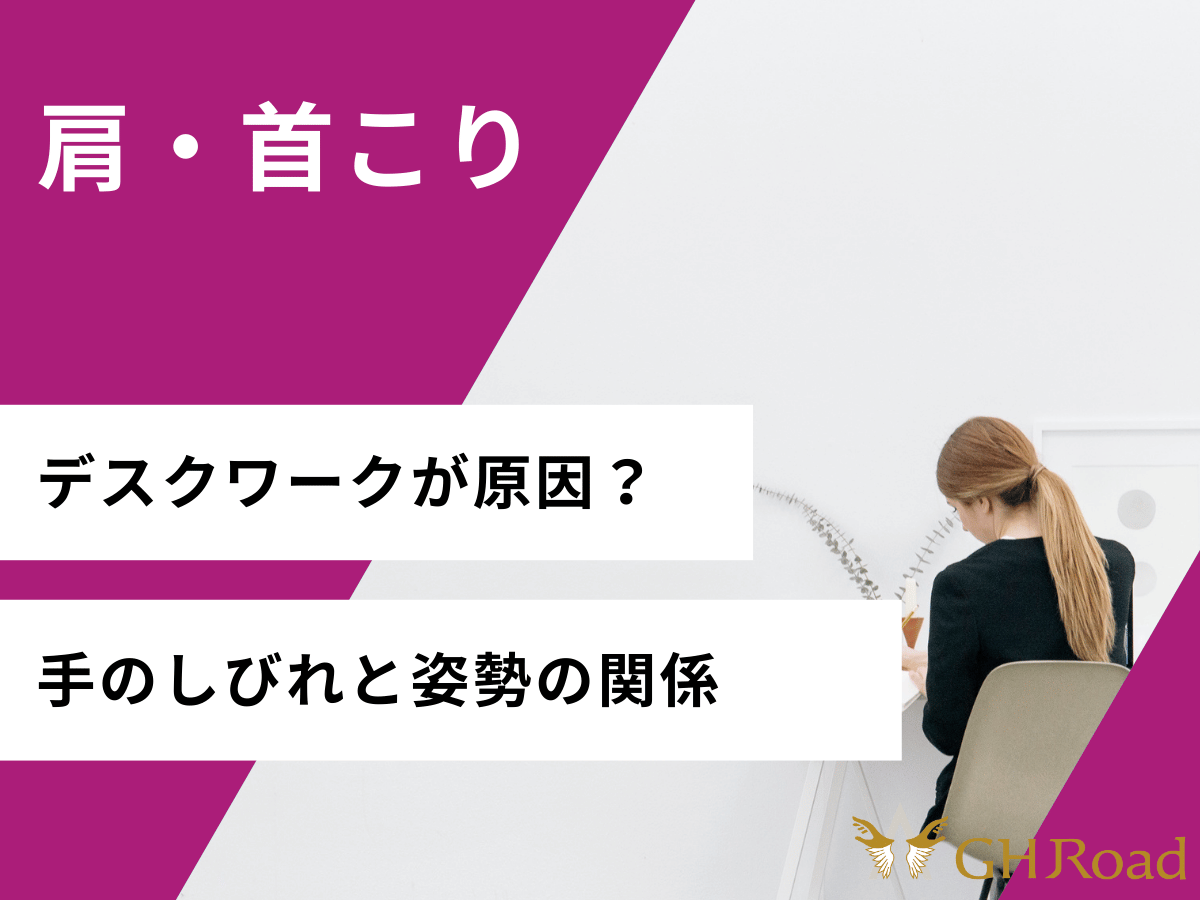目次
デスクワークによる手のしびれのメカニズム
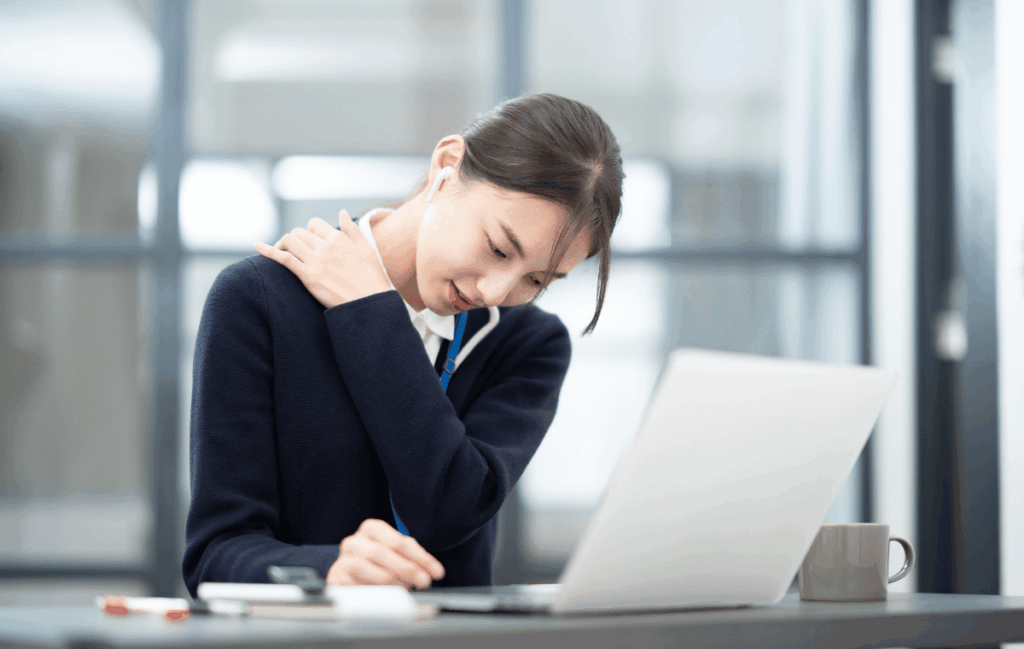
デスクワークは首・肩・腕に大きな負担をかけるため、手のしびれが出やすい生活習慣のひとつです。特に長時間同じ姿勢を続けることで、神経や血管の圧迫が起こりやすくなります。ここでは、その具体的なメカニズムを解説します。
デスクワークの影響と神経圧迫の関係
- 長時間の前かがみ姿勢により、首や肩の筋肉が硬直
- 硬くなった筋肉が神経や血管を圧迫
- 神経伝達が妨げられ、ピリピリ・ジンジンとしたしびれが出る
特に「胸郭出口」や「手首(手根管部)」は圧迫されやすく、デスクワークが直接的にしびれを引き起こすポイントになります。
マウス症候群とは?その症状と原因
近年よく耳にする「マウス症候群」とは、マウス操作を繰り返すことで首・肩・腕に負担がかかり、しびれや痛みを引き起こす状態です。
- マウスを長時間握ることで前腕や手首が緊張
- その負担が神経圧迫や血流障害につながる
- 指先のしびれや、手の甲のだるさとして現れる
デスクワーカーにとって、とても身近な原因のひとつです。
姿勢がもたらす手のしびれのリスク
悪い姿勢はしびれを慢性化させる大きな要因です。
- 猫背:首が前に出ることで頚椎や神経に圧迫がかかる
- 巻き肩:胸郭出口が狭まり、神経・血管が圧迫される
- 片側だけでマウスを使う:負担が偏り、左右差のあるしびれが出る
姿勢の悪さは「しびれを起こす土台」を作ってしまうため、改善が不可欠です。
デスクワークと手のしびれの関係

デスクワークをしていると「手がしびれてきた…」という経験をした方は少なくないでしょう。これは単なる疲れではなく、神経や血流に負担がかかっているサインです。ここでは、デスクワークと手のしびれの関係を整理します。
なぜデスクワークでしびれが出やすいのか
- 長時間同じ姿勢で筋肉が硬くなる
- 血流が滞り、神経への酸素供給が不足する
- キーボードやマウス操作による細かい動作の繰り返しが、局所的な疲労を招く
これらの要素が重なることで、手にしびれが現れやすくなります。
長時間同じ姿勢が体に与える影響
同じ姿勢を続けることは、首・肩・腕の「血流と神経」に大きな負担をかけます。
- デスクワーク中の猫背 → 首の骨(頚椎)にストレスが集中
- 腕を机に乗せっぱなし → 神経や血管の圧迫
- 前傾姿勢 → 胸郭出口のスペースが狭まり、神経が圧迫されやすい
これにより、しびれだけでなく肩こりや頭痛にもつながります。
キーボードやマウス操作と神経圧迫の関係
デスクワーク特有の「入力作業」も、しびれを悪化させる要因です。
- キーボード:手首を反らした状態で固定 → 手根管症候群を誘発しやすい
- マウス:クリック動作の繰り返し → 前腕や手首の緊張が持続
- 姿勢の偏り:利き手ばかり使う → 左右の筋バランスが崩れ、しびれが一側に出やすい
つまり、作業姿勢そのものが「神経の圧迫要因」となっているのです。
デスクワークによる姿勢習慣としびれの原因

手のしびれを訴えるデスクワーカーの多くに共通しているのが「姿勢の崩れ」です。悪い姿勢は、筋肉や骨格のアンバランスを生み出し、神経や血管を圧迫してしびれを引き起こします。
猫背・巻き肩が招く首や肩の負担
- 背中が丸まると首が前に突き出し、頚椎に負担が集中
- 巻き肩になると鎖骨の下で神経や血管が圧迫され、胸郭出口症候群の原因に
- 結果として、手の冷えやしびれ、肩や首のこりが悪化
猫背は「手のしびれを作る温床」といえる姿勢です。
スマホ首(ストレートネック)としびれの関連
- 長時間のうつむき姿勢で、首の自然なカーブ(頚椎の前弯)が失われる
- 頚椎の神経が圧迫されやすくなり、腕から手にかけてしびれが出る
- 頭の重さを支える筋肉も疲労し、肩や背中の痛みを伴うことも
「スマホ首」は若い世代にも急増しており、デスクワークしびれの隠れた原因です。
片側だけに負担がかかる座り方や作業環境
- マウスや電話を常に同じ手で扱う
- 体をねじったまま作業を続ける
- 片肘だけ机に乗せている
このような「左右非対称の姿勢」は、神経や筋肉のアンバランスを招き、片側の手だけにしびれが出やすくなります。
手のしびれの症状とその診断

デスクワークによる手のしびれは、症状の出方や特徴によって原因を見極める手がかりになります。ここでは、代表的な症状と診断の流れを整理します。
手がしびれる時の主な症状
- 指先にピリピリと電気が走るような感覚
- 手のひら全体のジンジンとしたしびれ
- 冷たさや血の気が引くような感覚
- 握力低下や、細かい作業がやりにくくなる
しびれの種類(ピリピリ/ジンジン/感覚が鈍い)によって、神経性か血流性かを推測できます。
しびれが緊急のサインである場合
次のような症状は、命に関わる病気のサインである可能性があります。
- 急に左手全体がしびれる
- 顔の片側や足にも同時にしびれがある
- 言葉が出にくい、視覚の異常、ふらつきがある
これは脳梗塞や心疾患の可能性があるため、すぐに医療機関を受診する必要があります。
疾病診断としての胸郭出口症候群
デスクワーカーに多い「胸郭出口症候群」は、鎖骨や肋骨の間で神経や血管が圧迫されることで起こります。
- 腕を上げるとしびれが悪化
- 握力低下や手の冷えを伴う
- 同じ姿勢を続けると悪化しやすい
診断は徒手検査(アドソンテスト、ライトテストなど)や画像検査で行われます。
手のしびれに関わる代表的な病気

デスクワーク中の手のしびれは、単なる疲労や一時的な血流不良だけでなく、神経や血管に関わる病気が隠れている場合もあります。ここでは代表的な病気とその特徴を整理します。
胸郭出口症候群とデスクワークの関係
首の付け根から鎖骨、肋骨の間を通る神経や血管が圧迫される病気です。
- デスクワーク中の猫背や巻き肩で悪化しやすい
- 腕を上げると症状が強くなる
- しびれだけでなく、手の冷えや握力低下を伴う
特に長時間同じ姿勢を続ける人に多くみられます。
頚椎症による神経圧迫
加齢や不良姿勢により、首の骨(頚椎)が変形して神経を圧迫する病気です。
- 首を動かすとしびれが悪化
- 肩や背中の痛みを伴う
- 重症化すると歩行障害や排尿障害につながる
「スマホ首」や長時間の前傾姿勢は、若年層でも発症リスクを高めます。
手根管症候群とキーボード操作の影響
手首の手根管というトンネルで正中神経が圧迫されて起こります。
- 親指、人差し指、中指のしびれが中心
- 夜間や朝方にしびれが強くなる
- 進行すると親指の筋肉が痩せてくる
キーボードやマウス操作を繰り返す人に多い病気です。
血流障害や全身疾患によるしびれ
- 糖尿病性神経障害:両手や両足に広がるしびれ
- 心臓や循環器疾患:胸の痛みや息切れを伴う左手のしびれ
- 脳梗塞などの脳疾患:急に発症し、顔や足のしびれを伴う
こうした全身性の病気が隠れている場合もあるため、症状を軽視しないことが大切です。
デスクワークを行う際の正しい姿勢とは?

デスクワークによる手のしびれを防ぐには、作業環境を整えることが欠かせません。正しい姿勢を意識することで、神経や血管への圧迫を減らし、症状の予防につながります。
デスク上での作業姿勢の重要性
- モニターは目の高さに合わせ、首を前に突き出さない
- 椅子の高さを調整し、肘が直角になる位置でキーボードを操作する
- 足裏を床につけ、骨盤を立てて腰を安定させる
姿勢が安定すると、肩や腕への負担が大幅に軽減されます。
正しいマウスの使い方と配置
- マウスは体の正面に近い位置に置く
- 手首だけで動かさず、肘から動かすように意識する
- 手首が反らないように、リストレストを活用する
「マウス症候群」の予防には、使い方の工夫が大きなポイントです。
肩甲骨を意識したストレッチ方法
長時間の作業の合間に、肩甲骨を意識したストレッチを行うと効果的です。
- 両腕を後ろで組み、胸を開く
- 肩をすくめてから大きく回す
- 肩甲骨を寄せて5秒キープする
肩甲骨まわりがほぐれることで、胸郭出口の圧迫が和らぎ、手のしびれ予防につながります。
整体でできる改善アプローチ

デスクワークによる手のしびれは、筋肉や神経への負担が蓄積することで起こります。そのため、整体で全身のバランスを整えることで改善が期待できます。ここでは平井塾の手技を中心にご紹介します。
FJAで細部のエラーを整える
平井塾独自の FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ) は、神経や関節の微細な動きを観察し、負担が集中している「細部のエラー」を修正する手技です。
- 痛みやしびれが出ている部分だけでなく、その原因を探る
- 力任せに押すのではなく「手で聴く」ように繊細に調整
- 神経や筋膜の動きをスムーズにし、圧迫を解消
これにより、しびれの根本原因にアプローチできます。
姿勢循環整体で全身のバランスと血流を改善
FJAで細部を整えたあとは、姿勢循環整体によって全身の姿勢と循環を調整します。
- 背骨や骨盤を安定させ、首や肩の負担を減らす
- 血液・リンパの流れを促し、神経の回復を助ける
- 全身をひとつのユニットとして整えることで自然治癒力を高める
部分的ではなく全体を調和させることが、再発防止につながります。
整体とセルフケアを組み合わせるメリット
整体の効果を持続させるためには、セルフケアとの組み合わせが大切です。
- デスクワーク中のストレッチを取り入れる
- 良い姿勢を意識して習慣化する
- 環境改善(椅子や机の高さ調整)を行う
施術+セルフケアの相乗効果によって、「症状の改善」と「再発予防」の両方を実現できます。
手のしびれを改善するための対処法

デスクワークによる手のしびれは、放置すると慢性化する可能性があります。日常生活に取り入れやすい対処法を実践することで、症状の軽減や予防につながります。
運動とストレッチで手のしびれを軽減
- 首のストレッチ:首をゆっくり横に倒す、肩を回す
- 胸を開く運動:両手を後ろで組んで胸を開くことで猫背を改善
- 手首のストレッチ:手のひらを下に向け、反対の手で軽く押して伸ばす
こまめな運動で筋肉の緊張をほぐし、血流を改善できます。
整体や鍼灸の効果と施術内容
整体や鍼灸は、神経や筋肉のバランスを整える有効な手段です。
- 整体:姿勢を正し、神経圧迫の原因を取り除く
- 鍼灸:ツボを刺激して血流を改善し、痛みやしびれを和らげる
特に整体は「根本原因の改善」、鍼灸は「循環の改善」という特徴があり、併用も効果的です。
適切な休憩時間と作業環境の見直し
- 休憩は1時間に5分を目安に取る
- 画面の高さや椅子の位置を調整する
- マウスやキーボードの配置を見直す
小さな環境改善の積み重ねが、手のしびれ予防に直結します。
自分でできる予防とセルフケア

手のしびれは、日常の小さな工夫で予防できます。デスクワークを続けながらも快適に過ごすために、セルフケアを習慣化しましょう。
正しいデスクワーク姿勢の作り方
- 背もたれに深く座り、骨盤を立てる
- モニターは目線と同じ高さにする
- 肘を90度に曲げ、手首を反らさない
「正しい姿勢」は、それ自体が最大の予防法です。
仕事中に取り入れたいストレッチ習慣
- 首回し運動:ゆっくり大きく円を描くように回す
- 肩甲骨寄せ:背中で両肩を寄せ、5秒キープ
- 手首ストレッチ:反対の手で手首を軽く押し、伸ばす
休憩のたびに行うだけで、筋肉のこわばりを防げます。
休憩の取り方と環境改善のポイント
- 1時間に1回は立ち上がって歩く
- マウスやキーボードは体の正面に置く
- 椅子の高さを調整し、足裏を床につける
環境改善と休憩の両立で、しびれの再発を大幅に減らせます。
手のしびれを予防するための習慣
一度しびれが出てしまうと改善までに時間がかかることがあります。だからこそ、日常的に「予防の習慣」を取り入れることが大切です。
日常生活でできる予防法
- 長時間同じ姿勢を避け、こまめに体を動かす
- 重たい荷物を片側の肩だけで持たない
- スマホをうつむいたまま長時間操作しない
小さな工夫の積み重ねが、手のしびれを防ぐ大きな一歩となります。
筋トレと血行改善の関係
筋肉を鍛えることで姿勢が安定し、血流も良くなります。
- 軽い腕立て伏せで肩・腕の筋肉を強化
- チューブトレーニングで肩甲骨周りを活性化
- ウォーキングで全身の血流を促進
筋トレは「支える力」を養い、神経圧迫を減らすことにつながります。
快適なデスク環境の整え方
- 椅子の高さと机のバランスを調整する
- リストレストや人間工学マウスを活用する
- 部屋の照明や湿度を整えて集中力を高める
快適な作業環境は、体の負担を減らし、しびれの再発を防ぐ効果があります。
受診が必要なしびれとは?

デスクワークによるしびれの多くは姿勢や生活習慣の改善で軽快しますが、なかには重大な病気のサインである場合もあります。ここでは、病院での受診が必要なしびれについて解説します。
すぐに病院に行くべき危険な症状
- 急に左手全体がしびれ、胸の痛みを伴う(狭心症・心筋梗塞の可能性)
- 顔や足にも同時にしびれが出る(脳梗塞の可能性)
- 言葉が出にくい、ふらつく、視覚の異常を伴う
これらは命に関わる緊急症状であり、直ちに救急受診が必要です。
整体と医療機関の役割の違い
- 整体:姿勢改善、筋肉や神経の負担軽減、循環の改善
- 医療機関:検査による診断、薬物療法、手術などの医療処置
両者の役割は異なりますが、補完し合うことで安全に改善を目指せます。
安心して回復を目指すための選択肢
- 日常のしびれ → 整体やリハビリで改善可能
- 長引く・悪化するしびれ → 医療機関での精密検査
- 緊急性が高いしびれ → ためらわず救急受診
「整体に行くか、病院に行くか」で迷ったときは、安全のため医療機関を優先することが推奨されます。
手のしびれに関するよくある質問(FAQ)

患者さんからよく寄せられる疑問を整理しました。気になる症状がある方は、セルフチェックの参考にしてください。
手のしびれが治らない場合の相談先は?
数日~数週間続くしびれが改善しない場合は、整形外科や神経内科での受診がおすすめです。
- 骨や神経の問題 → 整形外科
- 脳や全身疾患が疑われる場合 → 神経内科
整体は並行して受けることで、姿勢や筋肉の負担を減らす役割を果たします。
指先のしびれが続く時の注意点
- 親指~中指 → 手根管症候群の可能性
- 小指や薬指 → 胸郭出口症候群や頚椎症の可能性
- 両手の指先全体 → 糖尿病性神経障害など全身疾患の可能性
しびれの「出る場所」が診断のヒントになります。
気になる「手のしびれで目が覚める」理由
夜間や朝方にしびれで目が覚める場合は、以下の要因が考えられます。
- 手首や腕の血流が寝姿勢で圧迫されている
- 手根管症候群など神経圧迫がある
- 枕の高さや寝姿勢の影響で首に負担がかかっている
頻繁に起こる場合は、環境改善に加え、医療機関でのチェックが必要です。
もしも手のしびれが続いたら

手のしびれが一時的なものであれば、休憩やストレッチで改善することも多いです。しかし、長引く場合や悪化していく場合は、放置せずに適切な対応を取ることが大切です。
病院での検査と医師の診断
しびれが続く場合、まずは医療機関で原因を特定することが重要です。
- レントゲン:骨の変形や頚椎の異常を確認
- MRI:神経や脊髄の圧迫を詳細に評価
- 血液検査:糖尿病や代謝性疾患の可能性を調べる
これらの検査結果をもとに、医師が診断を行います。
適切な治療法とその流れ
診断によって治療法は異なります。
- 保存療法:薬物療法、ストレッチ、リハビリ
- 整体や理学療法:姿勢改善と循環改善
- 手術:神経圧迫が強く、保存療法で改善しない場合に検討
まずは保存療法から始めるのが一般的で、重症化しているケースのみ手術が考慮されます。
状態に応じた専門的な施術選択
- 胸郭出口症候群 → 姿勢改善や胸郭の調整
- 頚椎症 → 首への負担を軽減する整体やリハビリ
- 手根管症候群 → 手首の安静や手技療法
平井塾の整体アプローチでは、FJAによる細部の調整と姿勢循環整体を組み合わせ、全身の回復力を引き出すことで改善を目指します。
まとめ|姿勢と習慣を整え、しびれを防ぐ

デスクワークによる手のしびれは、多くの場合「姿勢の崩れ」と「生活習慣の積み重ね」が原因です。猫背や巻き肩、長時間同じ姿勢を続けることは、神経や血管を圧迫し、しびれを悪化させます。
しかし、
- 正しい姿勢を意識する
- ストレッチや休憩をこまめに取り入れる
- 作業環境を整える
といった工夫で、多くのしびれは予防・改善が可能です。
さらに、整体では FJA(ファシアティックジョイントアプローチ) による細部の調整と、姿勢循環整体による全身のバランス改善を行い、根本からの回復を目指します。これは単なる対症療法ではなく、再発しにくい体づくりにつながる大きな強みです。
「手のしびれはよくあること」と軽く考えず、体からのサインを正しく受け止めることが健康維持の第一歩です。
平井塾では、豊富な臨床経験と独自の手技をもとに、デスクワークで悩む多くの方をサポートしています。安心して仕事を続けたい方は、ぜひ信頼できる整体院や平井塾の受講生にご相談ください。
投稿者情報:平井 大樹

みゅう整骨院 代表。平井塾 代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。
「患者様の人生に、心からの安心を。」
私は、これまで20年間、延べ10万人を超える患者様と向き合ってきました。その中で最も大切にしてきたのは、「痛みを取る」ことだけではなく、「患者様が心から安心して過ごせる毎日を取り戻す」ことです。
- 長期にわたる信頼:みゅう整骨院には、5年以上通われる方が308名、10年以上通われる方も100名いらっしゃいます。これは、一時的な改善ではなく、患者様が私たちに一生の健康を任せてくださっている証です。
- 根本的なアプローチ:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)、姿勢循環整体という独自の手技で、痛みの箇所だけでなく、その根本原因である身体全体の歪みや動きの不調にアプローチします。
- 平井の予約が取れない理由:開業後、患者様の紹介がメインで予約が満員になりました。2020年以降、新規予約は5年待ちの状態です。現在、新規予約を取る予定はありませんが、みゅう整骨院または、平井塾受講生から同じ施術を受けることができます。
このコラムが、あなたの不調を改善し、より豊かな毎日を送るための一歩となれば幸いです。