整骨院スタッフ教育がうまくいかない院長の共通点
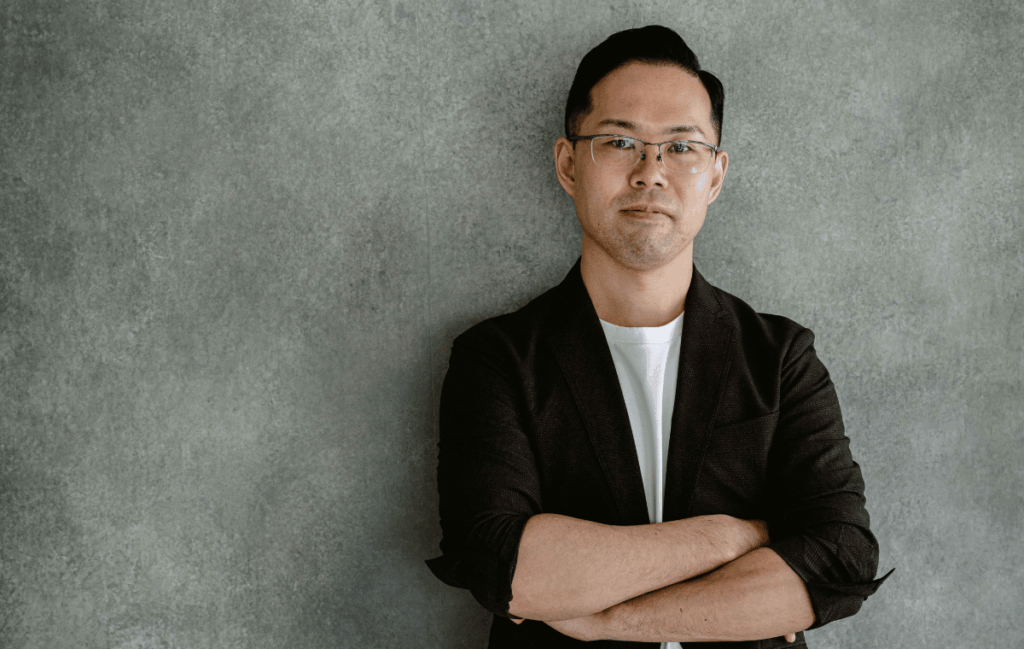
「できるようになってほしい」が裏目に出る理由
整骨院の院長なら誰もが思うこと。
「せっかく採用したスタッフには、早くできるようになってほしい」
この想い自体は間違っていません。
しかし、院長の熱意が強すぎると、それはスタッフに プレッシャー として伝わり、かえって成長を妨げてしまうのです。
熱意がプレッシャーに変わる心理的メカニズム
院長の熱意が「期待」という形で圧力になると、スタッフは「失敗してはいけない」と感じます。
この状態では新しい挑戦ができず、受け身で安全な行動しか取らなくなります。
結果として、院長は「全然成長しない」と苛立ち、スタッフは「何をやっても怒られる」と疲弊する悪循環が生まれるのです。
「できるようになってほしい」がプレッシャーになる3つの罠

強い期待がスタッフを萎縮させる
「絶対にできるようになれよ」というプレッシャーは、スタッフの心を固めてしまいます。
伸び伸びと試行錯誤する余裕を失い、緊張と委縮の中で働くことになります。
院長の顔色を伺う文化が根付く
「院長が怖そうにしているから、わかったフリをしよう」
そんな空気が院内に生まれると、スタッフは本音を言えなくなります。
教育の基本である「できません」と言える環境が壊れるのです。
挑戦よりも「失敗回避」が優先される
失敗を避ける文化では、スタッフは小さな挑戦すらできません。
臨床現場で本当に必要なのは 失敗を通じた学び ですが、そのチャンスが奪われます。
整骨院院長が陥るスタッフ教育の失敗例

「必ずできるように!」と詰め込むケース
熱意が強すぎると、一度に大量の知識や技術を教え込もうとします。
しかし情報過多は理解を浅くし、かえって成長を遅らせます。
熱意が怒りや苛立ちに変わるケース
「なぜできないんだ!」という怒りに変わった瞬間、教育は崩壊します。
スタッフは委縮し、学ぶ意欲を完全に失います。
「やる気がない」と誤解して信頼関係を崩すケース
できないのは「やる気のなさ」ではなく「理解が追いついていない」だけのことも多い。
しかし院長が誤解して叱責してしまうと、信頼関係が一気に壊れてしまいます。
伴走型教育が整骨院スタッフを伸ばす理由

「教える」より「一緒にやる」で安心感が生まれる
伴走型教育とは、院長が「教える人」から「共に成長する人」へと役割を変えることです。
「一緒にやってみよう」という姿勢が安心感を生み、スタッフは挑戦しやすくなります。
失敗しても大丈夫と思える心理的安全性の効果
「失敗しても院長が支えてくれる」と思える環境では、スタッフは積極的に学べます。
心理的安全性は、成長スピードを大きく加速させます。
小さな成功体験が定着率を高める
伴走型教育では「できた!」という小さな成功を積み重ねます。
この成功体験は自己効力感を高め、離職率を下げる効果があります。
伴走型教育を実践するための整骨院マネジメント法

ゴールを小さく分けるステップ設計
教育の最初から完璧を求めるのではなく、段階ごとに小さなゴールを設定します。
例:
- 第1週:患者さんへの挨拶と誘導
- 第2週:簡単な触診の補助
- 第3週:基礎手技の一部のみ
「これだけできれば合格」と明確にすることで、安心して学べます。
問いかけを増やしスタッフの思考を引き出す
伴走型教育では、答えを一方的に与えるのではなく 問いかけ を活用します。
「今の施術で患者さんはどう感じたと思う?」
「もし自分ならどう改善する?」
こうした対話がスタッフの主体性を育みます。
「できるようにさせる」ではなく「成長を支える」意識
教育のゴールは「自分と同じようにできるスタッフを作ること」ではありません。
院長自身が スタッフの成長を支える存在 になることこそ、マネジメントの本質です。
平井塾が提案する伴走型教育の具体例

FJAで磨く「観察と調整」の姿勢
FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)は、細部を観察し必要な調整を行う手技です。
教育においても「全部教える」ではなく、相手を観察し 今必要な調整だけ行う ことが重要です。
姿勢循環整体が示す「全体を診る」教育哲学
姿勢循環整体は「身体は一つのユニット」という哲学に基づきます。
教育も同じく「スタッフの全体像」を見ながら、優先順位をつけて育成していくことが求められます。
伴走型教育で変わった導入院の成功事例
ある導入院では、院長が「全部できるように」と詰め込み教育をしていたため、スタッフが次々に辞めていました。
しかし伴走型に切り替え、1つずつ小さなゴールを設定したところ、離職率は激減し、スタッフが自主的に患者対応を学ぶようになりました。
よくある質問

Q. スタッフができないとイライラしてしまいます。どうすればいいですか?
A. 「できないのは当たり前」という前提を持ちましょう。呼吸を整え、伴走者として支える意識に切り替えることが効果的です。
Q. 「甘やかし」と「伴走型教育」の違いは何ですか?
A. 甘やかしは「責任を奪う」教育、伴走は「挑戦を支える」教育です。責任は本人に持たせつつ、失敗を支えるのが伴走型です。
Q. 院長が伴走型教育を取り入れると経営にどう影響しますか?
A. スタッフ定着率が上がり、院長の負担が軽減します。結果として院の雰囲気が良くなり、リピート率も改善します。
まとめ|「できるようになってほしい」より「一緒に成長する」院長へ

- 院長の熱意が強すぎると、スタッフにプレッシャーとなって伝わる
- 「できるようになってほしい」という期待が委縮や離職を招く
- 解決策は「伴走型教育」―小さなゴール設定、問いかけ、心理的安全性
- 平井塾の哲学(FJA・姿勢循環整体)は、この伴走型教育を実現するための土台になる
院長が伴走者に変わると、スタッフは安心して挑戦し、整骨院全体が成長する環境が生まれます。
関連記事
➡︎ 焦りや苛立ちがスタッフ教育を壊す理由を詳しく見る
➡︎ 完璧主義の院長が陥る教育の落とし穴とは?
➡︎ イライラを防ぐ感情マネジメントの実践法はこちら
➡︎ 片方向コミュニケーションがスタッフを潰す原因を知る
➡︎ 教えることがストレスにならない伝え方のコツ
➡︎ 威厳より信頼が大切―スタッフが辞めない院長の在り方
投稿者情報【平井 大樹】

株式会社美絆 代表取締役。みゅう整骨院 代表。整体教育機関ゴッドハンドへの道「平井塾」代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。
「治療家を職業から誇りへ」を信念に、紹介だけで予約が埋まる「本物の治療家」を育てる平井塾を主宰。施術歴20年、延べ10万人以上を施術し、リピート率98.5%、新規予約は5年待ちという圧倒的な実績を持つ。
【平井塾が生まれた理由】
高校卒業後、スポーツトレーナーの世界で「本当に人の役に立ちたい」という強い想いを胸に治療家の道へ。雇われ院長時代には、1日来院数255名という日本一の実績を達成。しかし、数字を追い求める中で、本当にやりたかったこととのギャップに悩み、独立後は広告を一切使わない「紹介のみ」の治療院を確立しました。
その経験から、「技術だけでなく、患者さんの心に寄り添う在り方こそが、真のゴッドハンドへの道である」と確信。2020年から始めたセミナー事業も、広告を一切使わず、口コミだけで年間91回開催、延べ770名もの治療家が集まる場所となりました。
【平井大樹の圧倒的な実績】
私が提唱する「在り方で信頼され、結果で指名される」という哲学は、以下の圧倒的な実績によって証明できる確信しています。
- 長期継続患者数:私が施術している毎月211人の患者様のうち、5年以上継続が211名,そのうち10年以上が93名。これは、一般的な治療院が測る「初回リピート率」をはるかに超える、揺るぎない信頼の証です。当社独自の2年継続率では49.7%という圧倒的な実績を数字で証明しています。
- 独自のメソッド:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)や姿勢循環整体など、単なる技術ではなく、痛みの根本原因を「動きの連鎖」から見抜く独自の臨床思考モデルを確立しています。
- 全国規模の実績:東京、大阪、横浜、宮崎など全国9社の整骨院グループで社員研修を担当。組織の課題に客観的に向き合い、治療家として誇りを持って働ける社員を育成しています。
- 安定した組織運営:私が経営する院のスタッフ定着率は平均7年以上。これは、理念と実践が一致したマネジメントの証明です。
「在り方で信頼され、結果で指名される」
平井塾は、技術と人間性の両輪を磨き、治療家として誇りを持って生きる仲間を増やすことを目標としています。このブログが、あなたの治療家人生を変える一歩となれば幸いです。

