整骨院スタッフ教育で陥りやすい「片方向コミュニケーション」
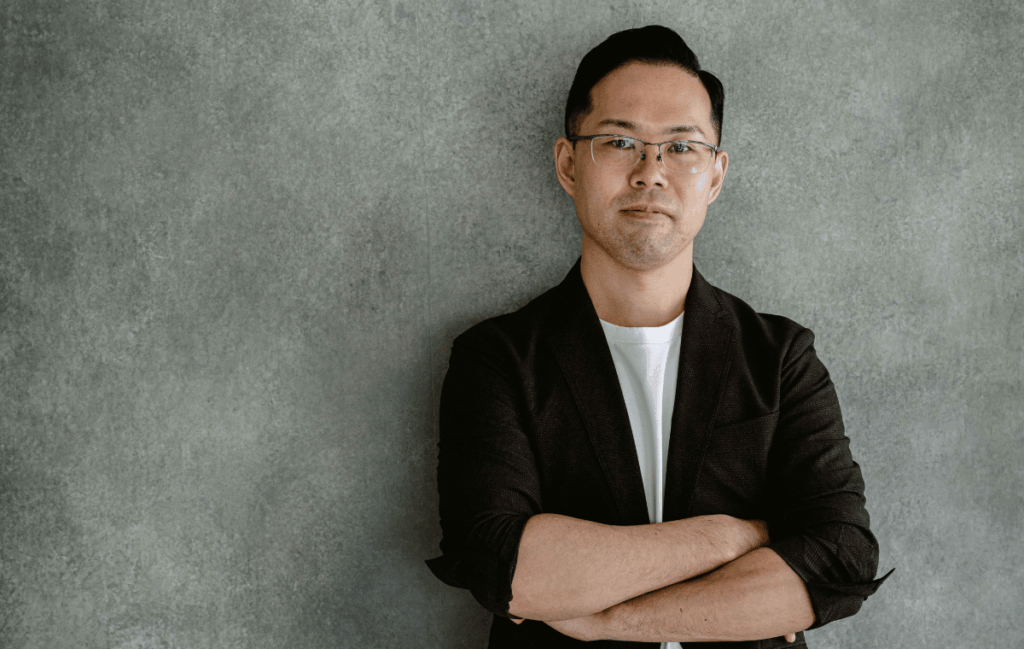
院長が一方的に話す教育スタイルの実態
多くの整骨院院長は「スタッフにできるようになってほしい」という思いから、教育の場で 自分が一方的に説明する ことが多いです。
「こうやるんだよ」「これは違う」「次はこうして」――気づけば院長がずっと話し続け、スタッフは頷くだけ。
一見すると丁寧な指導に見えますが、これは 片方向コミュニケーション に陥っている状態です。
「説明しているのに伝わらない」と感じる背景
院長は「こんなに説明しているのになぜできないんだ」と苛立ちます。
しかし、説明が多いほど理解が深まるわけではありません。
相手の頭に届くのは、聞いた情報の一部にすぎない からです。
スタッフが委縮してしまう心理的メカニズム
一方的に話される環境では、スタッフは「質問してはいけない」と感じます。
「わからない」と言うと怒られる、迷惑をかけると思うからです。
結果として、理解していなくても「はい、わかりました」と答え、成長が止まってしまうのです。
片方向コミュニケーションがスタッフを潰す3つの弊害

質問できない環境が学びを止める
教育で最も危険なのは、スタッフが「質問できない環境」に追い込まれることです。
疑問をその場で解消できなければ、理解は浅いまま進み、後から大きなミスにつながります。
院長の顔色を伺う文化が生まれる
スタッフは「理解していなくても、わかりましたと言う」ようになります。
これは教育における最大の損失です。
院長の顔色を伺いながら働く環境では、スタッフは本音を隠すようになり、信頼関係も崩壊していきます。
主体性のないスタッフを量産してしまう
片方向教育は「言われたことしかやらないスタッフ」を生みます。
主体的に考えず、指示待ちの姿勢が当たり前になってしまうのです。
その結果、院長の負担は増え、経営は安定しなくなります。
整骨院マネジメントに必要な「質問と傾聴」の習慣

「説明する」から「問いかける」へのシフト
教育の基本は「説明」ではなく「対話」です。
「どう感じた?」「なぜそうしたの?」と問いかけることで、スタッフの理解度や思考を確認できます。
傾聴がスタッフの安心感と主体性を育てる
院長が「聴く姿勢」を持つと、スタッフは安心して意見を言えるようになります。
心理的安全性が確保されることで、スタッフは挑戦し、主体性が芽生えます。
双方向コミュニケーションが信頼関係を強化する
対話を通じた教育は「信頼関係」を育てます。
スタッフは「院長は自分を見てくれている」と感じ、学びへの意欲が高まります。
質問と傾聴を取り入れたスタッフ育成の実践法

教育の場で使える具体的な質問例
- 「今の施術で患者さんはどう感じたと思う?」
- 「もし自分ならどう改善する?」
- 「理解度は10点満点中どのくらい?」
こうした質問が、スタッフの考える力を引き出します。
沈黙を恐れず「待つ」姿勢を持つ
問いかけた後、スタッフが答えるまでの沈黙は大切です。
院長がすぐに答えを言ってしまうと、スタッフは思考する時間を失います。
フィードバックは短く、スタッフの言葉を引き出す
フィードバックは「良かった点を具体的に伝える」ことを優先し、短くまとめます。
そして次はスタッフの言葉を引き出すことで、学びが定着します。
片方向教育をやめて変わった整骨院の成功事例

離職率が改善した導入院のケース
ある導入院では、以前は院長が一方的に話す教育スタイルでした。
スタッフが次々に辞めていましたが、質問と傾聴を取り入れたことで離職率が激減。
質問中心の教育でスタッフが自走したケース
「自分はどう思う?」という問いかけを増やしたところ、スタッフが自分で課題を発見し、改善するようになりました。
院長が楽になり、経営が安定したケース
傾聴を取り入れることで、スタッフが主体的に動くようになり、院長が抱えていた業務が分散。
結果として経営も安定しました。
平井塾が提案する「観察と傾聴」の教育哲学

FJAで養う「相手を観察する」姿勢
FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)は「観察と調整」を重視します。
教育でも同じく、相手の理解度を観察し、必要な部分だけ調整することが効果的です。
姿勢循環整体に学ぶ「全体を診る」視点
姿勢循環整体は「身体は一つのユニット」という哲学を持ちます。
教育も「スタッフの全体像」を見ながら、どこに介入するかを考えることが重要です。
「在り方」を整えることでコミュニケーションが変わる
院長が「伝える側」から「聴く側」へと意識を変えることで、教育が根本から変わります。
よくある質問

Q. スタッフが質問してくれないのはなぜですか?
A. 院長の表情や雰囲気が質問を封じている場合があります。まず「質問していいんだよ」と言葉で伝え、傾聴の姿勢を示しましょう。
Q. 傾聴を意識すると教育に時間がかかりすぎませんか?
A. はい、短期的には時間がかかります。しかし中長期的にはスタッフが自走し、院長の負担が軽減されます。
Q. 一方的に教える癖をやめるためのコツは?
A. 「まずは質問から始める」と決めることです。説明より先に問いかける習慣が癖を変えます。
まとめ|質問と傾聴がスタッフ育成を変える

- 片方向教育はスタッフの成長を止め、離職につながる
- 質問と傾聴はスタッフの主体性と安心感を育てる
- 成功事例からも「双方向コミュニケーション」が育成力を高めることがわかる
- 平井塾の哲学は「観察と傾聴」を通じて院長の教育力を高める
関連記事
➡︎ 焦りや苛立ちがスタッフ教育を壊す理由を詳しく見る
➡︎ 完璧主義の院長が陥る教育の落とし穴とは?
➡︎ 「できるようになってほしい」がプレッシャーになる仕組み
➡︎ イライラを防ぐ感情マネジメントの実践法はこちら
➡︎ 教えることがストレスにならない伝え方のコツ
➡︎ 威厳より信頼が大切―スタッフが辞めない院長の在り方
平井塾で学べるスタッフマネジメント術

平井塾では、技術習得だけでなく 院長の教育力と在り方 を磨くプログラムを提供しています。
- 年間91回のセミナーで全国770名以上が学習
- 傾聴と伴走型教育を導入し「離職ゼロ」を実現した院も多数
- 「教育が変われば院が変わる」を体感した成功事例が増えています
👉 一方的な教育から脱却し、スタッフと共に成長できる院長を目指すなら、ぜひ平井塾のセミナーで学んでみてください。
投稿者情報【平井 大樹】

株式会社美絆 代表取締役。みゅう整骨院 代表。整体教育機関ゴッドハンドへの道「平井塾」代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。
「治療家を職業から誇りへ」を信念に、紹介だけで予約が埋まる「本物の治療家」を育てる平井塾を主宰。施術歴20年、延べ10万人以上を施術し、リピート率98.5%、新規予約は5年待ちという圧倒的な実績を持つ。
【平井塾が生まれた理由】
高校卒業後、スポーツトレーナーの世界で「本当に人の役に立ちたい」という強い想いを胸に治療家の道へ。雇われ院長時代には、1日来院数255名という日本一の実績を達成。しかし、数字を追い求める中で、本当にやりたかったこととのギャップに悩み、独立後は広告を一切使わない「紹介のみ」の治療院を確立しました。
その経験から、「技術だけでなく、患者さんの心に寄り添う在り方こそが、真のゴッドハンドへの道である」と確信。2020年から始めたセミナー事業も、広告を一切使わず、口コミだけで年間91回開催、延べ770名もの治療家が集まる場所となりました。
【平井大樹の圧倒的な実績】
私が提唱する「在り方で信頼され、結果で指名される」という哲学は、以下の圧倒的な実績によって証明できる確信しています。
- 長期継続患者数:私が施術している毎月211人の患者様のうち、5年以上継続が211名,そのうち10年以上が93名。これは、一般的な治療院が測る「初回リピート率」をはるかに超える、揺るぎない信頼の証です。当社独自の2年継続率では49.7%という圧倒的な実績を数字で証明しています。
- 独自のメソッド:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)や姿勢循環整体など、単なる技術ではなく、痛みの根本原因を「動きの連鎖」から見抜く独自の臨床思考モデルを確立しています。
- 全国規模の実績:東京、大阪、横浜、宮崎など全国9社の整骨院グループで社員研修を担当。組織の課題に客観的に向き合い、治療家として誇りを持って働ける社員を育成しています。
- 安定した組織運営:私が経営する院のスタッフ定着率は平均7年以上。これは、理念と実践が一致したマネジメントの証明です。
「在り方で信頼され、結果で指名される」
平井塾は、技術と人間性の両輪を磨き、治療家として誇りを持って生きる仲間を増やすことを目標としています。このブログが、あなたの治療家人生を変える一歩となれば幸いです。

