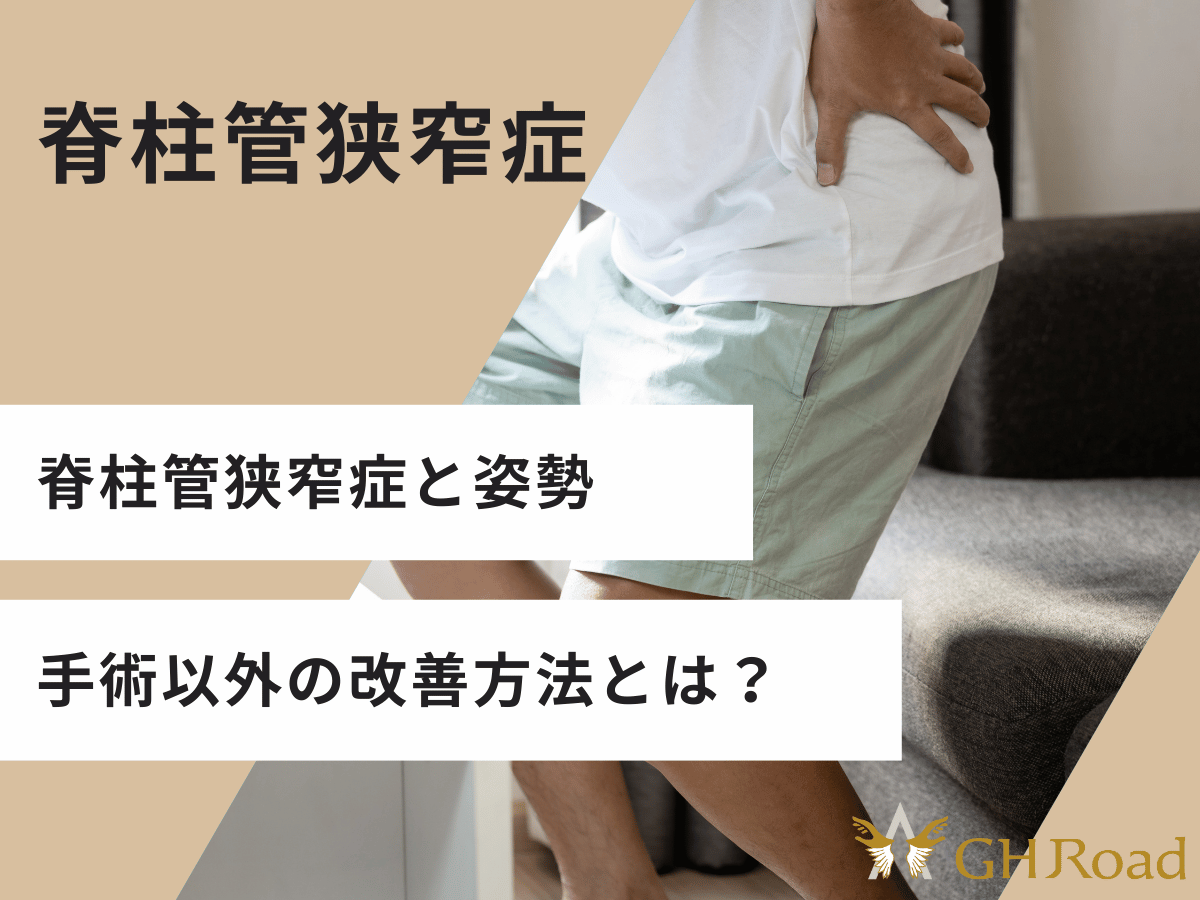「最近、歩いていると腰や足がしびれて長く歩けない…」「病院で脊柱管狭窄症と言われたけど、手術しか方法はないの?」
50代前後の女性を中心に、こうした不安の声をよく耳にします。
脊柱管狭窄症は、背骨の中にある神経の通り道(脊柱管)が狭くなることで、腰や足の痛み・しびれを引き起こす病気です。加齢による変化だけでなく、実は「姿勢の崩れ」や「血流の滞り」が症状を悪化させる大きな要因になっていることをご存じでしょうか。
「もう歳だから仕方ない」「手術しないと歩けなくなる」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。正しい知識とケアによって、手術以外の方法で改善を目指すことが可能です。
本記事では、
- 脊柱管狭窄症の基本情報と症状
- 姿勢や血流との関係
- 手術以外の改善法(整体・ストレッチ・生活習慣)
- 平井塾が提唱する「FJA」と「姿勢循環整体」による根本改善の考え方
についてわかりやすく解説していきます。
20年以上の施術経験と10万回以上の臨床経験をもとに、「痛みを一時的に和らげる」だけでなく「なぜその場所に負担がかかっているのか」を一緒に考え、安心して取り組める改善の道筋をご紹介します。
目次
脊柱管狭窄症とは?基本情報と症状の理解

脊柱管狭窄症の定義と主な症状
脊柱管狭窄症とは、背骨の中を通っている「脊柱管」という神経の通り道が狭くなり、神経や血管が圧迫されることで痛みやしびれを引き起こす病気です。
特に腰の部分で起こる場合を「腰部脊柱管狭窄症」と呼びます。
主な症状には以下のようなものがあります。
- 腰の痛み
- 足のしびれや重だるさ
- 歩くと足がつらくなり、休むと楽になる(間欠跛行)
- 長時間立ち続けられない
こうした症状は「神経が押されている」ことに加え、血流の滞りによっても悪化することがわかっています。
腰部脊柱管狭窄症の特徴
腰部脊柱管狭窄症は、中高年に多く見られる疾患です。50代以降になると、加齢による椎間板の変化や骨の変形が重なり、脊柱管が狭くなってしまうのです。
特徴的なのは「歩行時のつらさ」。最初は数百メートル歩けても、徐々に距離が短くなり「少し歩いただけで休まないといけない」状態に進行する方もいます。
ただし、症状の強さと脊柱管の狭さは必ずしも一致しません。画像診断で強く狭くなっていても症状が軽い方もいれば、逆に軽度の狭窄でも強い症状が出る方もいます。ここに「姿勢」や「体の使い方」が関わっているのです。
症状が及ぼす生活への影響
脊柱管狭窄症になると、
- 長く歩けないことで買い物や外出が困難になる
- 旅行や趣味が制限される
- 痛みやしびれから気分が落ち込みやすくなる
といった生活の質(QOL)の低下が起こります。
「このまま歩けなくなるのでは…」という不安は、多くの患者さんが抱える共通の悩みです。しかし、早めに正しい理解と対処を行えば、日常生活を取り戻せる可能性は十分あります。
脊柱管狭窄症と姿勢の関係

姿勢が脊柱管狭窄症を引き起こす理由
脊柱管狭窄症は「加齢だから仕方ない」と思われがちですが、実は姿勢の崩れが症状の大きな要因になっています。
特に、背骨の自然なカーブが崩れることで脊柱管が狭くなり、神経や血管に余分な圧力がかかるのです。
例えば、猫背や骨盤の傾きが強くなると、腰椎(腰の背骨)に不均等な負担が集中し、神経の圧迫や血流の滞りを招きます。その結果、足のしびれや痛みが悪化するのです。
前傾姿勢と反り腰の影響
脊柱管狭窄症の方に多いのが、
- 前傾姿勢(猫背):背中が丸まり、腰の神経が圧迫されやすくなる
- 反り腰(腰椎前弯の過剰):骨盤が前に傾き、腰の椎間関節に負担がかかる
この両極端な姿勢は、いずれも腰椎のバランスを崩し、脊柱管を狭める原因になります。
一方で「自転車に乗ると楽」「前かがみで台に手を置くと楽」という経験はありませんか?これは前かがみになると脊柱管が一時的に広がり、神経の圧迫が軽くなるためです。つまり、症状の強弱は「姿勢次第」で変わるのです。
座ると痛い?座った時の姿勢改善
座っている時の姿勢も、脊柱管狭窄症の症状に大きく影響します。
長時間のデスクワークやソファに深く沈み込む姿勢は、腰に余計な圧力をかけてしまいます。
改善のポイントは次の通りです。
- 背もたれに深くもたれかかりすぎない
- 座面にタオルを敷いて骨盤を立てる
- 足を組まない
- 長時間同じ姿勢を避け、30分に一度は立ち上がる
このように「日常の姿勢改善」が、手術に頼らない改善法の第一歩となります。
脊柱管狭窄症は姿勢と血流がカギになる理由(平井塾の視点)

前かがみ姿勢が神経や血流に与える影響
脊柱管狭窄症では「神経の圧迫」だけでなく、血流の悪化が大きな問題になります。
背骨の中を通る神経は血管と隣り合って走行しているため、姿勢が崩れることで血液の流れが妨げられ、神経に栄養や酸素が届きにくくなります。
前かがみの姿勢をとると、一時的に脊柱管は広がり楽になりますが、長時間続けると筋肉がこわばり、逆に血流が滞りやすくなります。
つまり、「どんな姿勢を取るか」が神経圧迫と血流の両面に直結しているのです。
姿勢を整えると脊柱管狭窄症の症状が軽くなる仕組み
私たちの体は「骨格のバランス」と「血液・リンパの流れ」が調和しているときに、最も自然に機能します。
姿勢を正しく整えると、
- 神経への圧迫が減る
- 筋肉の余計な緊張が緩む
- 血流やリンパの流れがスムーズになる
このような変化が起こり、しびれや痛みの軽減につながります。
実際に、姿勢を改善するだけで歩行距離が伸びたり、足の冷えやしびれが軽くなったという患者さんは少なくありません。
平井塾の視点
平井塾では「姿勢と血流」を一体のものとして捉えています。
- FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)では、細かい関節や筋膜のエラーを探り、部分的な滞りを解消。
- 姿勢循環整体では、全身の循環を改善するために姿勢を整え、体全体の治癒力を引き出します。
単なる「骨格矯正」や「マッサージ」とは異なり、姿勢と循環を同時に整えるアプローチだからこそ、根本的な改善につながるのです。
手術以外での脊柱管狭窄症改善法

脊柱管狭窄症と診断されると「いずれは手術が必要」と言われ、不安を抱える方が多いですが、すべての方に手術が必要なわけではありません。
症状が軽度〜中等度であれば、保存療法(手術をしない治療)で改善するケースも多くあります。ここでは、手術以外の改善法について解説します。
整体療法の重要性と効果
整体は「骨格や筋肉のバランスを整える」ことで、脊柱管狭窄症の症状改善に役立ちます。特に姿勢の崩れによる神経圧迫や血流の滞りに対しては、整体的なアプローチが効果を発揮しやすいのです。
- 骨盤や背骨の歪みを整える → 神経の通り道を確保しやすくなる
- 筋肉の緊張を緩める → 血流改善と痛みの軽減
- 体の使い方を修正する → 再発予防につながる
平井塾で指導している整体は「痛みのある部分だけを押す」のではなく、全身を診て根本から整えるアプローチを大切にしています。
運動・ストレッチでのアプローチ
脊柱管狭窄症において「体を動かす」ことは非常に重要です。安静にしすぎると筋力が落ち、かえって症状が悪化する可能性があります。
効果的な運動・ストレッチの例:
- 軽い前屈ストレッチ(背中や腰をゆっくり伸ばす)
- 股関節周りを柔らかくするストレッチ
- 体幹を安定させる呼吸法や軽い体操
これらは血流を促進し、神経の圧迫を軽減する助けになります。
ただし、強い痛みを我慢して無理に行うことは逆効果となるため、必ず専門家の指導のもと行うことが推奨されます。
日常生活での姿勢指導
整体や運動だけでなく、日常生活での「姿勢改善」も欠かせません。
- 歩くとき:少し前傾で杖やシルバーカーを使うと楽に歩ける
- 座るとき:骨盤を立てて浅めに座る
- 寝るとき:横向きで膝の間にクッションを挟むと腰の負担が軽減する
こうした小さな工夫が、症状の悪化を防ぎ、改善をサポートします。
平井塾の考え方
整体やストレッチ、姿勢改善は「一度やれば終わり」ではありません。継続して習慣にしていくことで、体が本来の状態を取り戻し、手術に頼らなくても生活の質を高めることができます。
脊柱管狭窄症の悪化を防ぐために
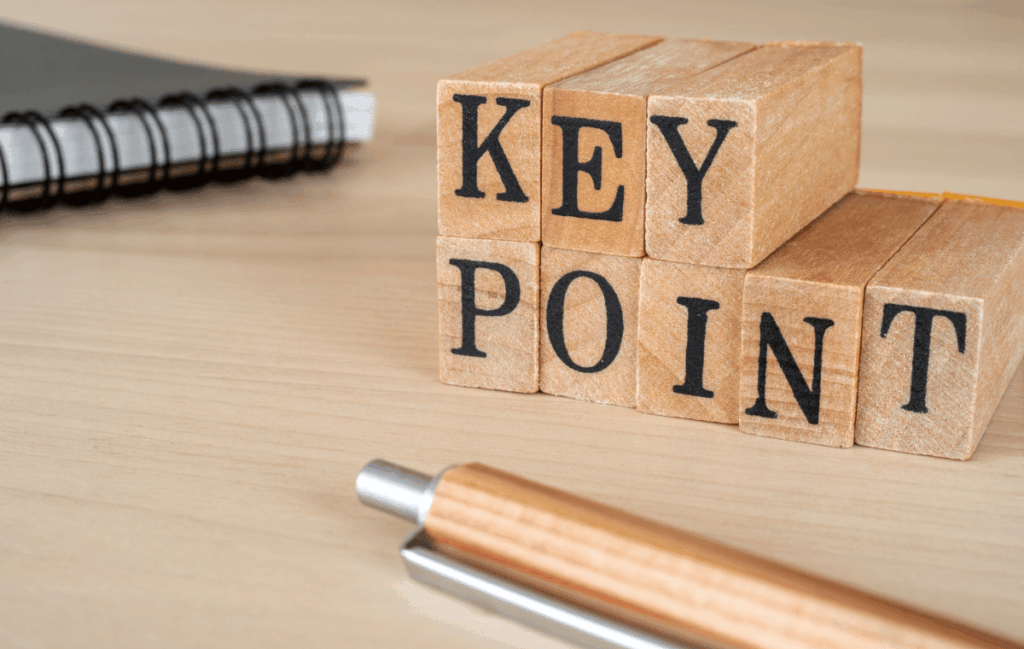
脊柱管狭窄症は、進行すると歩行距離が短くなったり、しびれが強くなったりすることがあります。しかし、日常生活での注意点を守ることで、症状の悪化を防ぎ、改善の道へつなげることができます。
脊柱管狭窄症やってはいけないことと注意点
症状を悪化させる生活習慣には共通点があります。次のような行動は注意が必要です。
- 長時間の立ちっぱなし、歩きすぎ
- 柔らかすぎるソファやベッドに沈み込んで座る・寝る
- 重い荷物を持ち上げるときに腰をひねる
- 運動不足や極端な安静
特に「痛いから動かない」ことは逆効果です。動かないことで筋力や血流が低下し、かえって症状が進むことがあります。
日常生活の中での予防策
一方で、日常生活の中でできる予防法もあります。
- こまめに休憩を取りながら歩く(間欠跛行の症状を和らげる)
- 軽いストレッチを習慣化する(血流改善に効果的)
- 腰に負担をかけない動作を心がける(前かがみで物を取るときは膝を曲げる)
- 椅子や寝具を見直す(骨盤を立てやすい椅子、適度な硬さのマットレスを選ぶ)
小さな習慣の積み重ねが、症状の改善と再発予防に大きな違いを生みます。
定期的な受診の重要性
「もう整体やストレッチで十分だから病院に行かなくてもいい」と考える方もいますが、それは危険です。
脊柱管狭窄症には、手術が必要となるケースも確かに存在します。
- 排尿・排便障害が出ている
- 安静にしていても強いしびれや痛みが続く
- 歩行距離が急激に短くなっている
こうした症状がある場合は、必ず医師の診察を受けることが大切です。
整体と医療の両方をうまく取り入れることで、安全かつ安心して改善の道を進むことができます。
「悪化させないこと」が、改善の第一歩です。無理をせず、しかし止まらずに、姿勢・生活習慣を見直していきましょう。
整体と脊柱管狭窄症の治療法

整体は、脊柱管狭窄症の「手術以外の改善法」として注目される選択肢のひとつです。ただし、整体といっても施術内容や考え方はさまざまで、効果も人によって異なります。ここでは、整体が脊柱管狭窄症にどのように関わるのかを整理します。
医療機関における整体療法
一部の医療機関やクリニックでは、リハビリの一環として「徒手療法(手による調整)」や「運動指導」が行われています。
これは整体的な考え方に近く、
- 腰椎や骨盤周囲の柔軟性を取り戻す
- 筋肉の過緊張を和らげる
- 正しい動作の習慣を身につける
といった目的があります。
医師の管理下で行う場合、安全性が高く、必要に応じて薬物療法や注射と組み合わせられる点もメリットです。
整体におけるストレッチとリハビリ
整体院や専門家による施術では、ストレッチや関節調整を通じて神経や血流の通りを改善していきます。
よく行われるのは、
- 股関節や太ももの筋肉を柔らかくするストレッチ
- 骨盤のバランスを整える調整
- 背骨の動きを引き出す軽い関節モビライゼーション
これにより、歩行時のつらさが軽減し、生活の質が上がるケースもあります。
ただし「強く押す」「バキバキ鳴らす」施術は、かえって症状を悪化させるリスクがあるため注意が必要です。安全に、やさしく体を整えていく整体が望ましいといえます。
脊柱管狭窄症に合った整体院の選び方
脊柱管狭窄症で整体を検討する際には、次のようなポイントが重要です。
- 医学的知識があるか(必要に応じて医療機関を勧めてくれるか)
- 姿勢や全身をみてくれるか(痛い部分だけを扱うのではないか)
- 継続的なセルフケア指導があるか
平井塾が推薦する整骨院・整体院では、「痛みを取ることだけ」を目的とせず、体全体を診て根本から整える手技を大切にしています。
そのため、患者さん自身が安心して体の回復に取り組めるのです。
整体は「魔法のように一度で治すもの」ではなく、姿勢改善・血流改善・生活習慣の見直しを支える役割を果たします。正しい整体院と出会うことが、改善への近道になります。
平井塾の考える根本改善アプローチ

脊柱管狭窄症の改善を考えるとき、「痛みを取ること」だけを目的にしてしまうと、本当の解決には至りません。
なぜなら、症状は「結果」であり、その背景には姿勢・循環・体の使い方のエラーが潜んでいるからです。
平井塾では20年以上、10万回以上の臨床経験を通じて、独自の手技と哲学を育んできました。その中心にあるのが、FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)と姿勢循環整体です。
FJAで細部のエラーを見つける
FJAは、体の細かい関節や筋膜(ファシア)の動きに注目する手技です。
脊柱管狭窄症の場合、腰そのものだけでなく、
- 股関節の硬さ
- 胸椎や骨盤の歪み
- 足首や肩甲骨の動きの悪さ
といった「一見関係なさそうな部位」が、実は腰に負担を集中させていることがあります。
FJAは、このような体の細部のエラーを手で聴き分けることで、本当の原因を探し当てます。
強く押したり、無理に矯正したりするのではなく、「観察と対話」のように体と向き合うことが特徴です。
姿勢循環整体で全身の血流を改善する
FJAで細部を調整した後は、全身の姿勢と循環を整える「姿勢循環整体」を行います。
これはオステオパシーの哲学に基づき、
- 血液やリンパの流れ
- 神経の働き
- 内臓の動き
といった生理的機能を改善するアプローチです。
同じ手技の流れを全員に行うため、施術者は手数を増やしながら上達でき、患者さんにとっては全身のバランスが整う安心感を得られます。
「細部」と「全体」を組み合わせることで、体の治癒力が高まり、症状の根本改善につながるのです。
信頼関係と施術の安心感が回復力を高める
平井塾が大切にしているのは、技術だけではありません。
「患者さんの体を聴く傾聴する手」という考え方を通じて、施術者と患者さんの間に信頼関係を築くことを重視しています。
人は安心すると副交感神経が働き、血流や回復力が自然に高まります。
つまり、信頼できる施術者と共に体を整えていく安心感こそが、改善への大きな力になるのです。
FJAで原因を見つけ、姿勢循環整体で全身を整え、信頼関係によって安心を得る。
この三つが揃ったとき、脊柱管狭窄症の改善は「単なる対処」から「根本改善」へと進んでいきます。
実際に改善した方のケース

脊柱管狭窄症は「手術しかない」と言われがちですが、実際には姿勢や循環を整えることで改善した例が多く存在します。ここでは、50代女性のケースをご紹介します。
歩行距離が伸びた60代女性のエピソード
この方は、数年前から腰の痛みと足のしびれに悩まされていました。病院で「腰部脊柱管狭窄症」と「側弯症」「すべり症」と3つの診断を言われ、手術を勧められたものの「できれば手術は避けたい」との思いで来院されました。
初診時の状況:
- 200メートルほど歩くと足がしびれて休まなければならない
- 長時間の買い物や外出は困難
- 不安から気分も落ち込みがち
平井塾の整体アプローチを受けていただいたところ、
- FJAで股関節・骨盤周囲の硬さを調整 → 腰の負担が減少
- 姿勢循環整体で全身の血流を改善 → 足の冷えやしびれが軽減
- 日常生活での姿勢指導 → 腰に負担をかけない座り方・歩き方を習得
これらを継続していく中で、徐々に歩行距離が伸び、半年後には1キロ以上歩けるようになったのです。今では、3人の孫と旅行に出かけても症状が出ない状況をキープすることができています。
ポイント
- 狭窄そのものを「広げる」ことはできなくても、姿勢と血流を改善することで症状は大きく変わる
- 「できないこと」が減ると気持ちに余裕が生まれ、回復がさらに加速する
- 手術を避けたい方にとって、整体は有効なサポートになり得る
脊柱管狭窄症に関する質問と回答

脊柱管狭窄症に悩む方から、よくいただく質問をまとめました。
間欠跛行とは?
Q:歩くと足がしびれるのに、少し休むとまた歩けるのはなぜですか?
A:これを「間欠跛行(かんけつはこう)」と呼びます。歩いているときに神経や血管が圧迫され、痛みやしびれが出る状態です。休むと脊柱管が広がり、血流が改善して症状が和らぐため、再び歩けるようになります。脊柱管狭窄症の代表的なサインの一つです。
血流改善のための生活習慣とは?
Q:整体以外に、普段の生活でできることはありますか?
A:はい。血流を良くする工夫は症状の軽減に役立ちます。
- ウォーキングなどの軽い有酸素運動
- 股関節やふくらはぎのストレッチ
- 深い呼吸を意識して副交感神経を働かせる
- 水分をしっかり摂る
こうした習慣を取り入れることで、血流が促進され、しびれや痛みが軽くなることがあります。
専門医への相談が必要な症状
Q:整体で改善できないケースはありますか?
A:はい。以下のような症状がある場合は、すぐに医師へ相談することが必要です。
- 尿や便のコントロールができなくなっている
- 強いしびれや痛みが安静時にも続いている
- 急激に歩行距離が短くなっている
これらは重度の神経障害のサインであり、手術を含めた医療的処置が必要になる可能性があります。
まとめ
- 「歩くとつらいけど休むと楽になる」=間欠跛行
- 血流改善は生活習慣の工夫でも可能
- 一部の症状は医療機関との連携が必須
整体と医療を適切に使い分けることで、安全に改善の道を歩むことができます。
医療機関との連携も大切に
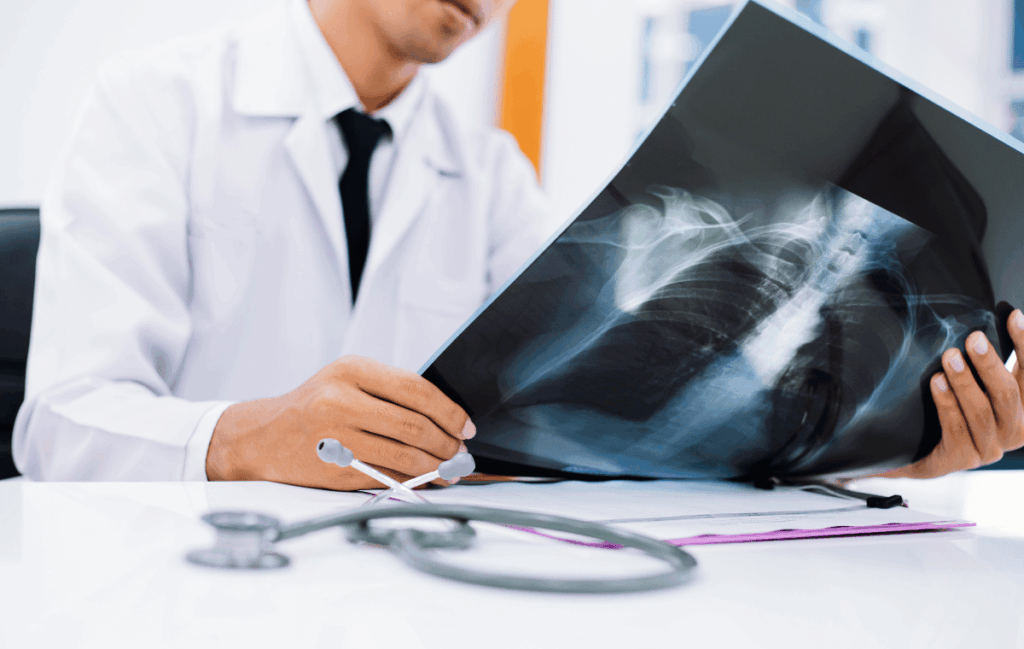
脊柱管狭窄症の改善には、整体や生活習慣の見直しが大きな力を発揮しますが、同時に医療機関との連携も欠かせません。
「整体だけでなんとかしよう」と考える方もいますが、症状によっては医師の診断や治療が必要なケースもあるからです。
手術が必要なケースについて
次のような場合には、整体や保存療法だけで対応するのは難しく、手術を検討すべきサインとなります。
- 排尿・排便がコントロールできない
- 強いしびれや痛みが常に続いている
- 足に力が入らず、歩行が困難になっている
これらは神経へのダメージが進行している可能性が高く、早急な対応が求められます。
安心して選択できるように
平井塾では「手術をしない道」だけを推奨するのではなく、患者さんにとって最も安心できる選択を大切にしています。
- まずは姿勢や循環を整える整体的アプローチを行う
- 必要に応じて医師への受診をすすめる
- 医療と整体の両輪で、患者さんが安心して取り組める環境を整える
これが「患者さん本位の医療・整体のあり方」だと考えています。
平井塾のスタンスは、「整体で改善できる方もいるし、医療の力が必要な方もいる」
大切なのは「どちらを選ぶか」ではなく、「安心して自分の体を任せられる選択肢を持つこと」です。
まとめ:脊柱管狭窄症の理解と改善への道
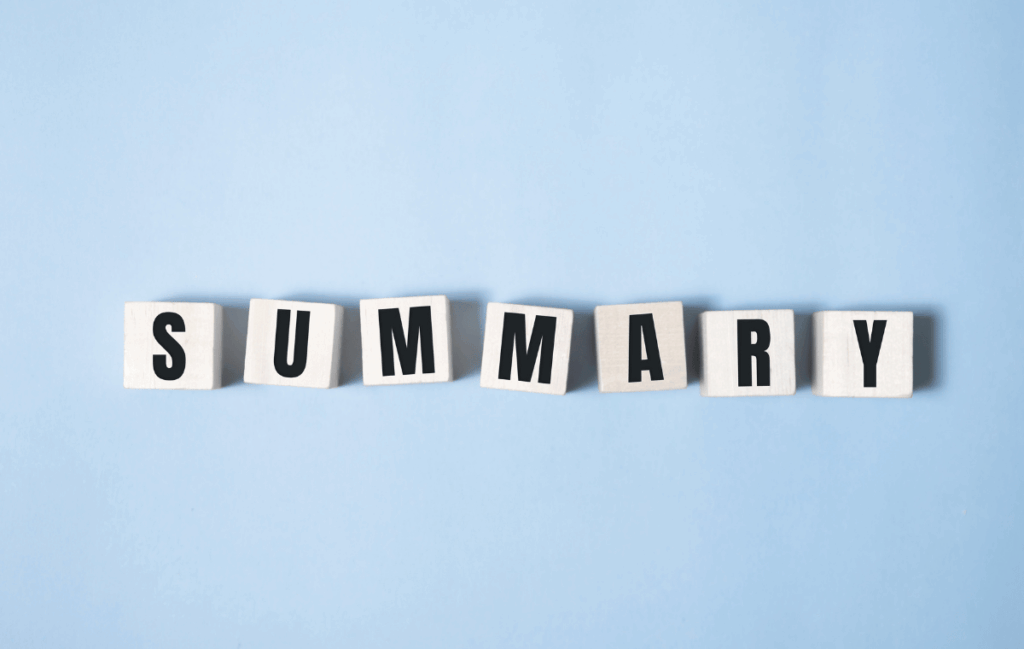
脊柱管狭窄症は「加齢だから仕方ない」「手術しかない」と思われがちですが、実際には姿勢の改善と血流の回復によって、症状が軽減する可能性があります。整体や生活習慣の見直しは、そのための大きな力となります。
姿勢改善の重要性の再確認
姿勢が崩れると神経や血管が圧迫され、痛みやしびれが強くなります。
逆に、姿勢を整えることで圧迫が減り、血流が改善し、症状は和らぎます。
「骨格のバランス」と「血流」を意識することが、改善の第一歩です。
生活習慣の見直しを
整体や運動だけでなく、毎日の生活習慣も症状の改善に直結します。
- 長時間同じ姿勢を避ける
- 軽いストレッチや体操を取り入れる
- 椅子や寝具を見直す
- 水分を十分にとる
こうした小さな工夫が、長期的に大きな違いを生みます。
平井塾では、痛みのある部分だけに注目せず、全身を診て根本から整えるアプローチを大切にしています。
FJAと姿勢循環整体を通じて、体の声を聴き、姿勢と血流を同時に改善することで、手術以外の道を模索できるのです。
「もう歩けなくなるかもしれない」という不安を抱えている方へ。
安心して体を預けられる施術者と出会い、希望を持って改善に取り組んでいただきたいと願っています。
関連記事
さらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
👉 猫背はなぜ腰に悪い?姿勢と腰痛の深い関係
👉 血流が悪いと痛みは強くなる?整体で循環を改善する考え方
👉 冷えとしびれの関係|整体でできる血流改善の方法
👉 脊柱管狭窄症の手術で後悔しないために|保存療法と整体という選択肢
👉 脊柱管狭窄症の代表症状『間欠性跛行』とは?歩行時の痛みと対処法
投稿者情報:平井 大樹

みゅう整骨院 代表。平井塾 代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。
「患者様の人生に、心からの安心を。」
私は、これまで20年間、延べ10万人を超える患者様と向き合ってきました。その中で最も大切にしてきたのは、「痛みを取る」ことだけではなく、「患者様が心から安心して過ごせる毎日を取り戻す」ことです。
- 長期にわたる信頼:みゅう整骨院には、5年以上通われる方が308名、10年以上通われる方も100名いらっしゃいます。これは、一時的な改善ではなく、患者様が私たちに一生の健康を任せてくださっている証です。
- 根本的なアプローチ:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)、姿勢循環整体という独自の手技で、痛みの箇所だけでなく、その根本原因である身体全体の歪みや動きの不調にアプローチします。
- 平井の予約が取れない理由:開業後、患者様の紹介がメインで予約が満員になりました。2020年以降、新規予約は5年待ちの状態です。現在、新規予約を取る予定はありませんが、みゅう整骨院または、平井塾受講生から同じ施術を受けることができます。
このコラムが、あなたの不調を改善し、より豊かな毎日を送るための一歩となれば幸いです。