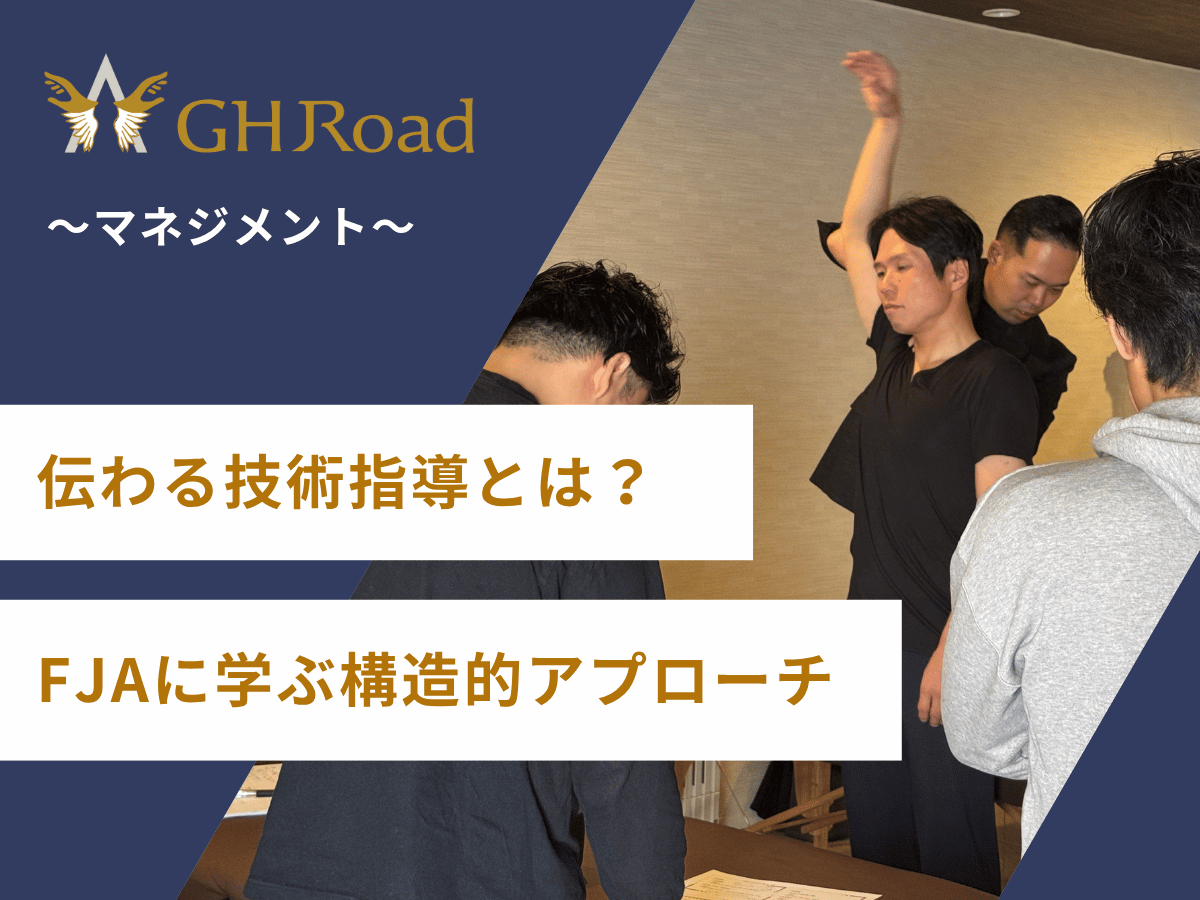「何度教えても、なかなか技術が伝わらない…」
「教えた通りにやってくれない…」
「結局、自分がやった方が早いと思ってしまう…」
そんな悩みを抱えている整骨院の院長や施術家の方は、決して少なくありません。
技術力には自信がある。施術結果も出している。
でも、「教える」となるとうまくいかない。
このギャップは、単なるコミュニケーションの問題ではなく、指導そのものに「構造」がないことが原因かもしれません。
実は、技術指導がうまくいかない多くのケースで見落とされているのが、「伝わるための仕組み」=構造的なアプローチです。
本記事では、平井塾の基礎手技であるFJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)に学びながら、整骨院現場において伝わる技術指導とは何か?を徹底的に掘り下げていきます。
FJAが大切にしている「観察」「調整」「対話」の臨床的アプローチは、実はスタッフ教育にもそのまま応用できる教える技術の原理原則でもあります。
「スタッフが育たない」のではなく、「育つ構造がないだけ」。
そう捉え直すことで、技術指導の手応えは大きく変わります。
なぜ「技術が伝わらない」のか?整骨院にありがちな指導の落とし穴
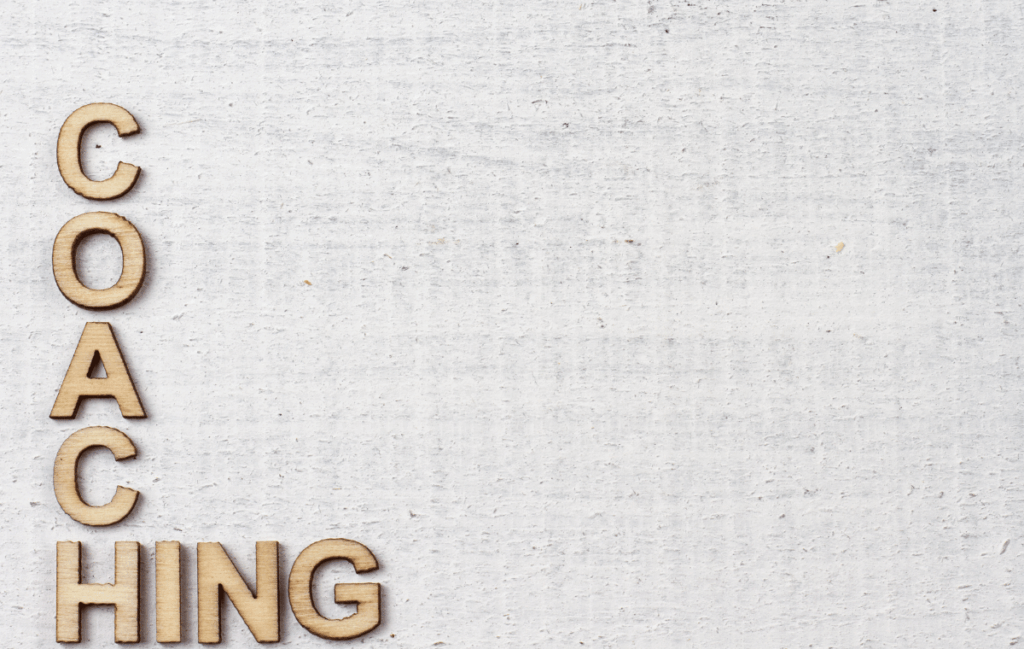
技術が伝わらない、それはスタッフ側の「理解力の低さ」や「やる気の問題」だと決めつけていませんか?
確かに、受け手の姿勢や性格の違いはあります。
しかし、本質的な問題は指導する側の構造にあるケースが圧倒的に多いのです。
技術力と指導力は、別物。
どれだけ施術の腕があっても、それを「伝える力」「育てる力」がなければ、院の成長は頭打ちになります。
教えたつもりになっていないか?
よくある落とし穴のひとつが、「自分は教えた」と思い込んでしまうことです。
- 「こうやってやるんだよ」と一回見せただけ
- 手順を口頭で伝えただけ
- ミスをした時にその場で指摘しただけ
これらは「情報を渡した」だけで、理解され、再現される状態には至っていないのです。
つまり、「教えた」と「伝わった」は、まったく別の現象です。
「できない」のは相手の理解力ではなく、伝え方の構造エラー
教えたことができないスタッフに対し、
「何度言っても覚えない」
「素質がないんじゃないか」
と感じてしまうことはありませんか?
しかし実際には、
- 手順が多すぎて整理されていない
- 言語だけで感覚を伝えようとしている
- 具体性がなく、イメージが湧かない
など、伝える側の「設計ミス」が原因である場合が多くあります。
この状態を放置して繰り返し指導しても、成果が出るどころか、スタッフの自信は失われ、院長のストレスも蓄積していきます。
技術指導は感覚ではなく構造で伝える時代へ
昔は「見て覚えろ」「数こなせば体に染みる」という指導が主流でした。
しかし、今の若手スタッフにそれが通用する時代ではありません。
技術も教育も、属人的なセンスではなく、再現性のある構造的アプローチが求められています。
- 何を見て、どう判断し、どこをどう動かすのか?
- その判断はどんな原則に基づいているのか?
- なぜその順番で行うのか?
こうした「見えない思考や意図」を、見えるかたちで伝える構造を持っていなければ、どれだけ優れた技術でも、継承されることはありません。
FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)とは?

「構造的な指導」と聞いても、具体的にどうすればいいのか分からない。
そんな院長・施術家の方にとってヒントになるのが、平井塾の基礎手技「FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)」です。
FJAは、単なる手技テクニックではなく、「構造を見る目」と「臨床思考」を育てるためのフレームワークであり、その哲学やアプローチは、技術指導やマネジメントにも大きく応用できます。
平井塾が提唱する構造思考の臨床技術
FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)は、「身体構造の微細なエラーにアプローチする調整技術」として設計されています。
大きな力や派手な動きではなく、観察→判断→最小限の調整という、臨床における本質的な対応力を重視するのが特徴です。
- どこに構造の歪みがあるのか?
- それがどのように全体に波及しているのか?
- どのタイミングで、どの関節にアプローチすべきか?
このような構造に対する仮説力と的確なアプローチを培うFJAは、まさに「見えないものを見えるようにする訓練」であり、それはそのまま「教える力」=伝える構造にも直結します。
「観察と調整の対話」が技術を磨き、伝える力も育てる
FJAにおいて最も重要とされるのが、観察と調整の対話です。
つまり、施術者が身体と向き合いながら、微細な変化を見逃さず、それに対して最適な対応を選び取っていく。
このアプローチは、実はスタッフ指導においても同じことが言えます。
- スタッフの理解度、動作の癖、思考の偏りを「観察」する
- そのズレを責めるのではなく、調整する視点で接する
- フィードバックを通じて、理解と行動の質を高めていく
つまりFJAは、「施術する力」を育てると同時に、「育てる施術者」=指導者としての基盤も鍛える手技だと言えます。
「施術者の在り方」がスタッフ指導にも反映される理由
FJAでは、どんな手技を使うか以上に重要視されるのが、「施術者の在り方」です。
- 観察力
- 客観性
- 主観を手放す姿勢
- 柔軟性と一貫性のバランス
これらはそのまま、スタッフ育成においても重要な要素です。
「なんでできないんだ!」と怒るのではなく、「どこにズレがあるのか?」を静かに見極め、調整していく。
技術を押しつけるのではなく、導くことができるかどうか。
それが、FJAの哲学であり、教育における信頼の土台でもあるのです。
FJAに学ぶ構造的アプローチで、伝わる技術指導を実現する方法

「伝える力」には、センスや経験が必要だと思われがちですが、FJAが教えてくれるのは、再現可能な構造に基づいた指導の仕方です。
ここでは、FJAの臨床的プロセスを技術指導に応用し、どのように伝わる指導が実現できるのかを、4つのステップで解説します。
ステップ①:観察 → 相手の理解度・癖・反応を見抜く
まず最初に必要なのは、「どこがズレているか」を的確に観察する力です。
- 手技の手順は覚えているか?
- 動作の一つひとつに「意図」があるか?
- フィードバックにどんな反応をしているか?
この観察をせずに「説明が足りない」「練習が甘い」と断定するのは、患者を診ずに施術をするのと同じです。
FJAと同様に、まずは構造の把握から始めましょう。
相手の理解のフェーズ(初見/練習中/応用)を把握すれば、伝え方も変わります。
ステップ②:分析 → どの部分にズレがあるかを明確にする
次に行うべきは、ズレの原因分析です。
- 頭では理解しているが、身体に落ちていない?
- 説明は受けているが、動作の意図がつかめていない?
- 手技の流れではなく、構造の意味が分かっていない?
このように、どの層で詰まっているかを分解して見る力が、指導には欠かせません。
FJAの臨床では「構造→エラー→機能障害→症状」と因果を追いますが、教育もまた「思考→理解→実行→定着」という構造を追うものです。
ステップ③:フィードバック → 言語・身体・感覚で伝える三方向アプローチ
ズレが明確になったら、それに応じた三方向フィードバックを活用しましょう。
- 言語的フィードバック
例:「今の手順は正しいけれど、体の重心が左に流れているよ」 - 身体的フィードバック
例:動作を一緒に行って、正しい位置を身体に刻ませる - 感覚的フィードバック
例:「このとき、指先にどんな反応が返ってきた?」と問いかける
これにより、脳・身体・感覚の三方向から学習が進み、定着率が飛躍的に上がります。
FJAの「構造と反応の対話」と同様に、指導においても一方通行の説明ではなく、相互的な感覚の共有が鍵となります。
ステップ④:定着 → ルーティンと内省で型を身につける
最後のステップは、伝えたことを「使える型」として定着させるフェーズです。
- 朝練での型の再現ルーティン
- 終業後のセルフチェック習慣
- フィードバックをもとにした修正練習
これらを通じて、「伝えた内容」がその人の技術として定着していきます。
重要なのは、繰り返しの中で考えるクセを育てること。
平井塾の指導でも強調されるように、ルーティンの中に内省を組み込むことで、自走型のスタッフが育ちます。
スタッフが育たないのではなく、育てる構造がないだけ

「うちのスタッフは育たない」
「人材に恵まれない」
そんな声を耳にすることがありますが、本当にそうでしょうか?
もしかすると、問題はスタッフの能力ではなく、育成の仕組みそのものにあるかもしれません。
技術が伝わらない。
成長が感じられない。
その根本原因は、偶発的な育成に頼っていることにあるのです。
個人差を見極める「観察力」が技術者としても教育者としても鍵
スタッフ一人ひとりには、理解の仕方・習得スピード・得意な学び方に違いがあります。
- 頭で理解してから動けるタイプ
- 実践しながら感覚で覚えるタイプ
- 細かい説明より全体像を重視するタイプ
それぞれの特性を無視して画一的な教え方をしても、育ちません。
FJAが構造の微細なズレを観察して調整するように、スタッフの学びの構造を見極め、そこに合った指導を行う。
この観察力こそが、技術者としての視点を教育者にも活かす鍵になります。
指導者が変われば、スタッフの行動が変わる
「育てるのが苦手」「伝えるのが下手」と感じる院長ほど、伝え方の構造を見直すだけで、スタッフがガラリと変わるケースは珍しくありません。
なぜなら、スタッフの多くはできないのではなく、「理解できていない」「何を求められているかが曖昧」という状態にいるからです。
FJAのように、施術者側が変化すれば、クライアントの反応が変わるのと同じく、指導する側が変われば、育つ側の動きも変わるのです。
信頼と安心が「挑戦できる空気」を作る
スタッフが自分から練習したり、質問したり、チャレンジする環境には共通点があります。
それは、安心して間違えられる空気があることです。
「怒られるかも」「否定されるかも」という恐れがある環境では、スタッフは守りの姿勢になり、学習も成長も止まってしまいます。
FJAのように、
- 丁寧に観察し、
- 的確に調整し、
- 相手と対話を通じて関係性を築く
この姿勢が、指導にも信頼を生み出し、挑戦できる風土を作るのです。
FJA指導で成果を出している導入院の声

「理論はわかるけど、本当に現場で効果が出るの?」
そんな疑問を抱く方もいるかもしれません。
ここでは、FJAの構造的指導アプローチを実際に導入し、成果を出している整骨院の事例をご紹介します。
技術の伝え方を変えただけで、ここまで現場が変わる。
それを体感した現場のリアルな声です。
例①:技術に自信がなかった新人が、FJAで自走型スタッフに成長
ある整骨院では、新卒1年目のスタッフが「技術に自信がなく、指導してもすぐに迷ってしまう」という課題を抱えていました。
以前は「数をこなせば覚える」「失敗は繰り返して慣れるしかない」といった指導法が中心でしたが、FJA導入後、スタッフの理解度に合わせて観察→分析→フィードバックの構造を整備。
すると、次第に本人の理解が深まり、半年後には「どこがズレているか」を自分で言語化できるようになりました。
結果として、患者対応にも余裕が生まれ、2年目には技術練習のリーダーとして後輩指導にも参加するように。
例②:指導に悩んでいた院長が、構造思考を取り入れて組織が変化
別の導入院では、分院長が「スタッフの育成がうまくいかず、自分ばかりが忙しくなってしまう」という悩みを抱えていました。
本人は技術に優れ、情熱的な指導者でしたが、「教えているのに伝わらない」「育ってくれない」ことにストレスを感じていたのです。
FJAの「構造エラーにアプローチする」考え方を指導にも応用し、指導フロー・観察ポイント・改善フィードバックをルーティン化したところ、数ヶ月で「教えることに余裕ができた」「スタッフからの質問が具体的になった」との変化が見られました。
結果的に、業務の属人化が減り、チームで技術を磨く文化が育ち始めたのです。
「伝え方」が変わると「育ち方」が変わる
どちらの事例にも共通していたのは、「伝える内容」よりも「伝える構造」が整ったこと。
FJAが教えてくれるのは、施術の構造を見る視点だけではなく、人が変化・成長するプロセスそのものを“構造として捉える”という臨床的思考法です。
「なんでできないんだ」から「どこで詰まっているんだ」へ。
その視点の転換こそが、スタッフを育て、院を育てる第一歩になるのです。
まとめ|伝わる指導は、技術ではなく在り方と構造で決まる

スタッフに技術を教えるとき、私たちはどうしても「何を伝えるか」に意識が向きがちです。
もちろん、手技の内容や理論も重要ですが、それ以上に重要なのが、どう伝えるかという構造と、それを支える指導者の在り方です。
「うまく教えられない」は才能の問題ではない
技術が伝わらない、スタッフが育たない。
そのときに「自分は教えるのが下手だ」「向いていない」と感じてしまうこともあるかもしれません。
しかし、FJAの臨床と同じように、ズレている構造を正すという視点を持てば、指導も上達します。
才能ではなく、
- 観察する力
- ズレを見抜く力
- 伝え方を設計する力
これらはすべて、鍛えることができる技術なのです。
FJAが教えてくれる、伝えるも技術であるという視点
FJAは、施術の技術であると同時に、考え方の技術であり、関わり方の技術でもあります。
- どう見て
- どう判断して
- どう伝えていくか
それはそのまま、スタッフ指導の質を決める視点になります。
「触れる技術」だけでなく「伝える技術」もまた、構造化できる。この視点こそ、院の未来を左右する大きな鍵です。
平井塾で学べる教える力とは?
平井塾では、FJAや姿勢循環整体といった技術指導を通して、臨床家としての腕と教育者としての力を同時に育てるカリキュラムを用意しています。
- スタッフが育つ仕組みを作りたい
- 指導にストレスを感じている
- チームで技術力を高めたい
そんな院長・施術家の方にこそ、ぜひ一度体験していただきたい指導体系です。
技術も、指導も、そして院の文化も、構造が変われば結果が変わる。
Q&A|スタッフ指導に悩む整骨院院長のよくある質問

ここでは、実際に平井塾に寄せられる整骨院の院長先生方の技術指導に関する悩み・疑問にお答えします。
現場であるあるな場面だからこそ、構造的に対処する視点が重要です。
Q:施術ができても、教えるのがうまくなりません…
A:それは「感覚」で教えようとしているからかもしれません。
施術は感覚で覚えてきたとしても、指導は感覚では伝わりません。
FJAが教えるように、技術には構造があります。
教える際は、
- どのステップで詰まっているかを観察し
- 理解の段階に合わせた伝え方を設計し
- 再現性のある形で型を身につけさせる
この流れを意識することで、指導も技術として上達していきます。
Q:スタッフによって理解度に差があるときは、どう対応すべきですか?
A:まずは学び方の違いを観察し、それに合わせたアプローチをしましょう。
- 言語で理解するタイプ
- 体験で覚えるタイプ
- 一度で飲み込める人と、繰り返しが必要な人
FJAでは、構造を見てどこがずれているかを見極めますが、指導でも同様に、「このスタッフは今どこで止まっているか?」を観察する力が重要です。
「全員に同じ教え方」でうまくいかないのは当然です。
個別最適化された伝え方を模索してこそ、スタッフの成長が加速します。
Q:FJAは新人スタッフにも有効ですか?
A:むしろ、新人こそFJAの構造思考に早く触れるべきです。
FJAは、単なる技術習得ではなく、
- 身体の見方
- 臨床の組み立て方
- 思考プロセスの型化
これらを学ぶ臨床教育のフレームです。
新人のうちからこの視点を持つことで、
- 「技術をマネする」から「構造を理解する」へ
- 「正解を探す」から「仮説を立てる」へ
と、思考の質が格段に向上します。
導入院では、新人にFJAの視点を教えたことで教えなくても自分で気づける人材に成長したという事例もあります。
技術が伝わる仕組みを学びたい方へ|平井塾で「教える力」を手に入れよう

「教えているのに伝わらない」
「何度も指導しても、スタッフの動きが変わらない」
「技術を教えることに自信が持てない」
そんな悩みを感じているなら、必要なのは才能でも根性でもありません。
構造的に伝える技術を学び、実践できる仕組みを持つことです。
平井塾では、FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)を通じて、
- 技術の構造化
- 指導プロセスの設計
- 成長を引き出すフィードバック技術
を体系的に学べる講座を提供しています。
平井塾で学べる3つの指導力
- 伝える内容を構造化する力
→「どうしてそうするのか?」を明確に言語化できる - スタッフの成長段階を観察する力
→「どこで詰まっているか?」を見抜いて適切にサポート - 再現性あるルーティンを設計する力
→ 誰でも、段階的に学べる型を提供できる
技術を伝えることに苦手意識がある方も、「体系的に教える力を磨きたい」という前向きな方も、ぜひ一度、平井塾の講座をご覧ください。
あなたの「教え方」が変われば、スタッフの「育ち方」も、院の「未来」も、必ず変わります。
▶ FJAベーシック講座の詳細はこちら
▶ 平井塾の講師紹介はこちら
関連記事
➡︎ 怒らずに伝える技術|整骨院マネジメントに効く非暴力的コミュニケーションとは?
➡︎ 整骨院の院長に求められるリーダーシップの条件とは?
投稿者情報【平井 大樹】

株式会社美絆 代表取締役。みゅう整骨院 代表。整体教育機関ゴッドハンドへの道「平井塾」代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。
「治療家を職業から誇りへ」を信念に、紹介だけで予約が埋まる「本物の治療家」を育てる平井塾を主宰。施術歴20年、延べ10万人以上を施術し、リピート率98.5%、新規予約は5年待ちという圧倒的な実績を持つ。
【平井塾が生まれた理由】
高校卒業後、スポーツトレーナーの世界で「本当に人の役に立ちたい」という強い想いを胸に治療家の道へ。雇われ院長時代には、1日来院数255名という日本一の実績を達成。しかし、数字を追い求める中で、本当にやりたかったこととのギャップに悩み、独立後は広告を一切使わない「紹介のみ」の治療院を確立しました。
その経験から、「技術だけでなく、患者さんの心に寄り添う在り方こそが、真のゴッドハンドへの道である」と確信。2020年から始めたセミナー事業も、広告を一切使わず、口コミだけで年間91回開催、延べ770名もの治療家が集まる場所となりました。
【平井大樹の圧倒的な実績】
私が提唱する「在り方で信頼され、結果で指名される」という哲学は、以下の圧倒的な実績によって証明できる確信しています。
- 長期継続患者数:私が施術している毎月211人の患者様のうち、5年以上継続が211名,そのうち10年以上が93名。これは、一般的な治療院が測る「初回リピート率」をはるかに超える、揺るぎない信頼の証です。当社独自の2年継続率では49.7%という圧倒的な実績を数字で証明しています。
- 独自のメソッド:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)や姿勢循環整体など、単なる技術ではなく、痛みの根本原因を「動きの連鎖」から見抜く独自の臨床思考モデルを確立しています。
- 全国規模の実績:東京、大阪、横浜、宮崎など全国9社の整骨院グループで社員研修を担当。組織の課題に客観的に向き合い、治療家として誇りを持って働ける社員を育成しています。
- 安定した組織運営:私が経営する院のスタッフ定着率は平均7年以上。これは、理念と実践が一致したマネジメントの証明です。
「在り方で信頼され、結果で指名される」
平井塾は、技術と人間性の両輪を磨き、治療家として誇りを持って生きる仲間を増やすことを目標としています。このブログが、あなたの治療家人生を変える一歩となれば幸いです。