整骨院を経営していると、どうしても「人」に悩まされる瞬間があります。
「何度言っても、スタッフが動いてくれない」
「技術を教えても、現場で活かされない」
「結局、自分がやった方が早い」
そんなふうに感じたことはありませんか?
けれど、そこで「人材の質が悪い」「最近の若者は…」と片づけてしまうと、組織の成長は止まってしまいます。
本当に変えるべきは、「スタッフ」ではなく、院長自身の在り方かもしれません。
今、多くの整骨院が直面しているのは、リーダーの孤独と限界です。
どれだけ技術に優れていても、チームが動かなければ院は回りません。
逆に、技術に自信がなくても、信頼される院長には人が集まり、育ち、定着していきます。
このページでは、整骨院の院長にとって本当に必要な「3つの力」技術力・教育力・在り方力について整理しながら、それぞれを高めるための具体的な視点や事例をご紹介します。
「怒らずに伝えるにはどうしたらいいのか」
「技術が伝わらないのはなぜか」
「リーダーとして自分をどう整えればいいのか」
そんな悩みを持つすべての院長に向けて、施術と同じように、関わり方も構造的に学ぶためのヒントをお届けします。
現場で使える実践知と、平井塾で実際に成果を出している整骨院の事例を交えながら、あなたの院を育つチームに変えるための一歩を、共に踏み出しましょう。
整骨院の院長に求められる「3つの力」とは?

整骨院という現場は、施術者としての「技術」だけでなく、経営者としての「判断」、そして教育者としての「関わり方」が問われる、非常に複雑なポジションです。
院長として成果を出し、チームを育て、院を安定的に運営するためには、以下の3つの力が不可欠です。
① 技術力:まずは自分が信頼される施術家であること
どれだけ教育やマネジメントを学んでも、院長自身の技術に説得力がなければ、スタッフの尊敬や信頼は得られません。
- 技術の再現性はあるか
- 患者さんの支持が得られているか
- スタッフが「真似したい」と思える臨床か
これは、施術技術のレベルというよりも、「基本に忠実で、再現性が高く、丁寧な仕事をしているか」という仕事への姿勢が評価される部分です。
特に平井塾で教えるFJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)は、「構造を見る力」を育てる基礎技術として、多くの院長から信頼されています。
▶ 関連記事:スタッフに伝わる技術指導とは?FJAに学ぶ構造的アプローチ
② 教育力:スタッフが育つ伝え方を持っているか
技術がどれだけ優れていても、それを「どう伝えるか」「どう育てるか」の視点が欠けていると、スタッフはなかなか定着しません。
- 一方的な指導になっていないか
- 相手の理解度に合わせた説明ができているか
- 感情的な指導になっていないか
ここで重要になるのが、非暴力的コミュニケーション(NVC)の視点です。
「怒らずに、でも甘やかさずに、しっかり伝える」。
そんな技術が、整骨院マネジメントにこそ必要なのです。
▶ 関連記事:怒らずに伝える技術|整骨院マネジメントに効く“非暴力的コミュニケーション”とは?
③ 在り方力:空気を作り、信頼を育むリーダーシップ
最終的に、スタッフが「この人のもとで働きたい」と思うかどうかは、
技術やノウハウ以上に、院長の在り方にかかっています。
- 感情をぶつけていないか
- 自分自身を整えているか
- チームの空気を観察し、育てているか
この“在り方”は、目に見えませんが、組織全体の空気感を左右する最も大きな要素です。
リーダーシップとは、「引っ張る力」ではなく、「育てる空気をつくる力」。
▶ 関連記事:整骨院の院長に求められる“リーダーシップ”の条件とは?
なぜ今、在り方が問われるのか?
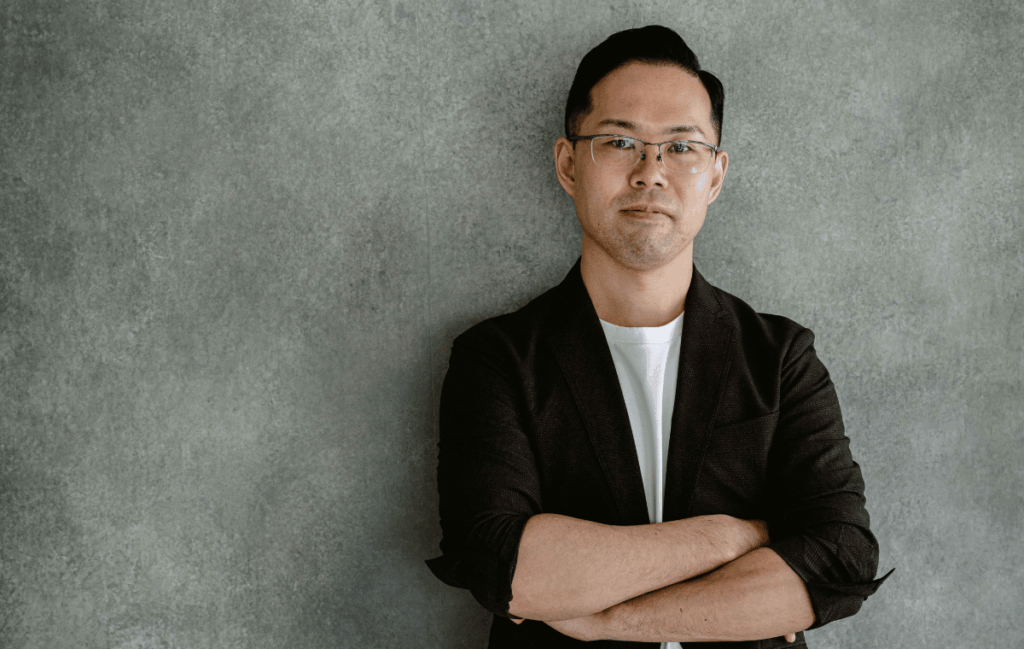
かつての整骨院経営では、「技術力」や「スピード」が何より重視されていました。
しかし今、スタッフの世代が変わり、患者さんの価値観も変化していく中で、
院長に求められる力もスキルから在り方へと移行しています。
伝え方・教え方の悩みは、ほとんどが在り方のズレから
「伝えたつもりなのに、伝わっていない」
「何度言ってもスタッフが動かない」
「指導するとき、感情が先に出てしまう」
こうした現場の悩みの多くは、実は「教え方の技術」ではなく、在り方のズレに原因があるケースが非常に多いのです。
- 相手の成長を心から願っているか?
- 感情的に相手をコントロールしようとしていないか?
- まず観察し、受け入れる姿勢があるか?
技術や方法論の前に、自分の内面=在り方が整っているかどうかが、伝わるか、響くか、スタッフが育つかの分かれ目になります。
スタッフが動かないのは、技術ではなく空気の問題
技術的なミスや行動の遅さの背景には、「この職場で安心して行動できるか?」という心理的安全性が関係しています。
院長がイライラしていたり、感情をぶつけていたりすると、スタッフはミスを恐れて受け身になり、失敗を隠すようになります。
逆に、「あなたの成長を信じているよ」という安心と信頼の空気があれば、スタッフは自然とチャレンジし、自ら学ぶようになるのです。
この「空気」をつくるのが、まさに院長の在り方なのです。
怒らないだけではダメ、本質は「どう関わるか」
最近では「怒らずに伝えましょう」といった指導が主流になりつつあります。
しかし、「怒らなければいい」という表面的な対応では、逆にスタッフに何も響かず、関係性が深まらないまま終わってしまいます。
大切なのは、「どう関わるか」=関係性の質を高める姿勢です。
- 相手の状況を観察し、的確にフィードバックする
- 指導前に共感し、信頼の土台を築く
- 自分の感情に気づき、態度に出さない力を磨く
在り方とは、「どう見られるか」ではなく、「どう関わるか」「どう伝わるか」を意図的に整える力なのです。
院長の在り方マネジメントを構造で理解する

「在り方」と言うと、精神論や抽象的な言葉に聞こえるかもしれません。
しかし、平井塾では在り方を構造的に捉えることで、再現性と実践性を両立させています。
ここでは、「感情」「信頼」「仕組み」を軸に、院長としての在り方を構造化してみましょう。
「信頼・感情・構造」の三層モデルとは?
スタッフと関わるとき、院長の言動は次の三層で影響を与えています。
- 感情層:今この瞬間、何を感じているか(例:イライラ、不安、焦り)
- 信頼層:スタッフとの関係性の深さ(例:安心して質問できる空気)
- 構造層:伝え方や仕組みが整理されているか(例:指導ステップ、評価軸)
この三層がズレていると、たとえ良い言葉を使っていても「伝わらない」「響かない」「育たない」といった問題が起きます。
逆に、構造を整え、信頼を育み、感情を整えることで、同じ言葉でも伝わり方が変わるという変化が現場で起きるのです。
感情をコントロールするのではなく、構造に変換する
イライラしてはいけない、怒ってはいけない。
そう考える院長ほど、感情を「抑える」ことに必死になり、結果的にストレスを溜めてしまいます。
重要なのは、感情を否定するのではなく、構造的に扱うことです。
たとえば、
- 「なぜイラっとしたのか?」→ 期待とのズレを言語化する
- 「どこが引っかかっているのか?」→ 伝え方の構造を見直す
- 「どうして伝わらないのか?」→ 相手の受け取り方を観察する
このように、感情を構造に変換できるようになると、指導やコミュニケーションの質は劇的に改善します。
FJAに通じる“ズレ”と調整の視点をマネジメントにも活かす
FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)は、構造のズレを観察し、最小限の調整で最大の変化を引き出す技術です。
この「ズレを見抜き、最適に整える」という視点は、人との関係や指導にもそのまま応用可能です。
- スタッフの理解度のズレ
- モチベーションの低下という微細な変化
- チーム全体の空気のズレ
こうした臨床では見逃さないズレを、マネジメントでも観察し、調整する。
それができるようになると、院の空気も自然と整っていきます。
怒らずに伝える技術とは?

スタッフに対してイライラしてしまう。
つい言葉が強くなり、後悔する。
そんな経験を持つ院長は多いのではないでしょうか。
しかし、怒りや感情をぶつけても、人は育ちません。
そこで重要になるのが、「非暴力的コミュニケーション(NVC)」という視点です。
怒りをぶつけるのではなく、背景を観察する
NVCでは、相手の行動に対する評価や否定の前に、「何が起きているのか?」「その人に何が足りていないのか?」を観察することから始めます。
たとえば、同じミスが続いている場合でも、
- 怒る前に、相手が理解できているか?
- どう伝わっているか?
- 感情的に追い詰められていないか?
こうした構造の観察が、怒りをぶつけずに育てる第一歩です。
甘やかすのではなく、信頼して伝える
「怒らない=優しくする」ではありません。
NVCは、信頼を前提に、正直に伝える技術です。
- その行動は何が問題なのか
- なぜ改善してほしいのか
- それをどう変えていけばいいのか
これらを冷静に、かつ信頼関係の上で伝える姿勢が、結果として育つ関係をつくります。
怒りを感じた瞬間にできるルーティンを持つ
感情は自然に湧き上がるものです。
だからこそ、「出さない」ことより、「向き合い方」を持つことが重要です。
- 呼吸を深める
- 感情を言葉にしてみる
- 一呼吸おいて、目的を再確認する
このような整えるルーティンを持つことで、感情ではなく意図で動けるリーダーシップが育っていきます。
▶ 詳しくはこちら
怒らずに伝える技術|整骨院マネジメントに効く“非暴力的コミュニケーション”とは?
伝わる技術指導の構造とは?

「技術は教えているのに、なぜかスタッフができるようにならない」
「真似してと言っても、動きが違う」
「何度も言っているのに変わらない」
これは多くの整骨院で起きている課題ですが、原因は教え方の量ではなく、教え方の構造にあります。
技術指導に必要なのは「見せる」より「分解する」
FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)では、臨床を「構造のズレを見抜き、最小限で調整する」ことが目的です。
これは技術指導でも同じ。
ただやって見せるのではなく、
- どのタイミングで
- どこに意識を置いて
- 何のためにその動作をするのか
を構造的に分解して教えることが必要です。
相手の理解スタイルに合わせて調整する
伝わらない原因の多くは、理解のズレです。
FJAの臨床と同じように、相手の受け取り方・学び方に応じて指導内容を調整する視点が欠かせません。
- 視覚的に伝える(動画・写真)
- 体感で覚えさせる(触ってもらう)
- 言語化して理解を深める(解剖・理論とつなげる)
つまり、指導者が柔軟にアプローチを変えられるかがカギになるのです。
FJAの考え方は、教育にもそのまま活きる
FJAで最も重要なのは、観察と対話によって、ズレを微調整する力です。
技術習得でも人材育成でも、必要なのは完璧に伝えることではなく、
- どこがズレているかを観察し
- どう調整すれば改善するかを対話で導く
というプロセスを繰り返すこと。
技術者としての視点と、指導者としての視点が構造思考でつながるとき、本当に「伝わる」技術指導が実現します。
▶ 詳しくはこちら
スタッフに“伝わる”技術指導とは?FJAに学ぶ構造的アプローチ
リーダーシップは在り方で決まる

多くの整骨院の院長が「リーダーシップ」に悩みます。
しかし、その正体はカリスマ性や統率力ではなく、日々の在り方と関わり方の積み重ねに他なりません。
「引っ張る」より「育てる」ことがリーダーの本質
リーダーと聞くと、前に立ってグイグイ引っ張るイメージを持つかもしれません。
ですが、整骨院のような現場型の組織においては、
- スタッフが安心して動ける空気をつくる
- 小さな成長に気づき、信頼で関わる
- 感情ではなく構造でフィードバックする
という育てる力こそが、リーダーに求められる真の条件です。
整骨院リーダーの5条件|観察・ビジョン・習慣・感情・関係
平井塾では、以下の5つをリーダーの在り方の構造として整理しています。
- 観察力:スタッフの状態・空気・変化に気づけているか
- ビジョン提示力:どこに向かっているのかを言葉にしているか
- 習慣形成力:成長の土台となるルーティンを作れているか
- 感情の扱い力:自分の感情を整え、反応で動いていないか
- 関係構築力:スタッフに「この人と働きたい」と思わせられるか
この5つは、どれも先天的な才能ではなく、後天的に磨けるスキルです。
在り方の変化が、現場を大きく変える
実際に、平井塾を導入した整骨院では、
- 指導が感情的だった院長が、スタッフから信頼される存在に
- 自分だけで抱えていた仕事を、自然と任せられるように
- スタッフが自主的に成長する文化が根づいた
といった変化が数多く報告されています。
技術や制度を変えたわけではありません。
変わったのは、院長の在り方だけだったのです。
▶ 詳しくはこちら
整骨院の院長に求められる“リーダーシップ”の条件とは?
現場事例|在り方が整った院はこう変わる

ここでは、実際に在り方を見直すことで現場が大きく変わった整骨院の事例を紹介します。
どの院も、特別なスキルや施策を導入したわけではありません。
ただ、「院長自身の関わり方」が変わったことで、スタッフとの関係性、院の空気、業績までもが好転したのです。
叱ってばかりだった院長が信頼される存在へ
ある30代男性の院長は、スタッフへの技術指導がうまくいかず、毎日のように怒ってばかり。
離職が続き、院内は常に緊張感に包まれていました。
しかし、平井塾で「怒りの背景にある期待と不安」を見つめ直す機会を得てから、指導の前に共感と観察の習慣を持つように。
その結果、スタッフのミスが減っただけでなく、「先生のもとで長く働きたい」という声が自然と生まれるようになりました。
伝え方を変えたら、スタッフの離職率がゼロに
別の院では、入職3ヶ月以内の離職率が高く、常に人手不足。
教える内容は変えていないのに、なぜ伝わらないのか悩んでいました。
そこで、FJAの構造的視点を取り入れ、伝えたつもりではなく相手が受け取れる形で分解・視覚化して伝えるように変更。
結果、同じ内容でも「分かりやすい」「安心して聞ける」と感じるスタッフが増え、新入社員の定着率が100%に改善されました。
共に学ぶ文化が院に根づいたケース
ある院では、院長が「自分が一番正しい」という態度を無意識に取り続けていたことで、スタッフが萎縮し、何も相談できない状態が続いていました。
平井塾の講座で「院長もまた学び続ける存在である」ことの重要性に気づき、日々の朝礼で「昨日の気づき」「自分の反省」をオープンに共有するようになったところ、スタッフからも自然と「学び」「振り返り」の声が出るように。
今では、院全体が一緒に育つ場へと進化しています。
このように、在り方を見直すことは、単に院長の成長に留まらず、組織文化そのものを変える力があるのです。
まとめ|院長力とは「技術×在り方」の総合力である

整骨院経営において、院長の役割はますます複雑かつ重要になっています。
「施術家として高い技術力を持つ」ことは当然の基盤であり、そのうえで、スタッフを育て、チームを導く教育者・リーダーとしての力が不可欠です。
そしてそれらを統合するのが、院長の在り方です。
すべては自分から整えるところから始まる
スタッフや院の雰囲気に問題があると感じたとき、まず見直すべきは、自分の態度・感情・伝え方です。
「怒らずに伝える」
「相手の理解スタイルを観察する」
「信頼を積み重ねる言葉と行動を選ぶ」
こうした積み重ねが、院の空気を変え、チームの関係性を深めていきます。
リーダーシップは後天的に育つ技術である
「自分には向いていない」「人をまとめるのは苦手だ」
そう思っている院長も多いかもしれません。
しかし、リーダーシップは後天的に学べる構造と習慣の技術です。
技術と同じように、
「観察」「実践」「改善」を繰り返すことで、
誰でも育て導ける人へと変わることができます。
あなたの在り方が、チームと院の未来を創る
整骨院は、技術だけで成り立つ現場ではありません。
そこに集うスタッフ・患者さん・地域の人々と、信頼でつながる空間をつくるのが、院長の本当の仕事です。
その鍵を握っているのが、あなたの在り方です。
「指導が伝わらない」
「スタッフが思うように育たない」
「組織に一体感がない」
そんな悩みを感じたときこそ、自分自身の整え方を学ぶ好機です。
平井塾のご案内|技術と在り方を同時に学ぶなら

「スタッフに伝わらない」
「感情でぶつかってしまう」
「リーダーとしての振る舞いに自信が持てない」
こうした悩みは、整骨院の院長であれば誰しも一度は経験するものです。
そして、そこから抜け出すには、技術だけでなく在り方そのものを整える学びが必要です。
平井塾では、
FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)と姿勢循環整体という実践的な技術を通して、自分を整え、人を育てるための構造的思考を身につけることができます。
FJA・姿勢循環整体が教える構造思考とは?
- FJA:細部の「構造エラー」にアプローチする技術
- 姿勢循環整体:全体のユニットを整えるルーティン型手技
これらは単なる技術ではなく、「どこを見るか」「どう変化を起こすか」という臨床思考の軸を育てる講座です。
この構造を見る力は、施術だけでなく、スタッフ指導やマネジメントにもそのまま応用できます。
リーダーとして育つ院長たちの変化
実際に導入した整骨院では、
- 「怒ってばかりだった指導が、信頼の対話に変わった」
- 「技術と関わり方の両面から、チームの空気が変わった」
- 「スタッフが自主的に学び、成長する文化が生まれた」
といった声が多数寄せられています。
院長自身が変わることで、院全体が自然と育ち始める。
これが、平井塾の在り方教育の根幹です。
▶ セミナー・体験会情報はこちら
投稿者情報【平井 大樹】

株式会社美絆 代表取締役。みゅう整骨院 代表。整体教育機関ゴッドハンドへの道「平井塾」代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。
「治療家を職業から誇りへ」を信念に、紹介だけで予約が埋まる「本物の治療家」を育てる平井塾を主宰。施術歴20年、延べ10万人以上を施術し、リピート率98.5%、新規予約は5年待ちという圧倒的な実績を持つ。
【平井塾が生まれた理由】
高校卒業後、スポーツトレーナーの世界で「本当に人の役に立ちたい」という強い想いを胸に治療家の道へ。雇われ院長時代には、1日来院数255名という日本一の実績を達成。しかし、数字を追い求める中で、本当にやりたかったこととのギャップに悩み、独立後は広告を一切使わない「紹介のみ」の治療院を確立しました。
その経験から、「技術だけでなく、患者さんの心に寄り添う在り方こそが、真のゴッドハンドへの道である」と確信。2020年から始めたセミナー事業も、広告を一切使わず、口コミだけで年間91回開催、延べ770名もの治療家が集まる場所となりました。
【平井大樹の圧倒的な実績】
私が提唱する「在り方で信頼され、結果で指名される」という哲学は、以下の圧倒的な実績によって証明できる確信しています。
- 長期継続患者数:私が施術している毎月211人の患者様のうち、5年以上継続が211名,そのうち10年以上が93名。これは、一般的な治療院が測る「初回リピート率」をはるかに超える、揺るぎない信頼の証です。当社独自の2年継続率では49.7%という圧倒的な実績を数字で証明しています。
- 独自のメソッド:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)や姿勢循環整体など、単なる技術ではなく、痛みの根本原因を「動きの連鎖」から見抜く独自の臨床思考モデルを確立しています。
- 全国規模の実績:東京、大阪、横浜、宮崎など全国9社の整骨院グループで社員研修を担当。組織の課題に客観的に向き合い、治療家として誇りを持って働ける社員を育成しています。
- 安定した組織運営:私が経営する院のスタッフ定着率は平均7年以上。これは、理念と実践が一致したマネジメントの証明です。
「在り方で信頼され、結果で指名される」
平井塾は、技術と人間性の両輪を磨き、治療家として誇りを持って生きる仲間を増やすことを目標としています。このブログが、あなたの治療家人生を変える一歩となれば幸いです。

