「腰が痛い」と感じたとき、多くの方がまず「腰痛かな?」と思うのではないでしょうか。
しかし実は、その痛みの正体が坐骨神経痛によるものであることも少なくありません。
腰痛と坐骨神経痛は、どちらも腰まわりに痛みを感じるという共通点がありますが、
原因・症状・対処法はまったく異なります。
「同じ腰の痛みなのに、なぜ違うの?」
「どんなときに病院へ行くべき?」
「整体で改善できるの?」
このような疑問を持つ方に向けて、この記事では腰痛と坐骨神経痛の本当の違いを、専門的でありながらやさしく解説します。
目次
なぜ「違いの理解」が大切なのか
平井塾の臨床現場でも、「腰が痛い=腰痛」と自己判断していた方が、実は坐骨神経痛だったというケースが多くあります。
坐骨神経痛は、腰から足へと伸びる坐骨神経が圧迫・炎症を起こすことで生じる痛みです。
腰だけでなく、お尻・太もも・ふくらはぎ・足先まで痛みやしびれが広がるのが特徴。
一方で、一般的な腰痛は、筋肉や関節などの局所的な負担によって起こるケースがほとんどです。
つまり、痛みの場所は似ていても、原因の構造が違うのです。
違いを正しく理解していないと、
・腰を揉んでも改善しない
・神経の炎症を見逃す
・誤った姿勢やストレッチで悪化する
といったリスクにつながることもあります。
医療と整体の間を埋める構造思考
平井塾では、痛みを「症状」ではなく「構造の乱れ」として捉えます。
腰痛も坐骨神経痛も、実は体のどこかで動きの連動が崩れているサインです。
たとえば、
- 骨盤がわずかに傾くことで坐骨神経が圧迫される
- 背骨の動きが硬くなって腰部の筋膜が緊張する
- デスクワークの座り方が原因で骨盤が後傾する
こうした構造的エラーを、FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)で丁寧に読み取り、姿勢循環整体で全身の流れ(循環)を取り戻す。それが、平井塾が考える「再発しない身体づくり」です。
医療の安全性を踏まえながら、整体でできるサポートを明確にし、「痛みを怖がるのではなく、身体の声を聴く」ための知識をお伝えしていきます。
「腰痛なのか、坐骨神経痛なのか分からない」
そんな不安を抱えている方が、自分の身体を理解し、安心して改善に向かえる。
この記事が、その第一歩になれば幸いです。
腰痛と坐骨神経痛の基本知識

「腰が痛い」と感じたとき、それが腰痛なのか坐骨神経痛なのかを正確に見分けることは、実はとても難しいことです。
なぜなら、どちらの痛みも「腰から下に痛みが出る」という点では似ているからです。
しかし、その「原因構造」と「痛みの出方」はまったく異なります。
ここでは、まずは両者の違いを理解するために、身体の仕組みをやさしく整理していきましょう。
腰痛とはどんな痛みか?
一般的に“腰痛”とは、腰部に痛みや重だるさを感じる状態全般を指します。
原因の多くは、筋肉や関節、靭帯などの軟部組織の緊張・疲労・炎症です。
具体的には
- 長時間同じ姿勢を取る(デスクワークなど)
- 重い物を持ち上げる
- 睡眠不足や冷えによる筋肉のこわばり
- 骨盤や背骨の歪みによる姿勢の乱れ
といった日常的な負担によって、腰のまわりに微小なストレスが蓄積することで起こります。
痛みの特徴は、
・腰の中央または片側に「鈍い痛み」
・動くと痛みが強くなり、休むと軽くなる
・しびれはあまり出ない
という点です。
平井塾では、こうした腰痛を「構造的エラー(身体のバランス崩壊)」のサインと捉え、痛みの出ている筋肉だけでなく、その緊張を生んでいる姿勢・動きの連鎖まで観察します。
坐骨神経痛とは何か?
坐骨神経痛は、腰から足に伸びる坐骨神経が圧迫または刺激されることで生じる神経痛です。
坐骨神経は人体で最も太く長い神経で、腰椎の下部からお尻・太もも・ふくらはぎ・足先へと枝分かれして伸びています。
この神経が何らかの原因で圧迫されると、
- お尻から太もも、ふくらはぎにかけての鋭い痛みやしびれ
- 腰を反らしたり、長く座ったときに悪化する
- 足に力が入りづらくなる
といった症状が現れます。
つまり、坐骨神経痛は「腰の筋肉」ではなく「神経の通り道」に問題がある痛み」です。
単なる腰痛とは異なり、神経レベルでの炎症や圧迫が関与するため、放置すると長引きやすいのが特徴です。
腰痛と坐骨神経痛の違い
| 比較項目 | 腰痛 | 坐骨神経痛 |
|---|---|---|
| 主な原因 | 筋肉・関節・靭帯の負担 | 坐骨神経の圧迫・炎症 |
| 痛みの範囲 | 腰の局所(中央〜片側) | 腰〜お尻〜脚へ広がる |
| 痛みの性質 | 鈍痛・重だるさ | ピリピリ・ズキッとした神経痛 |
| しびれ | ほとんどなし | あり(足の指まで) |
| 悪化する動作 | 長時間座る・前かがみ | 前屈・くしゃみ・長時間座位 |
| 原因の構造的特徴 | 筋膜・姿勢のアンバランス | 神経ルートの圧迫(椎間板・仙骨など) |
このように、痛みの「出る場所」ではなく、「どの構造に原因があるか」が違いの本質です。
坐骨神経痛を引き起こす身体のメカニズム
坐骨神経は、背骨(腰椎)から出て骨盤の中を通り、お尻や脚へと伸びる神経です。
その通り道のどこかで圧迫やねじれが生じると、神経が過敏になり痛みやしびれを感じます。
主な要因は以下の通りです:
- 腰椎椎間板ヘルニア
→ 椎間板の一部が飛び出して神経を圧迫。若年層に多い。 - 脊柱管狭窄症
→ 加齢で背骨の管(脊柱管)が狭くなり、神経が圧迫される。中高年に多い。 - 梨状筋症候群
→ お尻の筋肉(梨状筋)が緊張して坐骨神経を締め付ける。長時間座る人に多い。 - 骨盤の歪み・姿勢不良
→ 仙骨の傾きや筋膜のねじれが神経ルートを圧迫。デスクワーカーに多発。
平井塾の構造思考では、これらを単なる「神経圧迫」とは見ず、
なぜそこに圧がかかったのかという構造的な因果関係を読み解いていきます。
痛みの種類とその特徴
痛みには大きく分けて3種類あります
| 痛みのタイプ | 原因構造 | 感じ方の特徴 |
|---|---|---|
| 筋性の痛み | 筋肉・筋膜の緊張 | 重だるい、張るような痛み |
| 関節性の痛み | 腰椎・仙腸関節の不均衡 | 動かした時に痛い、体勢で変化する |
| 神経性の痛み | 坐骨神経・神経根の圧迫 | ピリピリ、ビリビリ、脚まで響く痛み |
腰痛は主に筋性・関節性の痛みが中心ですが、坐骨神経痛は神経性の痛みが主役です。
この違いを正しく見極めることが、治療や整体を選ぶ上でとても大切になります。
平井塾では、「痛みの種類を見分けること」=「構造を読み解くこと」と考えています。
FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)では、筋膜・関節・神経の連動を手で聴き取り、姿勢循環整体で全身の流れを整えることで、痛みをつくらない構造へ導くのです。
腰痛と坐骨神経痛の原因
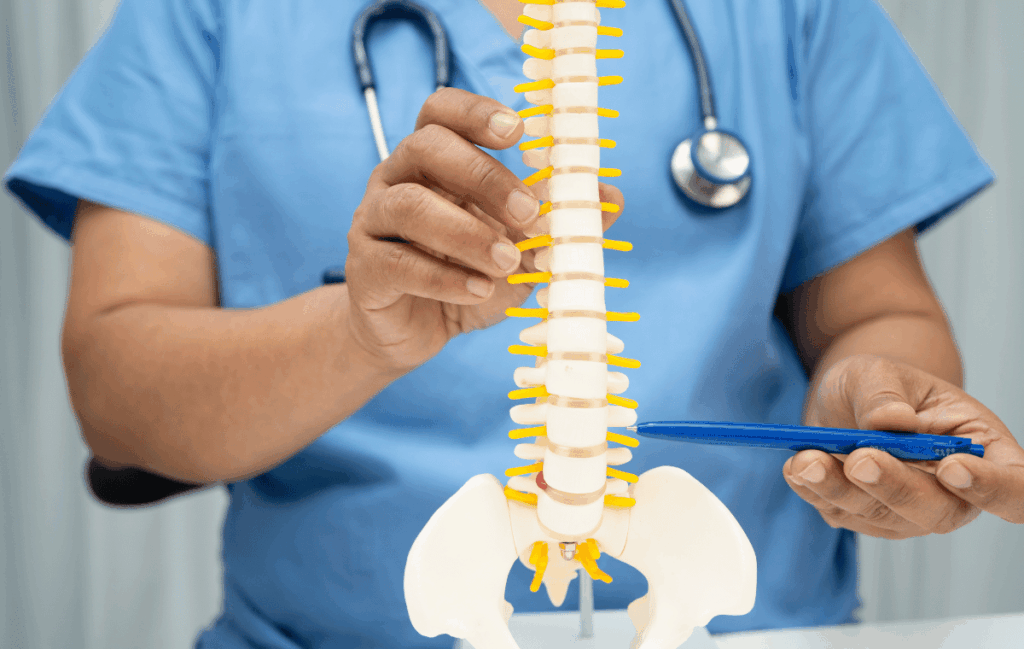
腰痛と坐骨神経痛は、どちらも「腰から下」に痛みを感じる点では共通しています。
しかし、その発生メカニズム(原因構造)はまったく異なります。
腰痛は主に筋肉や関節の機能的なアンバランス、坐骨神経痛は神経の通り道の圧迫や炎症によって生じます。
ここでは、それぞれの代表的な原因と、生活習慣との関係を詳しく見ていきましょう。
主な原因:腰椎椎間板ヘルニア
腰椎椎間板ヘルニアは、腰の骨と骨の間にある「椎間板」が後方に飛び出し、神経を圧迫する病態です。20〜40代の男性に多く、重い荷物を持ち上げた時や、前かがみ姿勢を繰り返すことで発症することがあります。
症状の特徴
- 腰からお尻、脚にかけてのしびれ・痛み
- 片側の脚に強い放散痛が出る
- 咳やくしゃみ、前屈で痛みが悪化
このような症状がある場合、整形外科でMRIなどの画像診断が必要です。
ただし、平井塾の臨床経験では、「ヘルニアの画像所見がある=痛みの原因とは限らない」ケースも多く見られます。
痛みは単に圧迫ではなく、筋膜や関節の滑走制限(構造エラー)によって神経が敏感化していることもあるのです。
そのため、FJAでは「圧迫されている場所」だけでなく、圧迫を生んだ身体全体の連動不良に着目します。
仙腸関節の問題による痛み
仙腸関節は、骨盤の中央にある仙骨と腸骨をつなぐ関節です。
一見動かないように見えますが、実は呼吸や歩行に合わせて数ミリ単位で動いています。
この仙腸関節の動きが硬くなると、
- 腰の奥の鈍痛
- お尻の片側の違和感
- 座ると痛くなる
といった症状が現れます。
この痛みは、坐骨神経痛と間違えやすい代表例でもあります。
MRIでも異常が見つからないため、「原因不明の腰痛」として放置されやすいのです。
FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)では、この仙腸関節の動きを手で聴くことができます。
関節面の微妙な引っかかりや滑走の制限を見つけ、本来の遊びを取り戻すことで、神経・筋膜・骨格の連動が改善していきます。
その他の原因:脊柱管狭窄症や筋肉の緊張
中高年に多いのが、脊柱管狭窄症です。
これは、背骨の中を通る「脊柱管」という神経の通り道が、加齢や変形によって狭くなることで発生します。
特徴的な症状
- 歩くと脚がしびれて止まる(間欠性跛行)
- 前かがみで楽になる
- 腰を反らすと悪化する
一方、若年〜中年層に多いのが、筋肉性の坐骨神経痛(梨状筋症候群)です。
お尻の奥にある梨状筋が硬くなることで坐骨神経を圧迫し、長時間座ることで痛みが強くなります。
これらの症状は、「神経圧迫」が直接の原因ですが、実際には姿勢・骨盤角度・筋膜の滑走不良などの構造的背景が必ず関わっています。
平井塾の構造思考では、「神経が圧迫されたから痛い」ではなく、「なぜその神経ルートに負担が集中したのか」を読み解くことが根本改善の鍵。
坐骨神経痛と間違えやすい病気
坐骨神経痛と似た症状を示す病気はいくつかあります。
| 疾患名 | 主な症状 | 見分けのポイント |
|---|---|---|
| 股関節症 | 股関節の痛み、脚の可動域制限 | 足の付け根が痛く、あぐらが難しい |
| 梨状筋症候群 | お尻の深い痛み | 座ると悪化、立つと楽になる |
| 椎間関節性腰痛 | 腰の片側の鋭い痛み | 反ると痛い、座ると軽くなる |
| 内臓由来の腰痛 | 腎臓・婦人科疾患 | 発熱や血尿などを伴うことがある |
このように、「腰から脚への痛み=坐骨神経痛」とは限りません。
医療機関での診断が必要なケースも多いため、自己判断で放置せず、早めの受診が大切です。
痛みを引き起こす生活習慣
腰痛や坐骨神経痛を繰り返す方の多くに共通しているのが、日常姿勢のクセです。
- 長時間のデスクワークや車の運転
- 足を組む、片足重心で立つ
- ソファでの前かがみ姿勢
- 運動不足や体幹筋の弱化
- 睡眠中の不自然な姿勢
これらはすべて、骨盤と背骨の動きを制限し、筋膜や関節の滑走性を低下させます。
その結果、神経ルートへの圧迫や循環不良が起こり、慢性的な痛みへとつながるのです。
平井塾では、これを「姿勢循環の破綻」と呼びます。
FJAで細部を整えた後、姿勢循環整体で全身の流れを再教育することで、痛みが再発しない身体をつくることができます。
痛みは「結果」であり、「原因」はその奥にある構造の乱れです。
その構造を見抜き、整えることが、平井塾が目指す構造思考の施術です。
症状の見極め方

腰痛と坐骨神経痛は、どちらも腰から下の痛みとして現れますが、痛みの出方・性質・広がり方に明確な違いがあります。
ここを正しく見極めることで、「自分はどちらのタイプなのか」「整体で対応できるのか、病院で検査が必要なのか」の判断ができるようになります。
坐骨神経痛の症状:しびれと放散痛
坐骨神経痛の最大の特徴は、「しびれを伴う痛みが、脚の後ろ側に広がる」ことです。
主な症状の特徴
- 腰・お尻・太もも・ふくらはぎ・足先まで痛みが走る
- 「ピリピリ」「ジンジン」といった電気的なしびれ感
- 座っていると悪化し、立ち上がると少し楽になる
- くしゃみや前かがみ動作で痛みが強くなる
- 痛みの左右差があり、片脚に集中することが多い
これは、坐骨神経が圧迫または炎症を起こしているサインです。
お尻の深部や太ももの裏の「1本のライン上」に痛みが続く場合、筋肉の問題ではなく神経の通り道のトラブルを疑いましょう。
注意:放置はNG
神経の炎症が長引くと、筋力低下や感覚麻痺を引き起こすこともあります。
脚に力が入らない、感覚が鈍い場合は、すぐ整形外科で検査を受けましょう。
腰痛の症状:重だるさから鋭い痛みまで
一方、腰痛は多くの場合、筋肉や関節にかかる負担によって起こります。
主な症状の特徴
- 腰の中央または片側に「重だるい」鈍痛
- 動いたとき・立ち上がるときに痛みが出る
- 同じ姿勢を続けると痛みが増す
- 横になると楽になる
- お尻や脚にしびれは少ない
腰痛の多くは「筋肉性」「関節性」「姿勢性」の痛みであり、神経が原因ではないケースが大半です。
ただし、腰痛が長期間続いたり、再発を繰り返す場合は、背骨や骨盤の構造に慢性的な歪みが生じている可能性があります。
この場合、FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)で硬くなった関節や筋膜の連動を整えることで、根本から改善することが可能です。
自己診断のポイント
「腰痛か、坐骨神経痛か」を見極めるには、以下のセルフチェックが参考になります。
自宅でできるセルフチェック
| チェック項目 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| お尻や脚の裏に痛み・しびれが広がる | ☐ | ☐ |
| くしゃみや前屈で痛みが悪化する | ☐ | ☐ |
| 長時間座るとお尻が痛い・足がしびれる | ☐ | ☐ |
| 痛みが脚の左右どちらか一方に集中している | ☐ | ☐ |
| 腰だけでなく脚までだるい | ☐ | ☐ |
| 横になっても痛みが続く | ☐ | ☐ |
3つ以上「はい」の場合→ 坐骨神経痛の可能性が高い
1〜2個「はい」の場合→ 腰痛(筋肉・関節由来)である可能性が高い
痛みやしびれが両脚に広がる・排尿障害がある場合→ すぐに医療機関へ(脊柱管狭窄症・椎間板ヘルニアなどの可能性)
医師に相談するタイミング
以下のような症状がある場合は、早めに整形外科・神経内科を受診してください。
- 脚のしびれや感覚低下が2週間以上続く
- 足に力が入らない・歩くのが辛い
- 尿や便のコントロールが難しい(膀胱直腸障害)
- 夜間痛が強く眠れない
- 体重減少や発熱を伴う腰痛
これらは、単なる筋肉痛ではなく神経・内臓・感染・腫瘍性疾患が隠れている場合があります。
一方で、画像検査に異常がなくても、身体の使い方や構造の乱れが原因のケースも多く、そのような場合は、構造思考に基づく整体(FJA・姿勢循環整体)でのアプローチが有効です。
平井塾の視点:痛みを「部分」ではなく「構造」で見極める
一般的な診断では、「腰痛」「坐骨神経痛」と名前で分けられますが、平井塾ではその先の「なぜそこに負担が集中したのか」を探ります。
- 腰の筋肉が張るのは、背骨の動きが硬いから?
- 神経が圧迫されるのは、骨盤が傾いているから?
- 骨盤が傾くのは、座り方や呼吸の癖があるから?
こうして、原因の連鎖を一つずつほどいていくのが“構造思考”です。
FJAで動きのエラーを見つけ、姿勢循環整体で全身の流れを整えることで、「腰痛か坐骨神経痛か」ではなく、痛みが出ない身体を取り戻すことが可能になります。
痛みの仕組みを構造で理解する

腰痛や坐骨神経痛を根本から整えるには、「どの神経が圧迫されているか」よりも、なぜそこに圧がかかる構造になっているのかを理解することが大切です。
痛みは、身体が出している「バランスの崩れ」のサイン。
筋肉や骨、神経だけを個別に見るのではなく、全体の構造的つながり(連動)から考えることが、
本当の意味での原因治療につながります。
筋肉や関節だけではない「ファシア(筋膜)」の関係
私たちの身体は、筋肉や骨が単独で動いているわけではありません。
すべてを包み込むファシア(筋膜)という組織が、筋肉・神経・血管・内臓を一枚のシートのように連結しています。
この筋膜が「ねじれる・癒着する・滑らなくなる」ことで、関節の可動域が制限され、筋肉に過剰な緊張が生じます。
その結果、
- 腰では筋肉が張る → 腰痛
- 坐骨神経の周囲で滑走不良 → 神経の圧迫・しびれ
といった痛みの連鎖が起こるのです。
平井塾のFJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)は、この筋膜の動きを聴く技術。
手でわずかな抵抗や流れを感じ取り、どの層が固まっているかを触知して整えます。
「押す」「揉む」ではなく、「聴く」「対話する」それがFJAが目指す観察の手です。
骨盤の歪みと坐骨神経の圧迫関係
坐骨神経は、骨盤の中央にある仙骨の横を通り、お尻から脚へと走る非常に長い神経です。
そのため、骨盤が傾いたり、仙腸関節の動きがロックされると、坐骨神経のルートがねじれた配線のようになり、圧迫や牽引が生じます。
特にデスクワークでは、
- 骨盤の後傾(背もたれにもたれる姿勢)
- 片側荷重(足を組む癖)
- 猫背による背骨の湾曲変化
などが重なり、骨盤が下がるように歪む構造が作られます。
このわずかな角度の乱れが、長期間続くことで坐骨神経痛や慢性腰痛へとつながっていくのです。
筋肉ではなく動きの連鎖を診る構造思考
一般的な施術では、痛みのある部分、つまり「結果」にアプローチします。
しかし、平井塾の構造思考は違います。
痛みを「現象」ではなく「構造の結果」として捉えることで、なぜそこに負担が集中したのかを分析します。
たとえば
- 腰の筋肉が張る → 背骨が硬い
- 背骨が硬い → 骨盤の動きが悪い
- 骨盤が動かない → 股関節や脚に負担が集中
つまり、痛みの起点は腰にあっても、原因はもっと上(胸郭)や下(足首)にあるということも珍しくありません。
FJAはその「連動の切れ目」を探し、姿勢循環整体で全身の流れを回復させることで、痛みの構造そのものを再教育していきます。
痛みは「ズレ」ではなく「連動の乱れ」から起こる
「骨盤がズレている」「背骨が歪んでいる」そう聞くと、骨の位置がずれているように感じますが、実際は骨のズレではなく、動きのリズムが乱れている状態です。
たとえば、歩くとき、本来は「骨盤 → 背骨 → 肩 → 頭」と連鎖的に動くはずが、どこかの関節や筋膜が固まると、その連動が途切れてしまいます。
連動が止まった部分に、負担が集中し、痛みとして現れる。
それが平井塾が考える「構造的痛み」の正体です。
痛みはズレではなく連動のエラー。
それを読み解くのが、平井塾の「構造思考」です。
構造を整えることで「身体の流れ」が戻る
FJAで細部の動きを整えた後は、姿勢循環整体によって全身の流れを整えます。
これは、静脈・リンパ・動脈・神経のすべてに働きかけ、姿勢そのものが循環する身体を取り戻す手技です。
構造が整うことで、
- 呼吸が深くなる
- 姿勢が自然に立ち上がる
- 痛みを繰り返さない身体になる
という「構造からの回復」が起こります。
治療法と改善策

腰痛や坐骨神経痛の改善において大切なのは、「今ある痛みを和らげること」と「再発を防ぐために構造を整えること」の両立です。
多くの方が「どんな治療を受ければいいのか」「整体と病院、どちらに行くべきか」と迷われますが、平井塾では、それぞれの治療法の特徴を理解したうえで、医療+構造ケアの併用が最も効果的であると考えています。
保存療法と運動療法(整形外科での基本治療)
整形外科で行われる治療の多くは、「保存療法」と呼ばれる方法です。
これは手術を行わず、痛みを軽減しながら自然回復を促す治療法です。
主な内容は以下の通りです。
- 安静・姿勢指導:炎症期は無理に動かさず、腰や脚への負担を軽減。
- 温熱療法:血流を促進し、筋肉の緊張を和らげる。
- 理学療法(リハビリ):筋肉の柔軟性を取り戻し、再発を防ぐ。
- コルセット装着:急性期の腰痛や椎間板ヘルニアで使用。
軽度〜中等度の坐骨神経痛であれば、この保存療法と運動指導で改善するケースも多いです。
しかし、「痛みが軽くなった=治った」ではなく、再発を防ぐためには、骨盤・背骨・筋膜の動きそのものを整えることが欠かせません。
薬物療法の選択肢
整形外科では、症状の程度に応じて薬が処方されます。
- NSAIDs(非ステロイド系抗炎症薬):炎症や痛みを抑える。
- 筋弛緩剤:筋肉の過剰な緊張を緩める。
- ビタミンB12製剤:神経の修復を助ける。
- 神経ブロック注射:強い痛みがある場合、一時的に神経の炎症を抑制。
薬は痛みを和らげる助けになりますが、原因を治すものではありません。
症状が落ち着いたら、身体の構造的原因(姿勢・関節・筋膜)を整えていくことが重要です。
専門医による神経ブロック
強い神経痛(坐骨神経痛など)では、神経ブロック注射が有効な場合があります。
これは、痛みの信号を一時的に遮断して炎症を鎮める治療法です。
ブロックを繰り返すことで、神経の過敏状態が落ち着き、その間に身体の構造をリセットするチャンスをつくることができます。
医療の力で「痛みを落ち着かせ」、その間に整体で「構造を整える」。
この連携こそが、最も理想的な治療プロセスです。
手術が必要なケース
以下のような症状がある場合は、手術が検討されます。
- 椎間板ヘルニアで、排尿障害や強い麻痺を伴う
- 脊柱管狭窄症で、歩行が困難
- 保存療法を6ヶ月以上続けても改善しない
現代の手術は低侵襲化が進み、成功率も高いですが、手術後の再発を防ぐためには、姿勢・骨盤・体幹の再教育が不可欠です。
平井塾では、手術後リハビリとして「FJA」「姿勢循環整体」を組み合わせることで、再発防止と回復促進の両方をサポートしています。
整体・整骨院でのアプローチ(構造ケアの重要性)
整形外科で痛みが落ち着いた後も、「慢性的に違和感が残る」「同じ場所が繰り返し痛む」という方は、構造そのものが整っていない状態です。
平井塾の手技では、
- FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)で関節と筋膜の連動を整え、
- 姿勢循環整体で全身の流れを回復させる
という2段階の施術を行います。
この組み合わせにより、
・痛みを作る根の部分(構造エラー)を修正
・体液・神経・呼吸の流れを改善
・自然に治る身体を再教育
することが可能です。
平井塾の理念は「押して治す」ではなく「動きで治す」。
痛みの奥にある構造の乱れを、観察と調整で整えます。
日常生活でできるストレッチとセルフケア
施術だけでなく、日常でのケアも非常に大切です。
以下は、自宅で簡単にできる基本的なストレッチです。
① 骨盤ゆらしストレッチ
椅子に浅く腰掛け、背筋を伸ばして骨盤を前後にゆっくり揺らします。
→ 腰椎と仙骨の動きを取り戻し、神経の圧迫を緩和。
② ハムストリングス(太もも裏)のストレッチ
片脚を前に出し、軽く前屈して太もも裏を伸ばす。
→ 神経の通り道を広げ、坐骨神経痛の軽減に効果的。
③ 呼吸リリース
深呼吸を意識して、息を吸うときに肋骨が広がる感覚を意識。
→ 背骨・横隔膜の動きが改善し、姿勢循環が整う。
④ 30分ごとの「立ち上がり習慣」
長時間座る場合は、30分に一度立ち上がって軽く背伸びをする。
→ 坐骨神経の圧迫を防ぎ、筋膜の滑走を保つ。
医療と整体の上手な使い分け
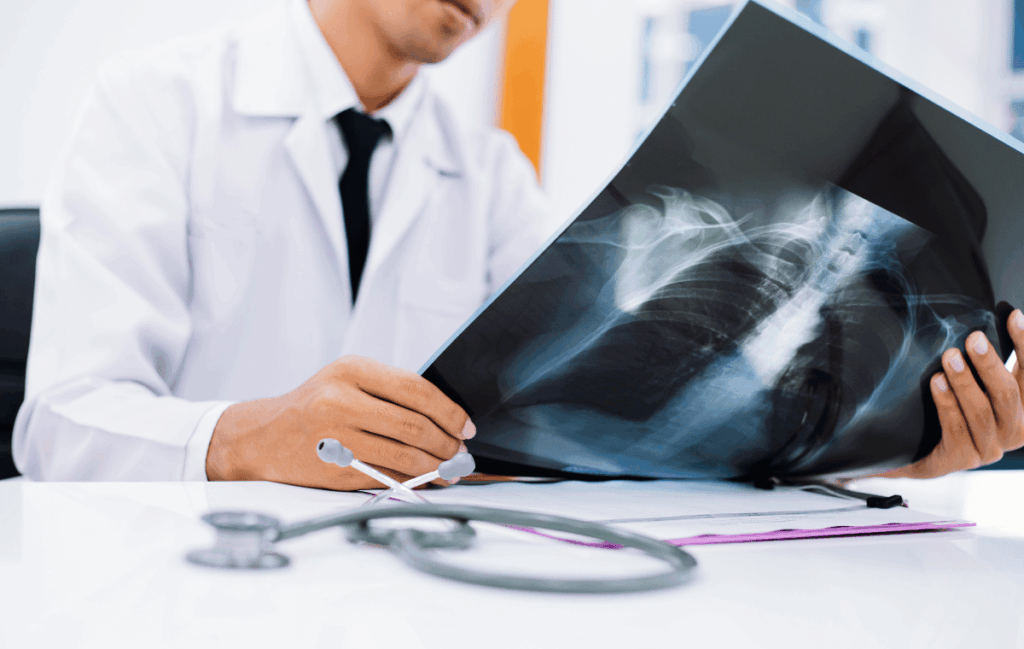
腰痛や坐骨神経痛に悩む多くの方が抱える疑問。
それは、
「この痛み、病院に行くべき? それとも整体でよくなる?」というものです。
どちらが「正しい」ではなく、それぞれに役割があり、補い合う関係にあります。
重要なのは、医療が担う「診断とリスク管理」、整体が担う「構造の再教育と再発予防」この両輪をうまく使い分けることです。
病院で検査を受けるべきタイミング
次のような症状がある場合は、必ず整形外科・神経内科などの医療機関を受診してください。
- 脚のしびれや感覚の鈍さが続く(2週間以上)
- 足に力が入らない、歩行が不安定
- 咳やくしゃみで痛みが強く走る
- 夜間痛が強く眠れない
- 排尿・排便の異常(膀胱直腸障害)
- 発熱・体重減少・食欲低下を伴う腰痛
これらは、椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症・腫瘍・感染など、神経や内臓に関わる重大な疾患が隠れている可能性があります。
まずは医療機関で「危険な痛みではないか」を確認する。
それが、安心して回復に向かう第一歩です。
平井塾が考える「併用」の重要性
最も理想的なのは、医療と整体を並行して活用することです。
たとえば
| フェーズ | 医療機関での対応 | 平井塾の構造アプローチ |
|---|---|---|
| 急性期(痛みが強い時期) | 薬・ブロックで炎症を抑える | 無理に動かさず、FJAで体の緊張をリセット |
| 回復期(痛みが軽減してきた時期) | リハビリ指導 | 姿勢循環整体で体の流れを整える |
| 慢性期(再発防止の段階) | 医療フォロー | 構造思考で“痛みを作らない身体”へ再教育 |
医療と整体を「競合」として捉えるのではなく、治る道の両輪として補完し合う関係にすることが、最短・最善の回復ルートです。
「痛いところだけを治す」から「構造全体を整える」へ
多くの方が「痛い部分=原因」と思いがちですが、平井塾では痛みの原因を「結果としての痛み」ではなく「構造としての不均衡」として見ます。
- 腰が痛い → 骨盤が傾いている
- 骨盤が傾く → 背骨の動きが偏っている
- 背骨が硬い → 呼吸が浅くなる
- 呼吸が浅い → 代謝・循環が滞り、痛みが慢性化
つまり、痛みを治すには「腰だけを施術する」のではなく、身体全体の構造的ハーモニーを回復させる必要があります。
FJAと姿勢循環整体を組み合わせることで、「痛みを取る」ではなく「痛みが出ない構造を育てる」施術が可能になります。
医療が「診断と安全」を担い、平井塾が「構造の回復と再発予防」を支える。
この2つの道が重なるとき、安心して治る未来が見えてきます。
平井塾が考える痛みを根本から整える方法

「腰痛を治したい」「坐骨神経痛を和らげたい」そう願う方の多くが、痛みのある部分に意識を向けがちです。
しかし平井塾では、痛みの出ている場所は「結果」であり、原因は身体の構造にあると考えます。
身体は一つのユニット。骨・筋膜・神経・内臓が絶妙なバランスで支え合っています。
そのどこかが滞ると、「痛み」という形でサインが現れるのです。
ここでは、平井塾が提唱する2つの柱。
FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)と姿勢循環整体を中心に、痛みを構造から整える考え方を紹介します。
FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)による原因特定
FJAとは、平井塾代表・平井先生が20年以上の臨床経験から体系化した、
「関節と筋膜(ファシア)の関係性を観察する手技」です。
多くの治療法が「痛い場所」を直接操作するのに対し、
FJAは「なぜそこに負担がかかったのか」という因果構造を見極めます。
FJAの特徴
- 観察の手
手で押すのではなく、身体の奥にある「抵抗」「沈み」「流れ」を聴き取ります。 - 構造的連鎖の解析
腰の痛みが実は胸郭の硬さや足首の制限から起きているなど、“動きの連動”を評価。 - 微細な調整
大きく動かさず、関節や筋膜の滑走性を1mm単位で整え、自然な可動を回復させます。
目的
- 筋肉・関節・神経の「誤作動」をリセット
- 体の正しい情報伝達を取り戻す
- 「押さない・強くしない」施術で、身体が自ら整う環境を作る
FJAは、「施術」ではなく「対話」。
施術者の手が患者さんの身体の声を“聴く”ための方法です。
姿勢循環整体で回復する身体を取り戻す
FJAで細部の動きを整えたあとは、
身体全体の循環を回復させる姿勢循環整体へと移行します。
これは、
「姿勢」=骨格構造と
「循環」=血液・リンパ・神経・内臓の流れ
を一体として整える平井塾独自の手法です。
姿勢循環整体のポイント
- 循環のループを再構築
骨盤・背骨・胸郭・頭蓋の順に整え、全身の体液・神経の流れを改善。 - 姿勢を作るのではなく戻す
姿勢を矯正するのではなく、身体が自然に正しい位置を思い出すよう導きます。 - リズムと安定の再教育
呼吸・歩行・バランスなど、日常動作の中に「整う姿勢」を定着させる。
姿勢が整うと、循環が生まれ、循環が整うと、自然治癒力が働く。
それが姿勢循環の本質です。
「押さない・戻さない」構造的アプローチ
多くの整体や矯正では、「ズレた骨を戻す」「歪みを直す」という発想が主流です。
しかし平井塾では、それを外から変えるのではなく、内から戻る方向へ導きます。
なぜなら、身体の構造は強い力ではなく、調和とリズムで成り立っているからです。
FJAで細部の歪みを解放し、姿勢循環整体で全体のリズムを整える。
その結果、身体は外部から押されなくても自然と正しい構造へと戻っていきます。
このプロセスを通じて、
- 腰痛や坐骨神経痛を繰り返さない身体に変わる
- 自分の身体を自分で守れる感覚が育つ
- 「治療」から「予防」へと意識が変わる
という持続的な変化が生まれます。
信頼関係が回復力を高める理由
平井塾では、手技だけでなく「信頼関係」も治療の一部だと考えています。
患者さんが安心して身体を預けられる環境こそが、副交感神経を高め、治る力=自己回復力を最大限に引き出すからです。
「この先生なら任せられる」その安心感が、筋肉の緊張をほどき、呼吸を深くし、身体全体の循環を促します。
技術ではなく在り方で治す。それが平井塾の理念です。
平井塾の施術で得られる変化
- 痛みを繰り返さなくなる
- 呼吸が深くなり、姿勢が安定する
- 歩き方が軽くなる
- 身体の動きに「しなやかさ」が戻る
- 精神的にも安心し、ストレスが軽減
痛みが消えることはゴールではなく、「身体が自然に整う状態」こそが真の回復。それが平井塾の構造から整えるという哲学です。
腰痛と坐骨神経痛の予防

腰痛や坐骨神経痛は、一度よくなっても再発しやすいのが特徴です。
しかし、日常生活でのちょっとした意識と構造を整える習慣で、再発は確実に減らすことができます。
平井塾では、
「身体を治すのではなく、治る構造を育てる」
という考えを大切にしています。
ここでは、そのための具体的な予防法を紹介します。
正しい姿勢の重要性と座り方のポイント
腰痛・坐骨神経痛の多くは、「姿勢のくずれ」から始まります。
特にデスクワーク中心の方は、座り方が最大のリスク要因です。
悪い座り方の例
- 背もたれに深くもたれ、骨盤が後ろに倒れる
- 背中を丸め、顎が前に出る(猫背姿勢)
- 片方の足を組む
- 体重が片方の坐骨に偏る
これらはすべて、骨盤の傾き→背骨の湾曲→神経圧迫という連鎖を起こします。
正しい座り方のポイント
- 坐骨で座る(お尻の骨でまっすぐ体重を支える)
- 膝は90度、足裏はしっかり床につける
- 骨盤を立て、背筋を軽く伸ばす
- モニターは目線の高さに
- 30分に一度、立ち上がって背伸びをする
平井塾では、この「30分リセット」を推奨しています。
これは、長時間の座位による坐骨神経への圧迫を防ぎ、循環を保つためのシンプルな習慣です。
適度な運動で筋肉とファシアを活性化
身体は「動くことで整う」構造をしています。
長時間同じ姿勢を続けると、筋肉だけでなく筋膜(ファシア)も硬くなり、動きが鈍くなります。
予防に効果的な運動
- ウォーキング(1日20〜30分)
→ 骨盤の左右運動を促し、坐骨神経の通りを保つ。 - 骨盤スイング運動
→ 骨盤を前後に軽く揺らし、仙腸関節の可動性を維持。 - 呼吸ストレッチ
→ 深く息を吸いながら腕を上げ、肋骨を広げる。背骨と骨盤の連動が改善。
「動く」ことは単なる筋トレではなく、関節と筋膜を滑らかに保つための循環刺激。
これが、平井塾の構造的予防の基本です。
生活環境(椅子・机・寝具)の見直し
環境の「ズレ」が、身体の「ズレ」を生むことがあります。
特に、毎日長時間使う椅子や寝具の選び方はとても重要です。
推奨されるポイント
- 椅子:骨盤を立てやすい硬めの座面、背もたれはやや前傾気味。
- 机の高さ:肘を90度に曲げてキーボードが打てる高さ。
- 寝具:沈みすぎないマットレス(腰が沈むと骨盤が後傾)。
- 枕:頭が沈まず、首の自然なカーブを支える高さ。
小さな環境の改善が、身体の構造バランスを保つ最も効果的な予防になります。
ストレス管理と呼吸・睡眠の質を整える
ストレスや疲労の蓄積も、腰痛や坐骨神経痛を悪化させる大きな要因です。
なぜなら、ストレスは自律神経を乱し、筋肉の過緊張や血流の低下を引き起こすからです。
今日からできるセルフケア
- 呼吸のリズムを意識する
→ 息を「吸う3秒・吐く6秒」で行うと副交感神経が優位になり、筋肉がゆるみます。 - 睡眠前のストレッチ
→ 骨盤まわりや太ももをゆっくり伸ばすことで、睡眠中の回復が促進。 - 湯船に10分浸かる
→ 血流が改善し、神経の炎症が和らぎやすくなる。
呼吸・睡眠・循環を整えることは、
構造的アプローチの基盤でもあり、姿勢循環整体の考え方そのものです。
坐骨神経痛に関するFAQ(よくある質問)

腰痛や坐骨神経痛について、患者さんからよくいただく質問をまとめました。
どの質問も、現場で多くの方が感じる「不安の声」です。
それぞれに対し、医療的な安全性と平井塾の構造思考の両面から解説します。
Q1:坐骨神経痛は治るのですか?
A:はい、多くの場合は回復可能です。
坐骨神経痛は、神経自体の損傷というよりも、その神経が「圧迫・刺激を受けている状態」が原因です。
したがって、圧迫の要因となっている姿勢・骨盤・筋膜のバランスを整えることで、自然回復が十分に期待できます。
ただし、原因が「神経そのものの変性」や「脊柱管の狭窄」である場合は、医療機関での治療が必要なケースもあります。
平井塾では、FJAで原因構造を見極め、姿勢循環整体で体全体の回復を促すことで、「再発しにくい回復」を目指しています。
Q2:痛みが再発しないための対策はありますか?
A:再発を防ぐ鍵は、動きの質を整えることです。
多くの方が「痛みがなくなったら終了」と考えがちですが、再発の多くは、構造的な歪みが残ったまま日常生活に戻ることで起こります。
予防のポイントは以下の通りです。
- 座る姿勢を見直す(骨盤を立てる)
- 30分に1度は立ち上がり、姿勢をリセット
- 呼吸を深くし、体幹の動きを柔らかく保つ
- 定期的にFJA・姿勢循環整体で構造バランスを確認
身体は使い方で変わります。動きの再教育=再発予防の根本治療です。
Q3:坐骨神経痛はがん(癌)と関係がありますか?
A:基本的には無関係ですが、ごく稀に関連するケースもあります。
がんが骨や神経に転移した場合、似たような「しびれ」や「放散痛」を生じることがあります。
以下のような症状がある場合は、必ず医療機関で検査を受けましょう。
- 体重が急に減った
- 原因不明の発熱や倦怠感がある
- 夜間、安静時でも強い痛みが続く
安全性のために、平井塾では「まずは医療機関での診断を」と常にお伝えしています。
医療的に問題がないことを確認した上で、構造的ケアを行うのが最も安心・確実です。
Q4:痛みを和らげるための生活習慣はありますか?
A:あります。
毎日の習慣を少し変えるだけで、痛みの感じ方は驚くほど変わります。
日常でできる5つのセルフケア
- 呼吸を深くする
→ 浅い呼吸は腰部の筋膜を硬くします。ゆっくり長く吐く習慣を。 - 同じ姿勢を続けない
→ 30分に一度、立って背伸び。坐骨神経の圧迫を防ぎます。 - 冷えを防ぐ
→ 冷えは筋肉・神経の緊張を高めます。腹・腰を温めましょう。 - 足を組まない・片足重心を避ける
→ 骨盤の歪みを防ぎ、左右バランスを保ちます。 - 睡眠前のストレッチ
→ 寝る前にお尻や太ももを軽く伸ばすと、翌朝のこわばりが軽減します。
これらはすべて、「姿勢循環」を保つための小さな積み重ね。
生活習慣そのものが治療につながる。それが平井塾の予防哲学です。
Q5:受診するべき病院やクリニックはどこですか?
A:症状に応じて、以下を目安に選びましょう。
| 状況 | 適した診療科・医療機関 |
|---|---|
| 強い痛み・しびれが出ている | 整形外科・脊椎外科 |
| 脚の麻痺・感覚異常がある | 神経内科 |
| 内臓の不調や発熱を伴う | 総合病院(内科含む) |
| 慢性的な軽い痛みが続く | 整形外科+整体(併用) |
| 手術後のリハビリ・再発防止 | 整骨院・整体院(平井塾推薦院) |
ポイント:
「医療で診断を受けて安心し、整体で構造を整えて回復を育てる」
この2段階アプローチが最も安全で、長期的な改善につながります。
まとめ|違いを知ることが、整える第一歩
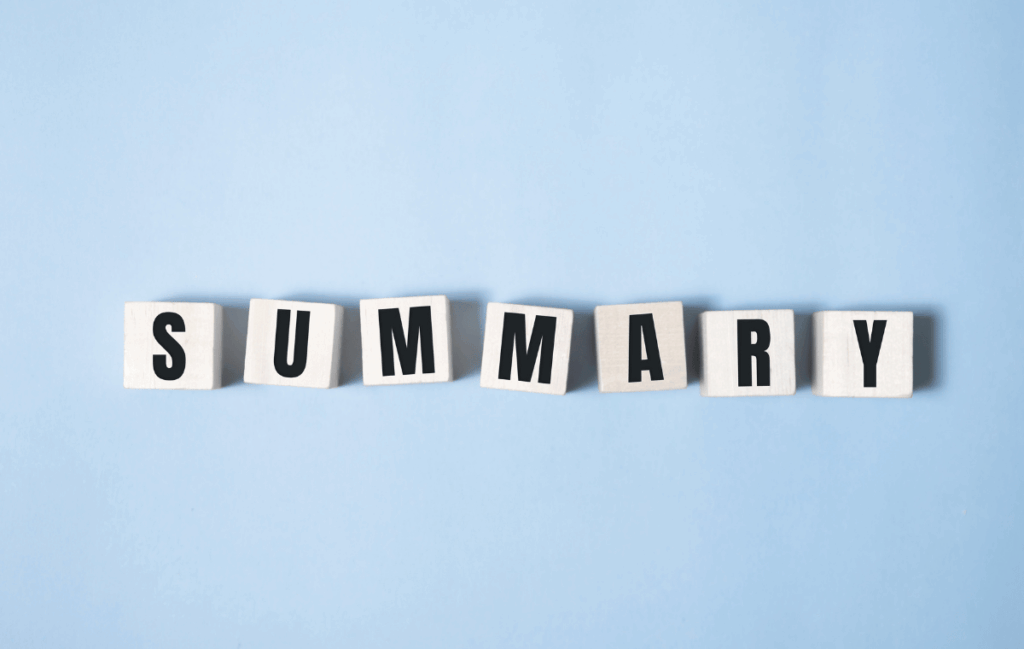
腰痛と坐骨神経痛。同じ「腰の痛み」として語られることが多いこの二つですが、実際には原因も、痛みの質も、対処法もまったく異なるものです。
腰痛と坐骨神経痛は「似て非なる痛み」
腰痛は、主に筋肉や関節などの構造的な緊張や負担が原因。
一方、坐骨神経痛は、神経の通り道にある構造の乱れ(骨盤・椎間板・筋膜)が神経を圧迫し、しびれや放散痛を引き起こすものです。
見た目は似ていても、根本は違います。
だからこそ、「どこが痛いか」ではなく「なぜそこに負担がかかるのか」を理解することが、本当の意味での治療のスタートラインです。
構造を整えれば、痛みは自然に軽くなる
平井塾の考え方はシンプルです。
「痛みを取る」のではなく、
「痛みが出ない構造を育てる」。
FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)で細部のエラーを整え、姿勢循環整体で全身の流れを取り戻すことで、身体は自ら整う力を思い出します。
この「構造思考の治療」は、単に症状を軽くするだけでなく、あなた自身が再発しない身体の使い方を身につける学びの場でもあります。
再発を防ぐ鍵は「姿勢」と「循環」
腰痛・坐骨神経痛を繰り返す方の多くは、痛みの原因ではなく、姿勢の癖や循環の滞りを放置していることが多いです。
- 座りっぱなしの姿勢を見直す
- 骨盤を立てる意識を持つ
- 深い呼吸で体幹をゆるめる
- 定期的に体を動かして循環を促す
これらはすべて、構造が整うための小さな行動です。
日常の中でできるケアこそが、最も確実な予防法なのです。
平井塾推薦の整骨院・整体院で「構造から整える」
もし、
- 「腰痛と坐骨神経痛、どちらか分からない」
- 「病院では異常がないのに痛みが取れない」
- 「何度も再発を繰り返してしまう」
というお悩みをお持ちであれば、平井塾の技術(FJA・姿勢循環整体)を学んだ施術者に相談してください。
平井塾の認定院では、
痛みを追うのではなく、身体の声を聴く施術を行っています。
患者さん一人ひとりの構造に合わせた丁寧な手技で、「安心して治る」ためのパートナーとして寄り添います。
痛みは敵ではなく、身体が「整えてほしい」と語りかけるメッセージです。
その声に耳を傾け、構造から整う身体へと導く、それが、平井塾が目指す「信頼と再生の整体」です。
▼関連する記事もあわせてご覧ください
- 「長時間のデスクワークで坐骨神経痛が悪化する…」そんな方へ。
痛みの原因と正しい座り方を詳しく解説しています。
→ 坐骨神経痛は「座りすぎ」が原因?デスクワーカーが知るべき正しい座り方 - 「午後になると腰が重い」「姿勢が傾く気がする」方は要チェック。
骨盤の歪みとデスクワーク姿勢の関係を詳しく解説しています。
→ 骨盤の歪みはなぜ起こる?デスクワークで崩れた姿勢を整える方法 - 姿勢と血流は切っても切れない関係。
猫背・反り腰・肩こり・冷えなど、全身の“循環不良”のメカニズムを解説します。
→ 姿勢が崩れると血流も悪くなる?不調と姿勢の関係とメカニズム - 「座りすぎ」は腰だけでなく、全身に影響を与えます。
腰痛・肩こり・むくみを引き起こす共通の“循環の乱れ”を詳しく解説。
→ 座りすぎがもたらす全身の不調:腰痛・肩こり・むくみの共通原因とは? - 「午前は平気なのに午後になると腰が痛い…」
そんな“午後腰痛”の原因と、流れる姿勢をつくる方法を紹介しています。
→ 午後の腰痛は座り方のせい?デスクワーク中に崩れる姿勢の原因を解説
【投稿者情報】平井 大樹

平井塾 代表。みゅう整骨院 代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。
「患者様の人生に、健康の安心を。」
私は、これまで20年間、延べ10万人を超える患者様と向き合ってきました。その中で最も大切にしてきたのは、「痛みを取る」ことだけではなく、「患者様が心から安心して過ごせる毎日をサポートする」ことです。
- 長期にわたる信頼:私は、5年以上通われる方が211名。その中で10年以上通われる方も93名いらっしゃいます。これは、一時的な改善ではなく、患者様が私に一生の健康を任せてくださっている証です。
- 根本的なアプローチ:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)という独自の手技で、痛みの箇所だけでなく、その根本原因である身体全体の歪みや動きの不調にアプローチします。
- 予約が取れない理由:広告を一切使わず、患者様のご紹介だけで新規予約は5年以上待ちの状態です。現在、お取りする予定はありません。
このコラムが、あなたの不調を改善し、より豊かな毎日を送るための一歩となれば幸いです。

