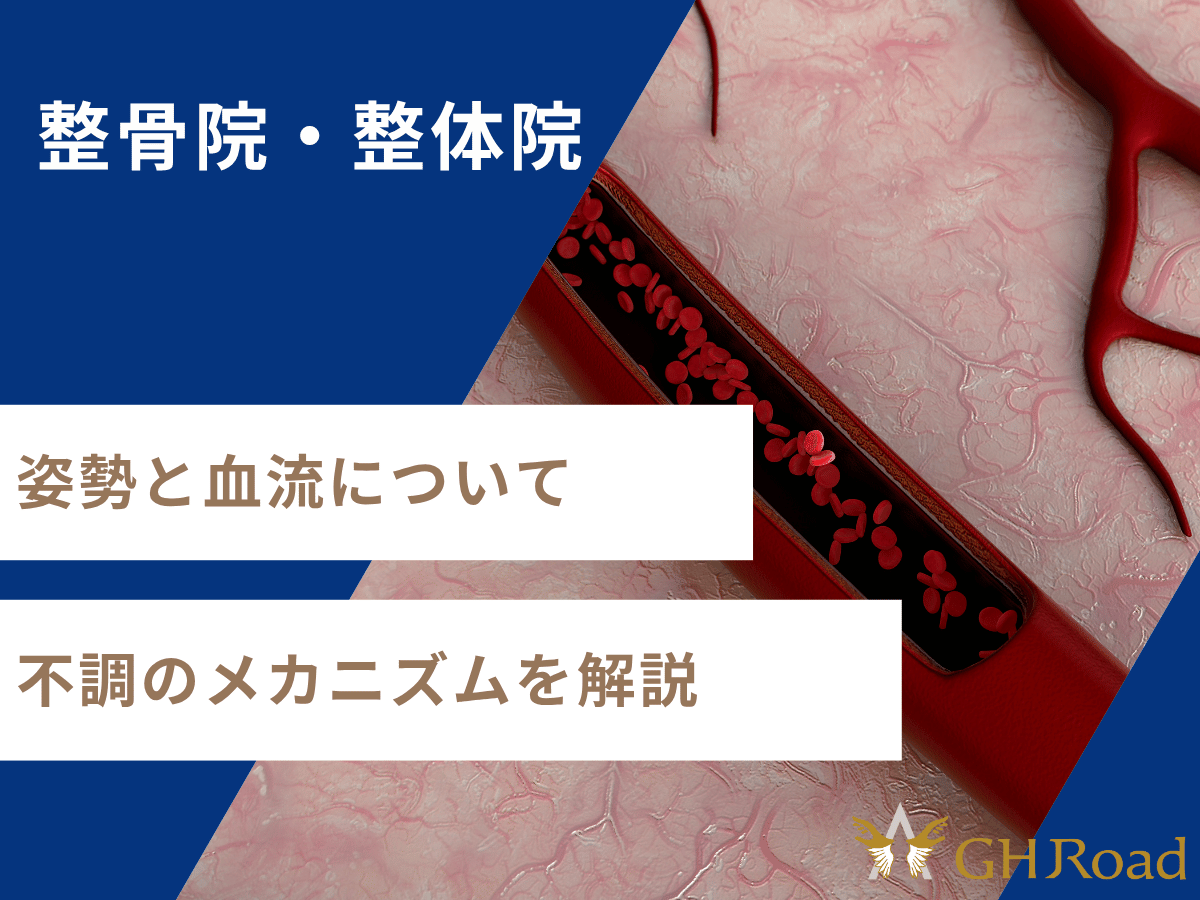「最近、体がだるい」「手足が冷える」「肩や腰が重い」
そんな不調を感じているのに、検査では異常なしと言われた経験はありませんか?
実はそれ、姿勢の崩れによる血流の滞りが関係しているかもしれません。
現代人の多くは、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用によって、猫背・巻き肩・ストレートネックといった「姿勢の乱れ」が進んでいます。
この姿勢の歪みが、骨格のバランスを崩し、筋肉の緊張を高め、結果として全身の血流を悪化させてしまうのです。
血流が悪くなると、身体のすみずみに必要な酸素や栄養が届かなくなり、老廃物の排出も滞ります。
それによって、肩こり・腰痛・頭痛・むくみ・冷えなど、一見バラバラに見える不調が同時に起こることも少なくありません。
ではなぜ、姿勢の崩れが血流を悪くするのでしょうか?
その根底には、身体の構造的なつながり(姿勢循環)が深く関係しています。
私たちの身体は、骨・筋肉・筋膜・内臓・神経・血管が一体となって働くひとつのユニットです。
姿勢が崩れると、関節や筋膜の滑走性が低下し、血液やリンパ、神経の流れが妨げられます。
つまり「姿勢の乱れ=循環の乱れ」であり、それが慢性的な不調を生む構造的な原因なのです。
平井塾では、この「姿勢と循環の関係」を根本から整えるために、独自の理論に基づいた姿勢循環整体を行っています。
これは、FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)で関節や筋膜の微細なエラーを整えた後、全身の循環を回復させる施術法です。
本記事では、
「姿勢が崩れると血流はどう変化するのか」
「血流の悪化が引き起こす症状と改善法」
「血流を整える姿勢づくりの実践法」
をわかりやすく解説します。
姿勢と血流の関係を理解し、流れる身体を取り戻すことができれば、冷えやだるさ、慢性的な痛みから解放されるだけでなく、心身ともに軽やかな日常を取り戻せるはずです。
目次
姿勢が血流に与える影響
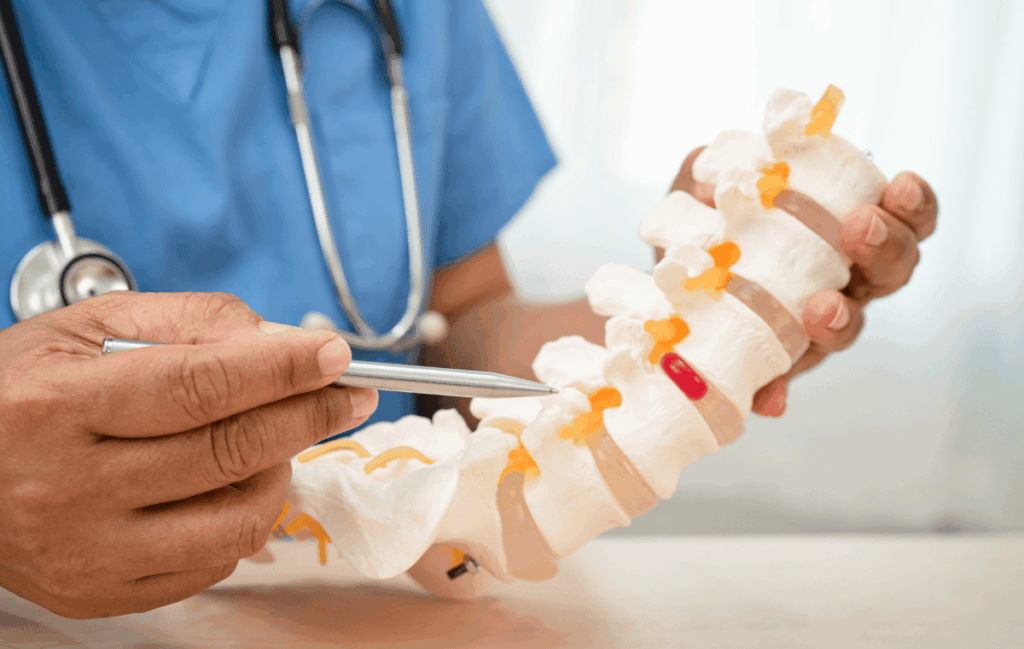
姿勢は単なる見た目の問題ではありません。
実は、私たちの血液の流れ──つまり「循環」の質を大きく左右しています。
立つ、座る、歩くといった日常動作の中で、背骨や骨盤のわずかな傾きが、全身の血流リズムを変えてしまうのです。
姿勢の悪化と血流低下のメカニズム
人間の身体は、本来「重力に対して最も効率よく立てる構造」を持っています。
しかし、猫背や前かがみ姿勢、長時間の座り姿勢が続くと、この重力線から身体がずれてしまいます。
すると、首・肩・背中・腰の筋肉が常に緊張状態となり、筋肉の中を走る血管が圧迫され、血流が滞ります。
血液が届かない部分は酸素不足となり、代謝物が溜まりやすくなるため、「こり」「だるさ」「痛み」といった症状が現れやすくなるのです。
さらに、骨盤が後傾することで内臓の位置も下がり、腹腔内の圧力が上昇して静脈やリンパの流れが悪化します。
つまり、姿勢が崩れると「骨格→筋肉→血管→内臓」といった全身の連動システムが次々と滞っていくのです。
猫背と血流の関係
猫背は、現代人に最も多い姿勢不良の一つです。
背中が丸まり、肩が前に出ることで、胸郭(肋骨まわり)が硬くなり、呼吸が浅くなります。
呼吸が浅くなると、酸素の取り込みが減り、肺や心臓まわりのポンプ機能が低下してしまいます。
結果として、心臓が送り出す血流の勢いが弱まり、全身の循環効率が落ちてしまうのです。
特にデスクワークで長時間猫背姿勢が続くと、「上半身の血流が滞り、肩こりや頭痛を起こす」「下半身の循環が悪くなり、むくみや冷えが出る」といった全身性の不調につながります。
平井塾では、このような猫背由来の循環低下を姿勢循環整体で整えていきます。
胸郭や骨盤の動きを同時に整えることで、「呼吸の深さ=循環の質」を高めることを目的としています。
ストレートネックが引き起こす血流問題
スマートフォンやPC作業で首が前に出る「ストレートネック」も、血流低下の大きな原因です。
首の前傾姿勢が続くと、首まわりの筋肉(胸鎖乳突筋や僧帽筋上部)が過緊張し、首を通る頸動脈・椎骨動脈が圧迫されます。
これにより、脳や頭部への血流が低下し、集中力の低下、頭痛、めまい、耳鳴りなどが起こることがあります。
さらに、首の血流が悪くなると、自律神経のバランスにも影響が出ます。
交感神経が優位に傾き、全身の血管が収縮し、慢性的な「冷え」や「緊張体質」が進行してしまうのです。
筋肉の緊張と血流の関連性
血流を支えているのは、心臓だけではありません。
筋肉も第二のポンプとして、全身に血液を循環させています。
ところが、姿勢の崩れによって筋肉が常に緊張した状態が続くと、そのポンプ機能がうまく働かなくなります。
緊張した筋肉は硬く縮こまり、血管を圧迫してしまうため、結果的に血流が滞るのです。
反対に、適度に動いて柔軟性を保った筋肉は、ポンプとしてスムーズに働き、血液・リンパの流れを促進します。
つまり、筋肉の緊張をゆるめることは、「血流をよくする」ことと同義です。
平井塾のFJAでは、関節や筋膜を丁寧に観察し、力ではなく構造の調和で筋緊張を解放することで、自然な循環を取り戻していきます。
姿勢が崩れると起こる身体の変化

姿勢が少し崩れるだけで、「疲れやすい」「体が重い」「集中できない」と感じることがあります。
それは単に筋肉が凝っているだけでなく、身体の構造的なバランスが崩れ、血流と神経の通り道が乱れているサインです。
身体は一つのユニットでつながっており、どこかが崩れると、その影響は全身に波及します。
骨格の歪みが血流を妨げるメカニズム
骨格が正しい位置にあると、血液は重力に逆らわずスムーズに全身を循環します。
しかし、姿勢が悪化して骨盤が傾いたり、背骨が曲がったりすると、その歪みが筋肉の緊張を引き起こし、血管を圧迫します。
たとえば、骨盤が後ろに倒れると、太ももの裏やお尻の筋肉が常に張った状態になります。
この緊張が坐骨神経や血管を圧迫し、脚の冷えやむくみ、だるさにつながります。
また、背骨が丸くなる(猫背)と、肋骨の動きが制限され、呼吸が浅くなって心臓や肺のポンプ機能が低下します。
すると、全身に酸素を運ぶ力が弱まり、慢性的な疲労感を感じやすくなります。
平井塾では、このような「骨格の歪み→血流停滞→症状」という構造的連鎖をFJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)で丁寧に解きほぐしていきます。
筋肉の緊張と自律神経の乱れ
姿勢の崩れは、筋肉だけでなく神経のバランスにも影響を与えます。
特に、肩や首の筋肉がこわばると、そこを通る自律神経の働きが乱れやすくなります。
交感神経が優位になると、血管が収縮し、手足の冷えや不眠、頭痛が起こりやすくなります。
反対に、副交感神経が働きにくくなると、リラックスができず、常に身体が「戦闘モード」になってしまいます。
つまり、姿勢の乱れは単なる見た目の問題ではなく、身体をコントロールする神経システムのバランスを崩す要因なのです。
平井塾では、姿勢循環整体によって呼吸・骨盤・背骨の動きを整えることで、自律神経のバランスを回復し、自然に緊張から解放された身体を取り戻すサポートをしています。
血流低下が引き起こす代表的な不調(肩こり・冷え・むくみ・頭痛)
血流が悪くなると、酸素や栄養が全身に届かなくなり、老廃物の排出も滞ります。
その結果として、次のような不調が現れやすくなります。
- 肩こり・首こり:筋肉が酸欠状態になり、疲労物質がたまりやすい。
- 冷え・むくみ:末梢の血管が収縮し、下半身への循環が滞る。
- 頭痛・めまい:脳への血流不足と、首の筋肉のこわばりによる神経圧迫。
- 集中力の低下:酸素供給の減少により、脳の働きが鈍くなる。
こうした症状は、単に「血行が悪い」だけではなく、姿勢の歪みが血流の経路そのものを変えてしまっている状態です。
つまり、痛みや冷えは「結果」であり、本当の原因は循環を阻害する構造の乱れにあるというのが、平井塾の考え方です。
身体は、本来つねに流れるようにできています。
その流れが止まるのは、構造のどこかに「詰まり」や「ねじれ」があるからです。
姿勢を整えることは、血流を取り戻すことであり、同時に身体の自然なリズムを取り戻すことでもあります。
血流と姿勢の深い構造的つながり

血液は心臓から押し出されるだけでなく、筋肉や関節、呼吸の動きによっても流れています。
つまり、血流は「循環器の働き」だけでなく、「姿勢と運動のリズム」によって大きく左右されるのです。
姿勢が乱れると、骨格の配列が崩れ、筋肉や筋膜の伸び縮みが不均一になります。
その結果、血液・リンパ・神経・体液といった流れが滞り、全身のバランスが崩れます。
この「構造と循環の関係」を理解することが、慢性的な不調を根本から整える第一歩です。
姿勢を支える「筋膜」と「循環」の関係
筋膜とは、筋肉や臓器を包み込み、全身を一枚のシートのようにつなぐ組織です。
この筋膜がスムーズに動くことで、筋肉や血管の滑走性が保たれ、血流が正常に保たれます。
しかし、姿勢が崩れて筋膜がねじれたり、硬くなったりすると、その部分で血管や神経が圧迫され、循環が悪くなります。
たとえば、肩甲骨まわりや骨盤まわりの筋膜が硬くなると、上半身・下半身ともに血液が流れにくくなり、冷えやむくみ、こりの原因になります。
平井塾のFJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)は、まさにこの「筋膜と関節の滑走不良」に対して働きかける手技です。
力で押すのではなく、手で聴くように観察し、どの層で流れが止まっているのかを感じ取りながら、筋膜の動きを回復させます。
筋膜が整うと、筋肉と血管が自然に動き出し、「押さなくても血流が戻る」身体へと変わっていくのです。
呼吸・横隔膜・骨盤のリズムが血流を作る
呼吸の動きは、全身の循環に直結しています。
深く息を吸うとき、横隔膜が下がり、腹腔内の圧力が変化します。
この圧の変化が、静脈やリンパを押し上げ、下半身から心臓へ血液を戻す「自然のポンプ」の役割を果たしています。
ところが、猫背やストレートネックで姿勢が崩れると、胸郭が縮こまり、横隔膜がうまく動かなくなります。
呼吸が浅くなることで、この循環ポンプの力が弱まり、血流が滞ってしまうのです。
また、骨盤は呼吸と連動して前後に小さく動いています。
横隔膜と骨盤底筋の動きがかみ合うことで、呼吸・姿勢・循環がひとつのリズムとして働いているのです。
平井塾の姿勢循環整体では、この呼吸リズムと骨盤の動きを整えることで、全身の血流・リンパ・神経の流れを自然に高めていきます。
呼吸が深くなるほど、体が温まり、心までゆるむ。
これこそが「姿勢と循環の調和」がもたらす自然な変化です。
姿勢の乱れは「体液の流れ」にどう影響するのか
姿勢が悪くなると、影響を受けるのは血液だけではありません。
体内には、血液・リンパ液・脳脊髄液など、複数の「流体」が存在します。
これらの流れが滞ると、代謝・神経・ホルモンの働きにも影響が及びます。
たとえば、首や背骨の歪みは、脳脊髄液(中枢神経を保護する液)の循環を妨げ、頭痛やめまい、集中力低下といった症状を引き起こします。
また、腹部の緊張や骨盤の硬さは、リンパの流れを阻害し、むくみや内臓の不調につながります。
身体は「流れ」が止まると不調を訴えます。
平井塾では、この体液循環を整えるために、全身の構造を同時に観察し、流れを回復させる「姿勢循環整体」を行っています。
血流が悪いと出る症状

血液は、全身に酸素と栄養を届け、老廃物を回収する生命の流れです。
その流れが滞ると、体のどこかに必ず「詰まり」や「重さ」といったサインが現れます。
多くの人は、この状態を「筋肉が硬い」「冷えている」と感じますが、実際には姿勢の崩れによって血管が圧迫され、循環がうまく機能していないのが本当の原因です。
ここでは、血流が悪化したときに現れやすい代表的な不調を紹介します。
頭痛や肩こりに関連する血流の影響
血流が悪いと最初に現れやすいのが、頭痛や肩こりです。
特に、首や肩まわりの筋肉が緊張して血管を圧迫すると、脳に送られる血液量が減り、酸素不足が起こります。
その結果、脳の血管が拡張して神経を刺激し、ズキズキするような頭痛が発生します。
また、首まわりの血流が滞ると、老廃物が溜まり、重だるさや集中力の低下を感じるようになります。
猫背やストレートネックの人は、特に首の付け根が硬くなりやすく、頸動脈や椎骨動脈の流れが弱まりやすい傾向にあります。
平井塾のFJA(ファシアティックジョイントアプローチ)では、首・胸郭・肩甲骨の動きを細かく観察し、筋膜の滑走不良を整えることで、血流と神経の通り道を回復させます。
腰痛と血流不足の関係
腰痛も、血流の低下と深く関わっています。
腰の筋肉(脊柱起立筋・大腰筋など)は、姿勢を保つために常に働いています。
そのため、血流が滞るとすぐに疲労が蓄積し、硬くなって痛みを引き起こします。
また、骨盤が歪んで静脈の還流が悪くなると、腰部の深部にある筋膜や関節が酸欠状態になり、「重い」「張る」「痛い」という感覚が慢性化します。
平井塾の姿勢循環整体では、骨盤の動きと背骨のリズムを整え、腰部の循環を取り戻すことで、痛みを繰り返さない身体づくりを行います。
腰の痛みを単なる筋肉のコリとして見るのではなく、「血液が届いていない構造的問題」として捉えることが、根本改善の第一歩です。
疲れやすさと血流異常
「寝ても疲れが取れない」「体が重い」と感じるとき、それは単なる疲労ではなく、全身の血流が低下しているサインです。
血液が十分に巡っていないと、細胞が酸素不足になり、エネルギーを生み出す力が弱まります。
さらに、代謝が落ちることで体温が下がり、免疫力までも低下します。
その結果、
・疲れやすい
・風邪をひきやすい
・朝スッキリ起きられない
といった「慢性疲労型の症状」が現れるのです。
平井塾では、このような慢性疲労を「構造的循環不良」と考えます。
血流を改善するには、マッサージや運動だけでなく、姿勢・呼吸・骨盤のリズムを取り戻すことが必要です。
姿勢循環整体では、深い呼吸を促しながら全身の構造を整えることで、自律神経の働きを安定させ、身体の内側から「巡る力」を取り戻していきます。
血流が悪いとき、身体は必ず信号を出しています。
肩こりや腰痛、だるさ、冷え──それらは流れが止まっていることを教えてくれるサインです。
そのサインを無視せず、構造から整えることで、身体は必ず変わっていきます。
悪い姿勢が続くことで起こる慢性不調

姿勢が崩れたまま長時間過ごすことは、身体にとって大きな負担です。
筋肉・関節・神経・血管のどれもが休むことなく緊張を強いられ、「痛み」「だるさ」「冷え」「むくみ」といった不調が慢性的に続く原因となります。
このような状態を、平井塾では「構造的循環不全」と呼びます。それは単に一部の筋肉が凝っているのではなく、
全身の循環リズムが崩れた“姿勢の固定パターン”なのです。
デスクワークによる循環不良の典型パターン
長時間の座り姿勢は、下半身の血流を著しく低下させます。
特にデスクワークでは、次のような構造的変化が起こります。
- 骨盤が後傾し、背骨のS字カーブが失われる
- 腰から背中にかけて筋肉が常に緊張する
- 太もも裏(ハムストリングス)が圧迫され、下肢静脈の血流が停滞
- 内臓が下がり、腹腔内の循環が悪化
この状態が数時間続くだけで、下半身の静脈血が戻りにくくなり、足のむくみや冷え、だるさが生じます。
さらに、背中が丸まることで呼吸が浅くなり、酸素の取り込み量が減少。脳への血流が減ることで、集中力の低下や頭の重さを感じやすくなります。
平井塾では、このような姿勢性循環不良に対して、FJAで骨盤と背骨の連動を整え、姿勢循環整体で呼吸のリズムを再教育することで、座っていても流れる身体を取り戻すことを目指しています。
足のむくみ・頭の重さ・だるさの共通点
むくみ、頭の重さ、全身のだるさ、これらは一見別々の症状に見えますが、実はすべて「血液とリンパの還流不足」という共通の原因を持っています。
姿勢が崩れて体のポンプ機能が弱まると、心臓へ血液を戻す力が不足し、下半身や頭部に血液が滞ります。
その結果、
- 下半身では「むくみ・冷え」
- 上半身では「頭の重さ・目の疲れ」
が生じます。
特に猫背の人は、胸郭が硬くなり横隔膜がうまく動かないため、全身の血液を循環させる呼吸ポンプが働きにくくなります。
その状態が続くと、筋肉だけでなく神経や内臓の働きまで鈍くなっていきます。
身体が重いのは、筋肉の問題ではなく「流れの滞り」。
姿勢が整えば、血も気も同時に巡り始めます。
「全身の循環が滞る」という構造的サイン
身体は常に、「循環が止まっている場所」を教えてくれます。
それが、痛み・張り・冷え・しびれなどの形で現れます。
例えば、
- 同じ場所ばかり凝る
- 常に片方の肩だけ重い
- 冷える部位がいつも決まっている
といった状態は、身体の構造が一定方向に固定されているサインです。
このような構造的な滞りを放置すると、血流の道筋が変わり、全身の循環リズムが乱れていきます。
平井塾の姿勢循環整体は、この「滞り」を力で押すのではなく、身体の自然なリズム(呼吸・重心・連動)を取り戻すことで解消します。
全身がつながって流れ始めると、
- 手足が温かくなる
- 呼吸が深くなる
- 頭がスッキリする
といった変化が自然に現れます。
これは、血流という生命の循環が再び働き始めた証拠です。
血流を改善するための姿勢改善方法

血流を良くするために大切なのは、単に「動かすこと」ではありません。ポイントは、姿勢そのものを整えて流れやすい身体の構造をつくることです。
筋肉を強くする、マッサージを受けるといった一時的な対処ではなく、姿勢・呼吸・骨盤の連動を意識することで、全身の循環が自然に回り出します。
ここでは、平井塾の「姿勢循環整体」の理論をもとに、自分でできるケアから専門的な改善法まで順に紹介します。
デスクワーク時の正しい姿勢
血流改善の第一歩は、「座り方」の見直しです。
多くの人が長時間同じ姿勢で座り続けることで、骨盤や背骨が歪み、下半身の血流が滞ってしまいます。
正しい姿勢のポイントは次の通りです。
- 坐骨で座る:お尻の下の骨(坐骨)で体を支えるように意識する。
- 骨盤を立てる:背もたれにもたれず、骨盤を軽く前に起こす。
- 膝は90度、足裏を床にしっかりつける:血液が足先に滞らないようにする。
- 背筋を伸ばし、肩の力を抜く:首と肩の緊張を防ぐ。
- 30分に一度、立ち上がってリセット:ふくらはぎを動かすことで下肢の循環を促す。
平井塾では、これを「姿勢の呼吸」と呼びます。呼吸をするように姿勢をこまめに変えることで、身体は自然に流れる構造を取り戻していきます。
自宅でできるストレッチ・運動
姿勢を整えるには、血流の通り道を広げる「動き」も必要です。
とはいえ、無理な筋トレではなく、緊張をゆるめる動きが大切です。
おすすめのセルフケアは以下の3つです。
- 胸を開くストレッチ
両手を後ろで組み、胸を軽く張って深呼吸。
猫背による胸郭の硬さを和らげ、呼吸が深くなる。 - 骨盤スイング運動
椅子に座ったまま骨盤を前後にゆっくり動かす。
仙腸関節の可動が改善し、下半身の血流がスムーズになる。 - ふくらはぎポンプ運動
立ったままかかとを上げ下げ。
下半身に溜まった血液を心臓へ戻すサポートになる。
どれも短時間ででき、続けるほど全身の巡りが良くなります。
重要なのは、「どの筋肉を動かすか」ではなく、呼吸と動きがつながる感覚を意識することです。
整骨院での姿勢改善トレーニング
セルフケアで改善が難しい場合や、長年の癖がある方には、専門家による姿勢改善が効果的です。
平井塾の理論を学んだ整骨院では、以下のような段階的アプローチで、姿勢と血流を整えます。
- FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)で微細な歪みを整える
筋膜や関節の滑走不良を改善し、動きの「つながり」を回復。 - 姿勢循環整体で全身のリズムを取り戻す
骨盤・胸郭・呼吸を同時に整え、体液・リンパ・神経の循環を促す。 - 正しい姿勢動作の再教育
座る・立つ・歩くといった動作の中で、自然な重心バランスを身体に覚えさせる。
平井塾では、姿勢矯正を「無理に形を直す」ものではなく、身体が自然に整う構造を思い出させる学びと考えています。
姿勢は「作る」ものではなく、「戻る」もの。自然な循環を取り戻すことが、血流改善の本質です。
血流を改善する姿勢循環整体とは?

血流の滞りを根本から整えるためには、単に筋肉をほぐしたり、血管を刺激したりするだけでは不十分です。
なぜなら、血液の流れを決めているのは「心臓」だけではなく、骨格・筋膜・関節・呼吸といった身体構造全体の調和だからです。
平井塾の「姿勢循環整体」は、この構造的な視点から血流を回復させる独自の手技法です。
身体の形ではなく、流れに焦点を当てることで、姿勢の歪みと血流の滞りを同時に解放していきます。
FJAで細部の歪みを整える
姿勢循環整体の第一段階は、FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)による微細な構造調整です。
FJAは、平井塾代表・平井先生が20年以上の臨床経験から体系化した手技で、「関節と筋膜(ファシア)の動きを聴く」ことを目的としています。
多くの施術が「痛い部分を押す・揉む」といった結果への処置を行うのに対し、FJAは「なぜそこに負担が生じたのか」という原因の構造を探ります。
手で触れながら、
・どの層で動きが止まっているか
・どの方向にねじれが生じているか
・呼吸と動きがどう連動しているか
を感じ取り、わずかなタッチで動きを解放していくのです。
このとき施術者が使うのは力ではなく観察。
筋膜や関節がゆるみ、血流や神経の通りが自然に戻るよう導きます。
FJAとは「押す手技」ではなく、「聴く手技」。
触れることで、身体が自ら整う道筋を教えてくれるのです。
姿勢循環整体で全身の流れを回復
FJAで細部の動きを取り戻した後、次に行うのが平井塾独自の姿勢循環整体です。
これは、「姿勢」と「循環」を一体のものとして整える手技。骨盤・背骨・胸郭・頭蓋を一定のリズムで動かし、全身の体液・リンパ・神経の流れを調和させていきます。
従来の整体が「骨格を正しい位置に戻す」ことを目的とするのに対し、姿勢循環整体は「身体が自然に正しい流れを思い出す」ことを目的としています。
特徴的なのは、呼吸を軸にしたリズム調整です。
呼吸に合わせて関節をわずかに誘導し、横隔膜・骨盤底筋・背骨の波打つような動きを再構築します。
この流れる姿勢が回復すると、次のような変化が現れます。
- 手足の冷えが和らぐ
- 背中の張りが消える
- 呼吸が深くなり、肩の力が抜ける
- 頭が軽くなる
- 睡眠の質が改善する
つまり、姿勢循環整体は構造から血流を変える施術なのです。
「押さない・戻さない」構造的アプローチの理由
平井塾の手技が他と大きく異なるのは、強い刺激で無理に形を変えようとしない点です。
なぜなら、人間の身体は「押された方向」ではなく、気づいた方向に整うようにできているからです。
姿勢循環整体は、力で形を戻すのではなく、身体に「正しい流れ」を思い出させるアプローチ。
そのため、施術後の変化が穏やかで、持続性が高いのが特徴です。
患者さんの中には、
「終わった瞬間から体がポカポカする」
「息が深く入るようになった」
と感じる方も多く、これは全身の循環リズムが再び動き出した証拠です。
姿勢を整えることは、骨を動かすことではなく、流れを回復させること。
循環が生まれた瞬間に、痛みや冷えは自然と消えていきます。
姿勢循環整体がもたらす根本改善
FJAで「部分の動き」を整え、姿勢循環整体で「全体の流れ」を回復させる。
この2つの技術は、平井塾が提唱する構造思考型治療の両輪です。
従来の「症状を取る」施術ではなく、「構造を変えることで、症状が起こらない身体を育てる」。
それが、平井塾が20年以上にわたり伝え続けてきた哲学です。
身体が正しいリズムで呼吸し、血液が自然に巡るようになると、痛みも冷えも、根本から改善していきます。
血流が良いと出る症状

血流が整うと、身体は目に見えないレベルから変化を始めます。
呼吸が深くなり、筋肉がゆるみ、体温が上がる。
それは単なる一時的なリラックスではなく、身体の構造が巡る状態に戻ったサインです。
多くの方は、「痛みが消える」ことをゴールと考えがちですが、本当の回復は「全身が流れるように働き始める」こと。
その変化を感じ始めたとき、身体は自ら治る方向へと舵を切っています。
血流改善による身体の変化
姿勢循環整体やFJAで全身の流れが回復すると、次のような変化が段階的に現れます。
- 身体が温かくなる
末梢血管の収縮が取れ、体温が1℃上がるだけで免疫力は約5倍向上すると言われています。 - 呼吸が深くなる
胸郭と骨盤の動きが連動し、横隔膜の上下運動がスムーズになる。
結果として酸素の取り込み量が増え、全身の代謝が上がります。 - 筋肉の柔軟性が戻る
血液が十分に行き届くことで、筋肉が酸素を受け取り、硬さが自然に取れていく。 - 姿勢が自然に整う
循環が改善すると、身体が軽くなり、重力に沿った姿勢が“楽に”保てるようになる。 - 心が落ち着く
副交感神経が優位になり、呼吸とともにリラックス感が広がる。
「気持ちが明るくなる」「眠りが深くなる」と感じる方も多くいます。
このような変化は、「何かを直した結果」ではなく、構造の流れを取り戻した結果として、身体が自ら整っている現象です。
血流が良い人の特徴
血流が良い人には、共通する特徴があります。
それは、筋肉や関節の弾力だけでなく、呼吸・姿勢・思考までもが柔らかいことです。
平井塾では、次のような身体の状態を「姿勢循環が整っている」と定義しています。
- 朝起きたとき、体が軽い
- 呼吸が深く、肩や首に力が入らない
- 姿勢を意識しなくても背筋が伸びる
- 手足が常に温かい
- 食後や夜に眠気が出すぎない
- 不調が出ても回復が早い
これらは、筋肉を鍛えた結果ではなく、「血液と呼吸が調和している構造」によって自然に得られる状態です。
姿勢循環整体では、誰でもこの循環のリズムを取り戻せるよう、身体の構造を教育するように整えていきます。
血流が良くなりすぎると注意すべきポイント
一方で、血流が急激に変化すると、一時的に違和感を感じる方もいます。
たとえば、施術後に「身体がだるい」「眠気が強い」「体が重く感じる」など。
これは、停滞していた老廃物や二酸化炭素が流れ始めた正常な反応です。
筋膜やリンパの通り道が開いたことで、身体が流す準備を始めているサインといえます。
このような場合は、
- 水分をしっかりとる
- 早めに休む
- 激しい運動を避ける
ことで、体は自然に安定します。
血流が安定すると、体内の熱とエネルギーが均等に巡り、施術前よりも軽く、呼吸が深い状態が続くようになります。
血流が良くなるということは、「治る力」が動き出したということ。
身体は、整った姿勢とともに、再び生きた循環を取り戻していくのです。
血流が良い状態とは、筋肉が柔らかい状態でも、姿勢が美しい状態でもなく、「全身が呼吸しているように流れている状態」です。
それこそが、平井塾が提唱する「姿勢循環の本質」であり、痛みや不調を超えた健康の基盤なのです。
姿勢改善のための対策とケア
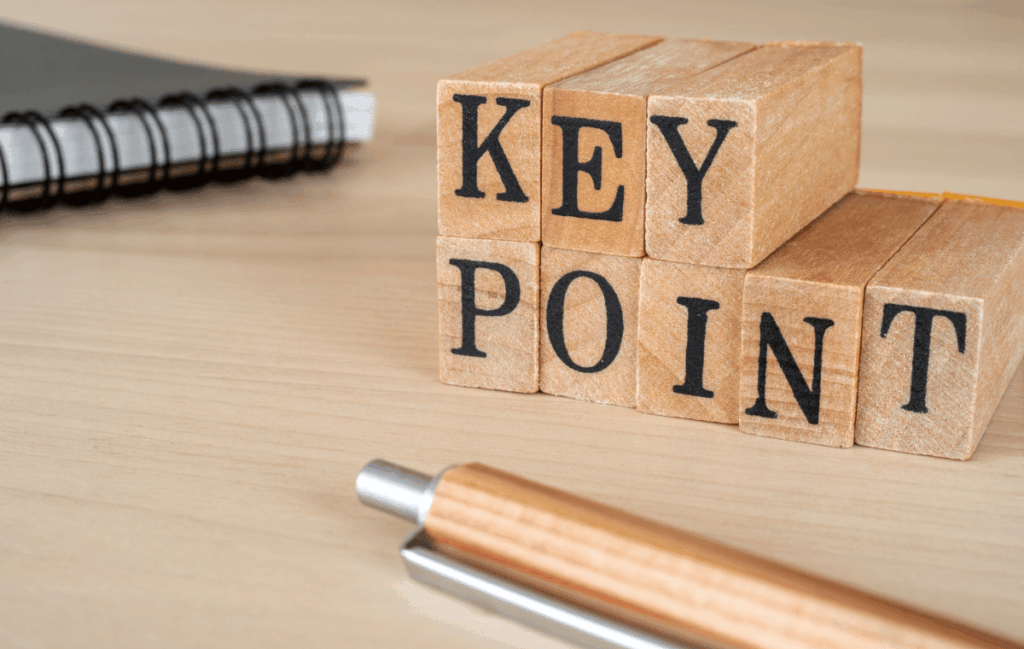
姿勢を整えることは、単なる見た目の問題ではありません。
それは、血液・リンパ・神経といった「流れの道」を整えることです。
正しい姿勢を身につけることで、全身の循環が自然に回復し、身体が自ら治る状態に戻っていきます。
しかし、良い姿勢を一時的に意識しても、生活の中で崩れてしまえば意味がありません。
大切なのは、「正しい姿勢を保つ力を育てること」。
ここでは、日常生活・運動・呼吸を通してできる姿勢ケアの方法を紹介します。
日常生活でできる姿勢ケア方法
日常の中で姿勢を保つコツは、長時間同じ姿勢を取らないことです。
デスクワーク・スマホ操作・家事など、どんな場面でも姿勢が固定されると、
筋肉が硬直し、血流が滞ってしまいます。
今日からできる簡単なケアとして、次の3つを意識してみましょう。
- 30分に一度、立ち上がる
立つだけで重力バランスがリセットされ、下半身の血流が促進されます。 - 肩を軽く後ろに引き、深呼吸
胸を開くと横隔膜が動き、呼吸のポンプ作用で全身の循環が回りやすくなります。 - 足を組まない・片側荷重を避ける
骨盤の傾きを防ぎ、左右均等に重心を保つ練習になります。
このような小さな姿勢リセットをこまめに行うことで、血流と神経の滞りが起きにくい身体に変わっていきます。
姿勢の意識は「時間」ではなく「回数」で育つ。短い動作の積み重ねが、流れる身体を作ります。
ウォーキングと運動での改善
姿勢と血流を整える上で、歩くことは最もシンプルで効果的な運動です。
歩行には、骨盤の回旋・脊柱の伸展・腕の振りなど、全身の関節と筋膜を連動させる循環運動が含まれています。
正しいウォーキングのポイントは以下の通りです。
- 骨盤を立てて歩く:背筋を伸ばし、下腹部を軽く引き上げるように。
- かかとから着地する:足裏全体を使うことでふくらはぎのポンプ作用が働く。
- 呼吸を意識する:歩幅に合わせて、息を「吸って・吐いて」を繰り返す。
1日10〜15分のウォーキングでも十分です。
呼吸と足のリズムがそろってくると、全身の循環リズムが整い、「歩くほどに身体が軽くなる」感覚を得られるでしょう。
呼吸法を用いた姿勢改善
姿勢を整えるうえで、もっとも見落とされやすいのが「呼吸」です。
呼吸は、姿勢と血流をつなぐ見えない動きです。
平井塾では、次のような姿勢循環呼吸法を推奨しています。
- 椅子に浅く腰かけ、骨盤を立てる
- 胸を少し開き、背骨を軽く伸ばす
- 鼻から3秒吸い、口から6秒かけてゆっくり吐く
- 吐くときに、お腹がふっと沈み、骨盤がわずかに動くのを感じる
この「呼吸と骨盤の連動」を意識すると、横隔膜と骨盤底筋が自然に働き、体幹が安定します。
また、長く吐くことで副交感神経が優位になり、全身の血流が穏やかに広がっていきます。
姿勢は呼吸でつくられ、呼吸は姿勢で支えられる。
どちらか一方ではなく、「動きの調和」が循環を生むのです。
姿勢を整えるケアとは、身体を「固める」ことではなく、「流れる状態」を維持することです。
筋肉や骨格を支えるのは形ではなく循環。
その流れが滞らなければ、痛みも冷えも自然に遠のいていきます。
血流を整えると身体はどう変わる?
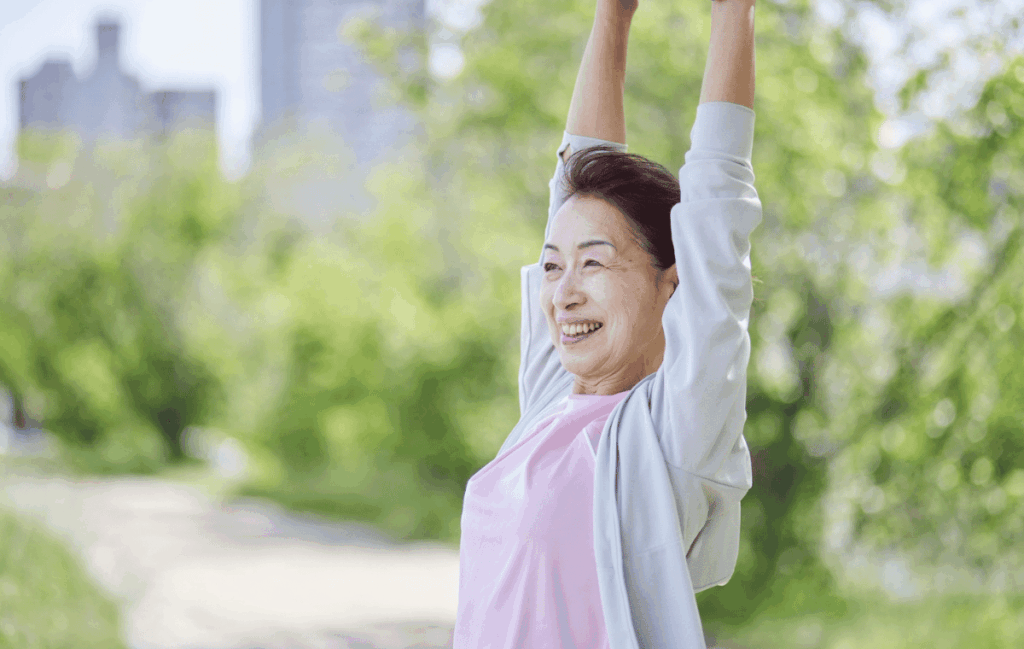
血流が整うと、身体は静かに、しかし確実に変化を始めます。
それは、筋肉がほぐれるような表面的な変化ではなく、身体の内側で起きる機能の再起動のようなものです。
姿勢が正され、骨格・筋膜・呼吸の連動が戻ることで、全身の体液や神経がスムーズに働き出します。
そしてその「流れの回復」が、代謝・免疫・精神の安定といった、目に見える変化をもたらすのです。
睡眠の質・集中力・代謝が上がる理由
血流が良くなると、身体の末端まで酸素と栄養が届きやすくなります。
その結果、細胞のエネルギー産生が活発になり、代謝が上がるのです。
代謝が上がることで体温が適正に保たれ、自律神経のバランスも安定し、夜は自然と深い眠りに導かれます。
朝の目覚めが軽くなり、日中の集中力や思考力も向上します。
特に、デスクワークや長時間同じ姿勢でいる人は、姿勢循環整体によって血流を取り戻すだけで、「頭が冴える」「眠りが深くなる」「朝の疲れが残らない」といった変化を実感されます。
これは単なるリラクゼーションではなく、身体のリズム(姿勢・呼吸・循環)が整った結果です。
冷え・むくみ・頭痛の改善メカニズム
血流を整えることは、冷えやむくみ、頭痛の根本改善にもつながります。
・冷え:末梢血管の収縮が取れ、毛細血管まで温かい血液が届くようになる。
・むくみ:リンパの流れが促進され、体内の水分循環がスムーズになる。
・頭痛:首や肩の緊張が取れ、脳への血流が安定する。
このように、血流が良くなると「症状がなくなる」というより、身体全体のコンディションが静かに上向くのが特徴です。
平井塾の姿勢循環整体では、呼吸と骨盤のリズムを整えることで全身の循環を改善し、これらの慢性症状を構造的に解消していきます。
自律神経が安定し呼吸が深くなる構造的変化
血流と自律神経は、密接に関係しています。
血管の収縮・拡張は自律神経によってコントロールされており、姿勢の乱れや呼吸の浅さが、この神経バランスを崩してしまいます。
しかし、姿勢循環整体で構造を整え、呼吸が深くなると、副交感神経が優位になり、身体は「安心・回復モード」に切り替わります。
すると、
- 眠りが深くなる
- 胃腸の働きが安定する
- 脈が穏やかになる
- イライラや不安が減る
といった、心身両面での変化が自然に現れます。
平井塾では、この状態を「循環が生きている身体」と呼びます。それは、力を抜いても姿勢が保てる、呼吸が自由にできる、そんなしなやかな安定を持つ身体です。
循環が整うと「生き方」も変わる
興味深いことに、血流が整うと多くの方がこう言います。
「気持ちが穏やかになった」「焦らなくなった」「視野が広がった」と。
これは、身体の循環が心の循環にも影響しているからです。
平井塾では、身体を整えることは、生き方を整えることという理念を大切にしています。
姿勢が整えば呼吸が整い、呼吸が整えば思考と感情も落ち着く。それが、身体の自然なリズムに沿った生き方なのです。
まとめ

姿勢が崩れると、血流も滞る。
この事実は、多くの不調の「共通の根」にあります。
肩こりや腰痛、冷えやだるさ、頭痛や集中力の低下、これらは、単なる筋肉の問題でも年齢のせいでもなく、「流れが止まっている身体」からのサインなのです。
姿勢と血流の関係を再確認
姿勢とは、単に骨格の形を正すことではありません。
姿勢が整うというのは、身体の内側で「血液」「リンパ」「神経」「呼吸」が調和して流れている状態を指します。
その流れが乱れれば、痛みや不調として現れ、整えば、温かさ・軽さ・安定感として実感されます。
つまり、姿勢と血流は「形と流れ」の関係であり、どちらか一方を整えるだけでは不十分なのです。
身体はひとつのユニットとして、常に全体で動いています。
痛みや不調は循環の乱れのサイン
平井塾では、不調や痛みを「敵」としてではなく、身体が流れを取り戻そうとしているメッセージと捉えます。
例えば、肩こりは「首や胸郭の動きが止まっている」サイン、腰痛は「骨盤と呼吸のリズムがずれている」サインです。
これを「押して治す」「動かしてごまかす」のではなく、なぜそこに滞りが起きたのか──その構造を読み解くこと。それこそが、平井塾の構造思考型の治療の原点です。
今後のケア方法と意識点
日常の中でできる最も大切なケアは、「姿勢を意識する時間を少しでも増やす」ことです。
・デスクワーク中に坐骨で座る
・30分ごとに立ち上がって深呼吸をする
・歩くときに骨盤を感じる
──そんな小さな積み重ねが、血流を守り、身体を軽くします。
そして、慢性的な不調や、呼吸の浅さ、手足の冷えを感じる方は、ぜひ一度、姿勢循環整体を受けてみてください。
全身のリズムが整うと、「血が流れる」と同時に「呼吸が通る」感覚を味わえます。
平井塾が伝えたいのは、押す技術ではなく、感じる手。その手で身体の声を聴くことこそ、真の治療の始まりです。
姿勢を整えるとは、形を正すことではなく、流れを取り戻すこと。
流れを取り戻すとは、自分自身の自然治癒力と再びつながること。
血流は、生命のリズムそのもの。そのリズムが回り始めると、身体も心も静かに調和を取り戻します。
「姿勢を正せば、血が流れる。血が流れれば、心が整う。」
平井塾の姿勢循環整体は、その自然の法則を形にした手技です。
身体は本来、治る方向を知っています。
あなたの身体の中にあるその力を、もう一度動かしてあげましょう。
▼関連する記事もあわせてご覧ください
- 「長時間のデスクワークで坐骨神経痛が悪化する…」そんな方へ。
痛みの原因と正しい座り方を詳しく解説しています。
→ 坐骨神経痛は「座りすぎ」が原因?デスクワーカーが知るべき正しい座り方 - 「午後になると腰が重い」「姿勢が傾く気がする」方は要チェック。
骨盤の歪みとデスクワーク姿勢の関係を詳しく解説しています。
→ 骨盤の歪みはなぜ起こる?デスクワークで崩れた姿勢を整える方法 - 「この痛み、腰痛?それとも坐骨神経痛?」
症状の違いや、見分け方のポイントをわかりやすく紹介しています。
→ 腰痛と坐骨神経痛の違いとは?間違えやすい痛みの見分け方 - 「座りすぎ」は腰だけでなく、全身に影響を与えます。
腰痛・肩こり・むくみを引き起こす共通の“循環の乱れ”を詳しく解説。
→ 座りすぎがもたらす全身の不調:腰痛・肩こり・むくみの共通原因とは? - 「午前は平気なのに午後になると腰が痛い…」
そんな“午後腰痛”の原因と、流れる姿勢をつくる方法を紹介しています。
→ 午後の腰痛は座り方のせい?デスクワーク中に崩れる姿勢の原因を解説
【投稿者情報】平井 大樹

平井塾 代表。みゅう整骨院 代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。
「患者様の人生に、健康の安心を。」
私は、これまで20年間、延べ10万人を超える患者様と向き合ってきました。その中で最も大切にしてきたのは、「痛みを取る」ことだけではなく、「患者様が心から安心して過ごせる毎日をサポートする」ことです。
- 長期にわたる信頼:私は、5年以上通われる方が211名。その中で10年以上通われる方も93名いらっしゃいます。これは、一時的な改善ではなく、患者様が私に一生の健康を任せてくださっている証です。
- 根本的なアプローチ:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)という独自の手技で、痛みの箇所だけでなく、その根本原因である身体全体の歪みや動きの不調にアプローチします。
- 予約が取れない理由:広告を一切使わず、患者様のご紹介だけで新規予約は5年以上待ちの状態です。現在、お取りする予定はありません。
このコラムが、あなたの不調を改善し、より豊かな毎日を送るための一歩となれば幸いです。