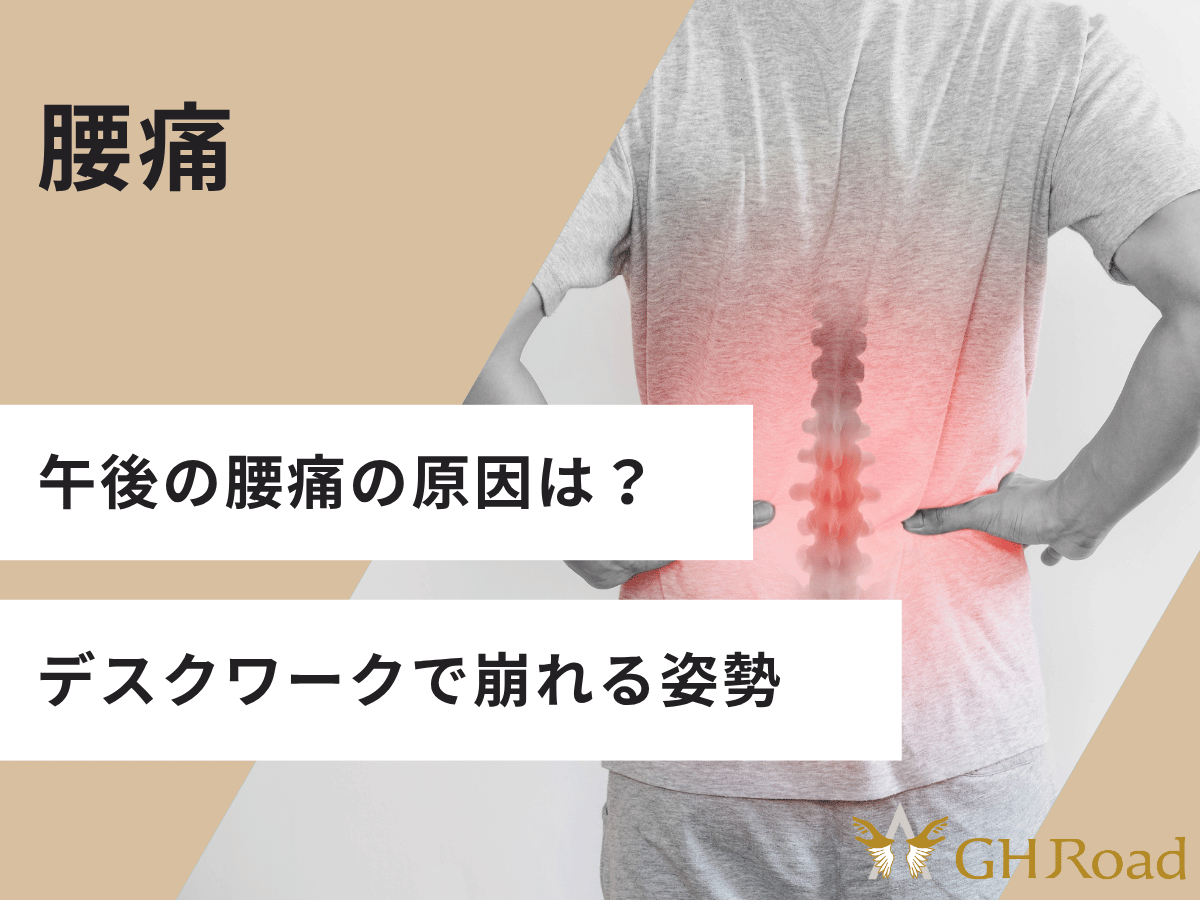「朝は平気なのに、午後になると腰が重くなる…」
「夕方になると座っていられないほど腰がつらい…」
そんな経験、ありませんか?
実はこの午後から始まる腰の痛みには、明確な理由があります。
それは、座り方のわずかな崩れが、時間とともに身体全体のバランスを乱しているからです。
デスクワークをしていると、最初は良い姿勢を保っていても、時間が経つにつれて骨盤が後ろに傾き、背中が丸まり、気づけば肩や首まで硬くなってしまいます。
この姿勢の変化は一瞬で起こるものではなく、「午後の疲れ」とともに静かに進行する構造的な崩れなのです。
平井塾では、この現象を「姿勢循環の乱れ」と呼びます。
つまり、
- 骨盤の傾き(構造)
- 呼吸の浅さ(機能)
- 血流の滞り(循環)
これらが同時に崩れることで、午後に腰痛というサインが現れるのです。
多くの人は「筋肉の疲れ」や「運動不足」と考えがちですが、本当の原因は、身体の流れが止まってしまうことにあります。
午後の腰痛は、身体が「そろそろ流れを戻して」と教えてくれるメッセージ。
本記事では、
- 午後に腰が痛くなる原因
- デスクワークで崩れやすい姿勢のパターン
- 正しい座り方と姿勢循環の整え方
を、平井塾の「構造思考」と「姿勢循環整体」の視点からわかりやすく解説します。
あなたの腰痛が、単なる疲れではなく、身体の流れを整えることで改善できることを、ぜひ知ってください。
座り方を変えれば、午後の腰痛は変わる。
そしてその変化は、あなたの一日の「流れ」そのものを整えてくれます。
目次
午後になると腰が痛くなる人が増えている理由

朝は快調なのに、午後になると腰がじわじわ痛み出す。
このような時間帯による腰痛を訴える人が、近年とても増えています。
特に、デスクワーク中心の働き方が主流になってからは、20代・30代の若い世代でもこの「午後腰痛」を感じるケースが多く見られます。
では、なぜ午後になると痛みが強くなるのでしょうか?
そこには、身体の「構造的疲労」と「循環の低下」が関係しています。
朝は快調なのに午後から痛む腰痛のメカニズム
午前中は筋肉や関節がまだ柔らかく、血流も活発で、神経もリフレッシュした状態にあります。
しかし、長時間座り続けることで、次第に筋肉が固まり、骨盤の角度が少しずつ後ろに傾いていきます。
このわずかな傾きが、午後になると「腰にじわじわと圧」をかけ、腰椎・筋膜・神経の働きを鈍らせてしまうのです。
さらに、デスクワーク中は集中しているため、呼吸が浅くなり、腹圧(お腹の内側の圧力)が低下。
その結果、腰を内側から支える力が弱まり、「支えきれない腰」を無理に姿勢でカバーしようとして痛みが出ます。
つまり、午後の腰痛とは、「姿勢の崩れ+呼吸の浅さ+血流の滞り」という三重の負担の結果なのです。
姿勢疲労が溜まる午後の落とし穴
人間の身体は、立っているよりも座っている方が腰への負担が大きいといわれています。
その圧力は立位の約1.4倍。
つまり、一日中座り続けていると、午前中に受けた腰への負荷が午後にピークを迎えるのです。
さらに午後は、
- 集中による肩・首のこわばり
- 代謝低下による体温の低下
- 水分不足による筋肉の硬化
なども重なり、腰部への血流がますます悪化します。
この「座る・止まる・冷える」という状態が、午後の腰痛を慢性化させる最大の要因となります。
平井塾では、この状態を姿勢循環の停滞と捉えています。
骨盤・背骨・呼吸・血流、この4つの循環が止まると、身体は静かに「痛み」という信号を出し始めるのです。
「集中しているほど痛くなる」のはなぜ?
午後の腰痛を訴える人の多くが口にするのが、「仕事に集中していると、気づいたら痛くなっている」という言葉です。
これは、心理的ストレスが身体の構造に影響を及ぼす典型的な例です。
緊張状態が続くと、交感神経が優位になり、筋肉は戦闘モードのまま固まり続けます。
さらに、無意識に呼吸が浅くなることで、横隔膜と骨盤底筋の連動が失われ、姿勢の支えが崩れてしまうのです。
つまり、午後の腰痛は「心身の姿勢疲労」。
心の緊張が身体の構造に波及し、姿勢と血流の流れを止めている状態といえます。
午後の腰痛はなぜ起こるのか?
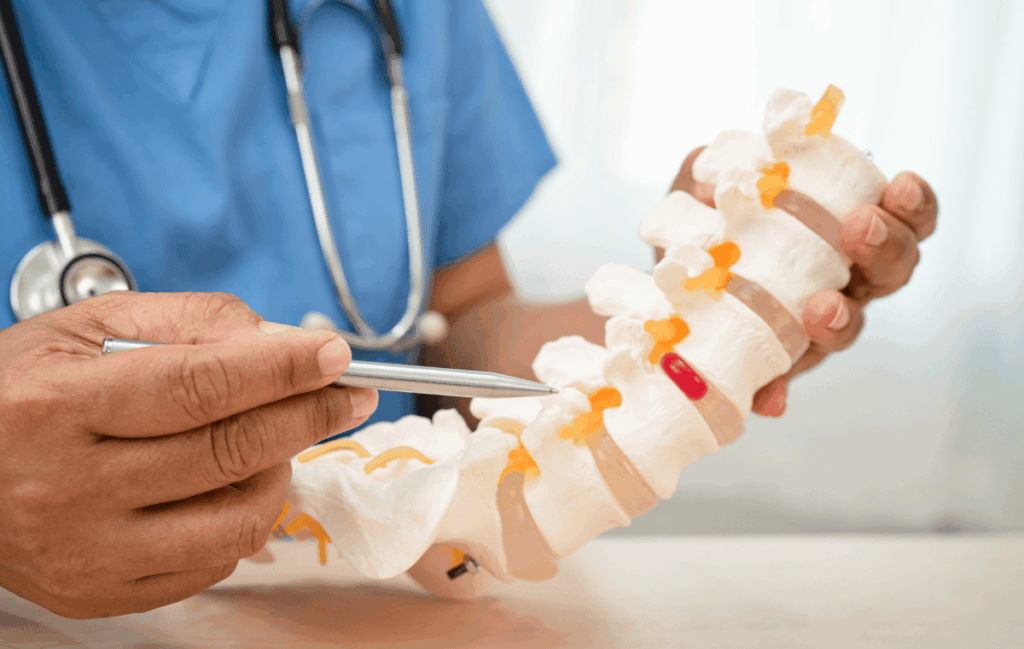
午前中は何ともなかったのに、午後になると腰がじわじわ痛くなる。
この「午後腰痛」は、単なる疲れや加齢ではなく、座り方と姿勢の崩れが引き起こす構造的な現象です。
長時間のデスクワークでは、身体のバランスが少しずつ崩れ、「止まる姿勢」に変化していきます。
その結果、骨盤や背骨の動きがなくなり、血流や呼吸が滞る。これが午後に痛みが現れる根本的な理由です。
座りすぎによる骨盤の傾きと腰椎への圧迫
人間の骨盤は、わずかな角度の変化で腰への負担が大きく変わります。
理想的な姿勢では、骨盤はまっすぐ立ち、背骨は自然なS字カーブを描いています。
ところが、長時間座っていると骨盤が後ろに倒れ(=骨盤後傾)、その上にある腰椎が押しつぶされるような状態になります。
この「骨盤後傾」が続くことで、腰の筋肉(脊柱起立筋や多裂筋)が硬くなり、腰椎の関節や椎間板に圧が集中。
結果として、午後になる頃には「重だるさ」や「鈍い痛み」を感じるようになります。
平井塾では、こうした骨盤の動きの停止を「構造のロック」と呼びます。
骨盤が動かなくなると、腰も動けなくなり、痛みが始まります。
姿勢の崩れが腰の血流を止めるメカニズム
腰痛の背景には、血流の停滞があります。
座り姿勢では、太ももの裏やお尻が圧迫され、骨盤周囲の静脈やリンパが流れにくくなります。
さらに、猫背姿勢になると背中の筋膜が張り、腰から背中へと伸びる血管の通り道が狭くなります。
これが午後のだるさや重さの正体です。
血液の流れが悪くなると、筋肉に酸素や栄養が届かず、老廃物が滞ることで痛み物質(ブラジキニン、ヒスタミンなど)が蓄積します。この化学的反応が、「午後になると痛くなる」原因のひとつなのです。
腰痛を治すカギは「流れ」。
血液・リンパ・呼吸が流れると、痛みは自然に引いていきます。
午後特有の「姿勢疲労」と呼吸の浅さ
デスクワークが長引く午後は、集中状態が続き、無意識のうちに呼吸が浅く、早くなります。
この浅い呼吸は、腰への負担をさらに増やします。
呼吸が浅いと、横隔膜(呼吸筋)と骨盤底筋の動きが止まり、腹圧(体幹を支える内圧)が下がります。
その結果、背骨や腰椎が自分の体重を支えきれず、筋肉が代わりに無理をしてしまうのです。
特に、午後の疲れた時間帯には
- 腰を支える力が弱まり
- 呼吸が浅くなり
- 血流が滞る
という「三重の姿勢疲労」が起こります。
集中とストレスが引き起こす無意識の緊張
午後の仕事は、会議・納期・タスク処理など、頭を使う時間が多く、精神的な緊張が続きます。
このとき、身体の中では交感神経が優位になり、筋肉が「戦う準備」をして固くなります。
とくに背中や腰の筋肉は、ストレスの影響を受けやすい部位。
緊張状態が続くと、腰が常に張ったままになります。
平井塾では、この状態を「心の姿勢疲労」と呼びます。
身体の姿勢が崩れる前に、心の緊張が先に姿勢の流れを止めているのです。
だからこそ、午後の腰痛には「姿勢+呼吸+心のリズム」のケアが必要。
その全てを一体として整えるのが、平井塾の姿勢循環という考え方です。
デスクワーク中に崩れる姿勢の原因

「最初はいい姿勢で座っていたのに、午後になると猫背になっている…」
「気づいたら片方に体重をかけて座っている」
デスクワークの腰痛の多くは、気づかないうちに崩れていく姿勢が原因です。
しかも、その崩れ方には一定のパターンがあります。
身体は常に「楽な方向」に逃げようとする性質があり、長時間の座位では、知らず知らずのうちに構造が偏っていくのです。
骨盤後傾と猫背の連鎖反応
最も多い姿勢の崩れが、「骨盤後傾からの猫背姿勢」です。
座る時間が長くなると、骨盤が後ろに倒れ、腰の自然なカーブ(前弯)が失われていきます。
すると、背骨全体が丸まり、肩が前に出て、最終的には頭が前に突き出るという連鎖が起こります。
この姿勢では、背骨全体が「前へ倒れる力」に逆らうため、腰の筋肉(脊柱起立筋・多裂筋)が常に緊張した状態になります。
この頑張り続ける筋肉こそが、午後の腰痛の元凶です。
平井塾では、骨盤の傾きを「姿勢循環の起点」と考えます。
骨盤が立てば、背骨も呼吸も流れ出す。骨盤が倒れれば、すべてが止まる。
反り腰姿勢と腰への負担
逆に、「良い姿勢を意識しすぎる人」に多いのが反り腰型の姿勢です。
「背筋を伸ばそう」「猫背にならないようにしよう」と意識するあまり、腰を反らせて胸を張る姿勢を取ってしまうケースです。
一見正しく見えますが、腰椎の関節を過度に圧迫し、腰の筋肉が常に縮んだ状態になるため、午後には「張り」「鈍痛」「だるさ」を感じるようになります。
この頑張る姿勢は、呼吸も浅くし、結果的に「疲れる姿勢」になってしまうのです。
モニター位置・椅子の高さ・足の位置の影響
姿勢の崩れは、身体だけでなく環境要因にも大きく左右されます。
- モニターが低い:頭が前に出て首と腰に負担
- 椅子が高い:足が浮き、骨盤が後傾
- 机が高い:肩が上がり、背中が緊張
- 足を組む癖:骨盤の左右差が固定化
つまり、環境が身体を歪ませているケースが多いのです。
いくら姿勢を意識しても、椅子や机の高さが合っていなければ、午後には自然と崩れてしまいます。
理想は、
- 肘が机とほぼ水平
- 目線がモニターの上端と同じ高さ
- 足裏がしっかり床につく
この3点。
これだけでも、骨盤の安定が全く違います。
環境を変えることは、身体の使い方を変えること。
良い姿勢は、正しい環境の中で自然に育ちます。
「姿勢を正そうとすること」が逆効果になる理由
「姿勢を正せば腰痛が治る」と思い、背筋を伸ばして頑張っている方も少なくありません。
しかし、それがかえって午後の腰痛を悪化させることもあります。
なぜなら、「正そう」と意識するほど筋肉が固まり、流れない姿勢になるからです。
平井塾では、姿勢を正すのではなく、姿勢を流れさせることを大切にしています。
- 骨盤が呼吸でわずかに動く
- 背骨が波のようにしなやかに動く
- 肩と腰がバランスよく揺らぐ
この「動的安定」こそが、本当の意味での良い姿勢です。
良い姿勢とは、静止ではなく循環。それは、「止まらない姿勢」です。
午後の腰痛を軽減する正しい座り方

午後の腰痛は、「座っている時間」と「止まった姿勢」に比例して起こります。
つまり、座り方を変えるだけで、午後の腰痛は防げるのです。
ただし、ここで大切なのは「良い姿勢を保つ」ことではなく、呼吸が通る座り方を身につけること。
身体を正すのではなく、自然に整う方向へ導く、これが、平井塾の姿勢循環の考え方です。
骨盤を立てて座るニュートラルポジション
腰に負担の少ない座り方の基本は、骨盤を立てること。
椅子に浅めに腰をかけ、坐骨(お尻の下の左右の骨)が座面にしっかり当たるように座ります。
背中は無理に伸ばさず、骨盤をまっすぐに立てるだけでOKです。
このときの感覚は、「腰で座る」のではなく、「骨盤の上に身体を乗せる」イメージ。
そうすることで、背骨が自然なカーブを描き、腰の筋肉がリラックスした状態になります。
骨盤を立てることは、「身体の軸を起こす」ということ。
軸が整えば、重力も呼吸も自然に流れ始めます。
腰に優しい椅子・クッションの選び方
どんなに意識しても、椅子が合っていなければ良い姿勢は保てません。
座面が硬すぎたり、背もたれが深すぎる椅子は、骨盤後傾を招きます。
理想は、
- 座面が少し前傾している椅子(骨盤が自然に立つ)
- お尻が沈みすぎないクッション
- 背もたれは浅く、腰を軽く支える程度
もし一般的なオフィスチェアを使う場合は、骨盤サポートクッションなどを併用すると効果的です。
良い椅子とは、座らせる椅子ではなく、座りやすくする椅子。
道具は、姿勢を正すためでなく、流れを支えるために使いましょう。
1時間に1回の「姿勢リセット」のすすめ
午後の腰痛を防ぐ最大のコツは、動くことです。
良い姿勢を1日中保つことは不可能です。
だからこそ、定期的に「姿勢をリセットする時間」をつくりましょう。
おすすめは、1時間に1回、次のような簡単な動き
- 椅子から立ち上がって伸びをする(10秒)
- 肩をゆっくり後ろに回す(3回)
- その場でかかと上げ(10回)
このわずかな動きが、骨盤と背骨を再び動かし、血流を回復させます。
「動き続ける姿勢」こそが、午後の腰痛を防ぐ最も自然な方法です。
姿勢を維持するのではなく、更新する。小さな動きが、午後の腰痛をリセットします。
お腹と背中をつなぐ呼吸の座り方
座り姿勢で最も見落とされがちなのが「呼吸」です。
呼吸は姿勢のバランスを整える内側の動き。呼吸が止まると、姿勢も止まります。
座ったままでもできる簡単な呼吸法を紹介します。
- 骨盤を立てて、背骨をやや伸ばす
- 鼻からゆっくり息を吸い、お腹を膨らませる
- 口を軽く開き、ふぅっと息を吐きながら肩の力を抜く
- 背中が膨らむように呼吸する
この呼吸を数回繰り返すだけで、腰周りの筋肉がゆるみ、背骨の動きが滑らかになります。
平井塾では、「呼吸が通る姿勢=流れる姿勢」と教えています。
息を深くするだけで、姿勢も血流も整い始めるのです。
午後の腰痛は、「良い姿勢ができていない」のではなく、「身体が動いていない」ことから起こります。
座り方を止まる姿勢から流れる姿勢に変えることで、午後特有の腰の重さや痛みは驚くほど軽くなります。
姿勢循環の視点で見る午後の腰痛対策

午後の腰痛は、単なる「座りすぎ」や「筋肉疲労」ではなく、身体の流れが止まっている状態です。
座ることで骨盤が固定され、背骨の動きが止まり、呼吸と血流の循環が乱れる。
この「構造の停止」こそが、午後に腰が痛くなる根本原因です。
平井塾では、この現象を「姿勢循環の乱れ」と呼び、身体を形ではなく流れとして整えるアプローチを取ります。
FJAで整える細部のエラーとは
FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)は、平井塾が独自に体系化した、筋膜(ファシア)と関節の微細な調整法です。
デスクワークによって、骨盤・腰椎・肋骨などの関節は、わずか数ミリ単位で動きが滞ります。
これを力で押したり、ストレッチで伸ばそうとすると、一時的には楽になっても、すぐに戻ってしまいます。
FJAでは、施術者が手で聴くように身体を観察し、その部位が「どちらへ動きたがっているか」を感じ取り、わずかな誘導で流れを再起動させます。
押すのではなく、動きたい方向を見守る。身体は気づけば、自ら戻っていく力を持っています。
こうして、骨盤・背骨・筋膜・神経が再び滑らかに連動を始めると、止まっていた血流と呼吸も同時に回復し、午後の腰の重さが自然に抜けていきます。
姿勢循環整体で呼吸と骨盤をリンクさせる
FJAで局所の動きを整えたあとは、姿勢循環整体で全身のリズムを統合していきます。
姿勢循環整体は、「骨盤―背骨―胸郭―頭蓋」という身体の主要ユニットを、呼吸の流れに合わせて調整する整体法です。
午後の腰痛のように、呼吸が浅く、身体が止まっている状態では、このユニットがバラバラに動き、姿勢全体の連動が崩れています。
施術では、患者さんの呼吸のリズムに合わせて関節や筋膜の微細な動きを整え、呼吸と骨盤の動きを再びリンクさせるのが目的です。
呼吸は、姿勢の指揮者です。呼吸が通れば、骨盤も背骨も動き出します。
この「呼吸の循環」が回復すると、午後になると出ていた腰痛が軽くなるだけでなく、背中が軽くなり、呼吸が深く、気持ちまで落ち着く。そんな全身の再起動が起こります。
「押さない・戻さない」ことで流れを取り戻す
一般的な施術では、「硬いところを押す」「歪みを戻す」ことが主流です。
しかし、平井塾ではそれを行いません。
なぜなら、身体の歪みや硬さは原因ではなく結果だからです。
それを無理に戻そうとすると、身体は一瞬で防御反応を起こし、さらに深い部分の緊張を強めてしまいます。
平井塾の施術哲学は、
「身体を変えるのではなく、身体が変わる環境をつくる」。
押さない、戻さない、無理をしない、この待つ姿勢こそが、身体の自然な治癒力を引き出す最短ルートです。
流れる姿勢を保つ3つの意識
午後の腰痛を予防・改善するために、平井塾では次の3つの意識を日常に取り入れることをすすめています。
- 止まらない姿勢を意識する
長く座るときほど、「動いていい姿勢」でいること。 - 呼吸を通す
息を吸うたびに背骨が広がる感覚を持つと、姿勢が自然に整います。 - 支えではなく流れで立つ
筋肉で支えるのではなく、骨盤と背骨の軸で支える。
この3つを意識するだけで、午後の腰痛だけでなく、肩こりや倦怠感までもが軽くなっていきます。
良い姿勢とは、「形」ではなく「流れ」。止まらない身体が、痛まない身体をつくります。
午後の腰痛を解消するカギは、「押すこと」でも「矯正すること」でもなく、流れを戻すことにあります。
FJAと姿勢循環整体の考え方は、身体に治る力を思い出させるためのアプローチです。
午後の腰痛を予防する生活習慣

午後になると腰が重くなる。それは、身体が「流れを止めないで」と訴えているサインです。
整体やストレッチも大切ですが、本当に腰痛を防ぐのは、日々の生活の使い方です。
平井塾の考え方では、身体は「動けば整い、止まれば崩れる」構造をしています。
つまり、流れる生活こそ最高の整体なのです。
デスクワーク中にできるミニストレッチ
腰痛を防ぐには、「止まらない姿勢」が基本。とはいえ、仕事中に大きく動くのは難しいものです。
そこでおすすめなのが、座ったままできる流れのストレッチ。
1. 骨盤ゆらしストレッチ(30秒)
椅子に座ったまま、骨盤を前後にゆっくりゆらします。
腰の筋肉がほぐれ、背骨の動きが戻ります。
2. 肩甲骨まわし(20秒)
肩を大きく後ろに回し、呼吸を整えます。
血流が上半身に広がり、姿勢がリセットされます。
3. 深呼吸リリース(3呼吸)
鼻から吸い、口から吐く。そのとき腰がふっと緩む感覚を大切に。
これを1時間に1回行うだけで、午後の腰痛は驚くほど軽減します。
「時間を作って動く」のではなく、「動く時間を作らない」。小さな流れが、痛みを止める最大の薬です。
水分・呼吸・休息をバランスよく取る
腰痛対策というと、ストレッチや筋トレを思い浮かべる人が多いですが、体内の循環を助ける習慣も同じくらい大切です。
- 水分:1時間にコップ半分を意識的に。血液の粘度を下げるだけで腰のだるさが軽減。
- 呼吸:デスクワーク中も「息を止めていないか?」をチェック。
- 休息:5分の休憩を呼吸の時間に変えることで、自律神経が安定します。
身体は「酸素」「水」「リズム」で動いています。
午後の腰痛を予防するには、流れの素材を補うことが何より重要です。
身体を整えるのは運動だけではありません。「呼吸と水分」も立派な整体です。
朝・昼・夜の姿勢リズムを整える
腰痛を起こさない人は、1日の中で姿勢のリズムを上手に切り替えています。
平井塾では、「姿勢も呼吸も一日のリズムに従う」と考えています。
- 朝:骨盤と背骨を起こすストレッチ(流れのスイッチを入れる時間)
- 昼:デスクワーク中に姿勢リセット(流れを保つ時間)
- 夜:深呼吸と軽い伸び(流れを戻す時間)
このリズムを意識するだけで、身体の循環システムが自動的に整い、
「午後だけ痛い腰」が「一日中軽い腰」に変わっていきます。
姿勢は1日で作られるのではなく、1日の流れの中で育つ。リズムを整えれば、自然に姿勢も整います。
平井塾がすすめる「姿勢を整える1日の流れ」
以下は、平井塾が提案する姿勢循環を保つ生活モデルです。
腰痛予防だけでなく、肩こり・疲労感・集中力低下にも効果的です。
| 時間帯 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 朝(起床後) | 深呼吸+骨盤立ちストレッチ(2分) | 呼吸で骨盤を起こす |
| 午前中 | 姿勢意識チェック(30分ごと) | 止まらない姿勢を維持 |
| 昼休み | 軽いウォーキング or 骨盤ゆらし | 血流をリセット |
| 午後 | 1時間に1回のリフレッシュ動作 | 腰への圧を軽減 |
| 夜 | 深い呼吸と温浴で緊張を解放 | 一日の“流れ”を整える |
このように、「姿勢を作る」のではなく「流れを回す」ことを意識することで、
午後の腰痛だけでなく、全身の疲労感やストレスも減少します。
まとめ──午後の腰痛を防ぐ流れる身体のつくり方

午後になると出てくる腰の重さや痛み。
それは、あなたの身体が「もう少し流れを戻して」と伝えているサインです。
多くの人が姿勢が悪いから痛いと思いがちですが、本当の原因は、座りっぱなしによって身体の流れが止まってしまうことにあります。
午後の腰痛をつくる3つの要因
- 骨盤の傾き(構造の停止)
長時間座ることで骨盤が後ろに倒れ、背骨の動きが止まる。 - 呼吸の浅さ(機能の低下)
集中するほど呼吸が浅くなり、身体を内側から支える力が弱まる。 - 血流の滞り(循環の乱れ)
筋肉や神経に酸素が届かず、午後になると痛みやだるさが強くなる。
この3つが重なると、身体の姿勢循環が乱れ、午後特有の腰痛が現れるのです。
「正す姿勢」から「流れる姿勢」へ
平井塾では、姿勢を「形」としてではなく、呼吸と血流を含めた流れの構造として捉えます。
だからこそ、
「背筋を伸ばす」よりも「呼吸を通す」、「止める姿勢」よりも「動ける姿勢」を大切にします。
良い姿勢とは、静止ではなく循環。動きながら安定している姿勢こそが、流れる身体の証です。
日常生活でできる午後腰痛予防の3原則
- 30分に一度、姿勢を変える
椅子から立ち上がる、伸びをする、肩を回す──それだけでOK。 - 呼吸を意識する
お腹や背中に呼吸を通すことで、腰の圧が自然に抜けていきます。 - 骨盤を立てて座る
坐骨で座る感覚を持つと、背骨が自然なS字を保ち、腰が疲れません。
この3つを日常に取り入れるだけで、午後の腰痛は確実に軽くなっていきます。
平井塾の考える流れる身体とは
平井塾の「FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)」と「姿勢循環整体」は、
単なる整体技術ではありません。
それは、
- 身体が本来持つ治る力を思い出させる哲学であり、
- 施術者と患者が呼吸を合わせる体験であり、
- 力で押すのではなく、流れを聴く技術です。
午後の腰痛を繰り返す人ほど、身体が止まっている時間を長く持っています。
その時間を流れる時間に変えるだけで、身体は必ず変わります。
「身体を変える」のではなく、「流れを戻す」。
平井塾の姿勢循環の本質は、そこにあります。
午後の腰痛は「流れを取り戻す合図」
午後になると腰が痛くなるのは、あなたの身体が「もう少し呼吸して」「もう少し動いて」と教えてくれているだけ。
無理に矯正する必要はありません。
止まった姿勢を動かし、呼吸を通し、流れを思い出すだけで、痛みは自然と静まっていきます。
腰痛を治すのは、あなたの中の流れ。
午後の小さな違和感を、流れる身体への第一歩に。
このように、午後の腰痛を防ぐためには、姿勢を「正すもの」ではなく、「流すもの」として捉えることが大切です。
平井塾では、構造思考にもとづいたFJAと姿勢循環整体を通して、
身体の自然な流れを取り戻すサポートをしています。
▼関連する記事もあわせてご覧ください
- 「長時間のデスクワークで坐骨神経痛が悪化する…」そんな方へ。
痛みの原因と正しい座り方を詳しく解説しています。
→ 坐骨神経痛は「座りすぎ」が原因?デスクワーカーが知るべき正しい座り方 - 「午後になると腰が重い」「姿勢が傾く気がする」方は要チェック。
骨盤の歪みとデスクワーク姿勢の関係を詳しく解説しています。
→ 骨盤の歪みはなぜ起こる?デスクワークで崩れた姿勢を整える方法 - 「この痛み、腰痛?それとも坐骨神経痛?」
症状の違いや、見分け方のポイントをわかりやすく紹介しています。
→ 腰痛と坐骨神経痛の違いとは?間違えやすい痛みの見分け方 - 姿勢と血流は切っても切れない関係。
猫背・反り腰・肩こり・冷えなど、全身の“循環不良”のメカニズムを解説します。
→ 姿勢が崩れると血流も悪くなる?不調と姿勢の関係とメカニズム - 「座りすぎ」は腰だけでなく、全身に影響を与えます。
腰痛・肩こり・むくみを引き起こす共通の“循環の乱れ”を詳しく解説。
→ 座りすぎがもたらす全身の不調:腰痛・肩こり・むくみの共通原因とは?
【投稿者情報】平井 大樹

平井塾 代表。みゅう整骨院 代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。
「患者様の人生に、健康の安心を。」
私は、これまで20年間、延べ10万人を超える患者様と向き合ってきました。その中で最も大切にしてきたのは、「痛みを取る」ことだけではなく、「患者様が心から安心して過ごせる毎日をサポートする」ことです。
- 長期にわたる信頼:私は、5年以上通われる方が211名。その中で10年以上通われる方も93名いらっしゃいます。これは、一時的な改善ではなく、患者様が私に一生の健康を任せてくださっている証です。
- 根本的なアプローチ:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)という独自の手技で、痛みの箇所だけでなく、その根本原因である身体全体の歪みや動きの不調にアプローチします。
- 予約が取れない理由:広告を一切使わず、患者様のご紹介だけで新規予約は5年以上待ちの状態です。現在、お取りする予定はありません。
このコラムが、あなたの不調を改善し、より豊かな毎日を送るための一歩となれば幸いです。