目次
左手のしびれの概要

左手にしびれを感じると、多くの方が「血行が悪いだけかな」「一時的な疲れかな」と軽く考えがちです。しかし、実際にはその裏に神経や血管のトラブル、さらには内科的な疾患が隠れていることもあります。ここではまず、「左手のしびれ」がどういうものなのかを整理しましょう。
左手がしびれるとはどういうことか?
「しびれ」という感覚は、医学的には 異常感覚(パレストジア) と呼ばれます。神経の伝達がスムーズにいかないときに生じるもので、
- ピリピリする
- ビリビリ電気が走るように感じる
- 感覚が鈍くなる
といった表現で訴える方が多いです。
左手のしびれは、神経が圧迫されている場合だけでなく、血流が滞っている場合や、脳からの指令がうまく伝わらない場合にも起こります。
左手のしびれの一般的な症状
左手のしびれは次のような形で現れることがあります。
- 指先だけがしびれる
- 手のひら全体がビリビリする
- 腕から手首にかけて重だるい
- 動かしにくさや力が入りにくい
特に「左手」だけに出る場合、循環器系や脳の病気が関わっていることもあるため、注意が必要です。
左手のしびれが引き起こす感覚の違い
しびれといっても、その感じ方は人によって異なります。
- 神経性のしびれ:電気が走るような鋭い感覚
- 血流性のしびれ:冷たさや重だるさを伴う
- 中枢性のしびれ(脳梗塞など):感覚が失われるような違和感
このように、しびれの種類を見分けることが、原因を探る大きな手がかりになります。
左手のしびれとは?なぜ起こるのか

左手のしびれは、単なる「疲れ」や「一時的な血行不良」と片づけられがちですが、実際には身体の深い部分で起こっている異常のサインであることがあります。ここでは、しびれがどのように起こるのか、そのメカニズムを整理します。
しびれの仕組み(神経・血流の関与)
しびれは大きく分けて 神経の障害 と 血流の障害 によって生じます。
- 神経性のしびれ:末梢神経や脊髄、脳の異常によって「感覚の電気信号」がうまく伝わらない状態。ピリピリ、ビリビリといった感覚が特徴。
- 血流性のしびれ:血管が圧迫されたり、血流が滞ったときに酸素や栄養が不足して神経が一時的に反応する状態。冷感や重だるさを伴いやすい。
この2つはしばしば重なって起こるため、症状だけでの判断は難しいのが実情です。
左手にしびれが出やすい理由
左手のしびれは、右手に比べて注意が必要とされることがあります。
- 循環器系の関与:左腕は心臓から直接血液が流れるため、心疾患や大動脈のトラブルが症状に現れやすい。
- 姿勢や生活習慣:デスクワークでの猫背やスマホ操作の癖が、左肩・首周りに負担をかけやすい。
- 神経の走行:首や胸郭出口を通る神経が複雑に交差しており、圧迫が左手に出るケースが少なくない。
つまり「左手だけのしびれ」は、筋肉や神経の問題に限らず、心臓や脳に関連したサインである可能性もあるのです。
左手のしびれの主な原因

左手のしびれには、さまざまな原因が隠れています。筋肉や神経の圧迫によるものから、循環器・代謝疾患、さらには脳の病気まで幅広く考えられるため、症状の特徴を整理することが大切です。ここでは代表的な原因を解説します。
胸郭出口症候群によるしびれのメカニズム
胸郭出口症候群は、首の付け根から鎖骨・肋骨の間にある「胸郭出口」で神経や血管が圧迫されることで起こります。
- 腕を上げたり長時間同じ姿勢を取るとしびれが悪化
- 握力の低下や物を落としやすくなる
- 血流障害で手が冷たくなる、白くなることもある
特にデスクワークやスマホ操作の多い人に多く見られる原因です。
頚椎症がもたらす神経の圧迫としびれ
頚椎症は、加齢や姿勢不良によって首の骨(頚椎)が変形し、神経や脊髄が圧迫されて起こります。
- 首を動かすとしびれが悪化
- 肩や首の慢性的な痛みを伴う
- 進行すると歩行障害や排尿障害に発展することもある
首そのものに原因がある場合、左手のみにしびれが出ることもあります。
手根管症候群の影響とその症状
手根管症候群は、手首の中を通る正中神経が圧迫されることで起こります。
- 親指、人差し指、中指のしびれが中心
- 夜間や朝方に強いしびれが出やすい
- 進行すると親指の筋肉が痩せてくる
特にパソコン作業や手作業を繰り返す方に多く見られます。
脳卒中や脳梗塞による左手のしびれ
脳の血流が一時的に低下したり、血管が詰まると、突然のしびれや麻痺が起こります。
- 顔の片側や足と同時にしびれる
- 言葉が出にくい、ふらつきがある
- 急に発症するのが特徴
この場合は一刻も早い受診が必要で、救急搬送が推奨されます。
糖尿病と手のしびれの関係
糖尿病の方では、高血糖によって末梢神経が障害され、しびれが出やすくなります。
- 手足の先からじわじわ広がるようなしびれ
- 感覚が鈍くなり、熱さや痛みを感じにくくなる
- 進行すると日常生活に支障をきたす
この場合は血糖コントロールと合わせたケアが必要です。
胸郭出口症候群と左手のしびれ
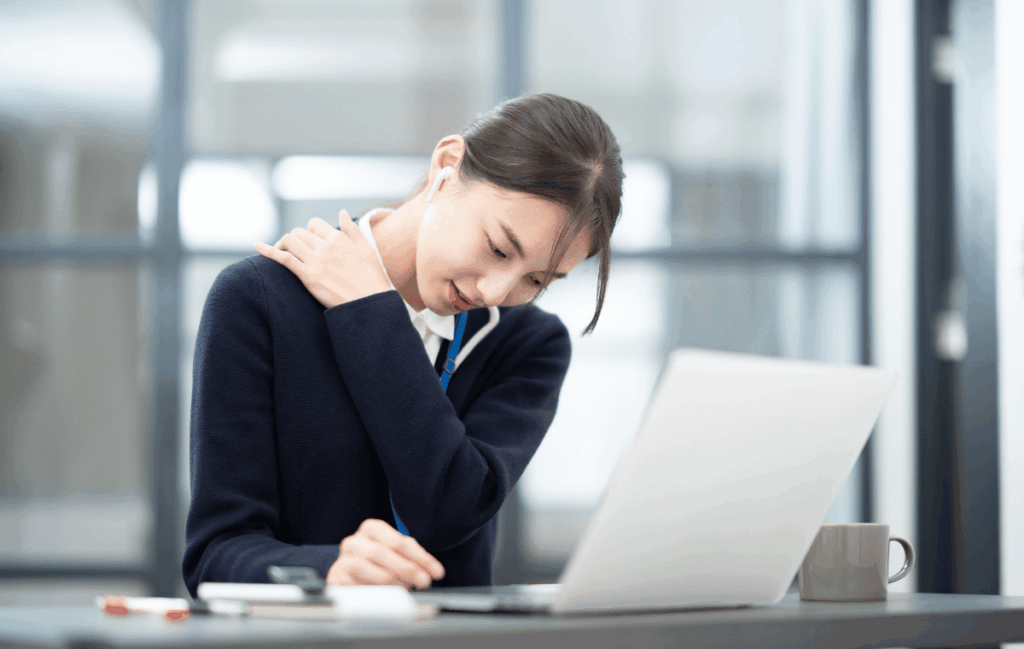
胸郭出口症候群は、首の付け根から鎖骨・肋骨の間にある「胸郭出口」という部分で神経や血管が圧迫されて起こる病気です。特にデスクワークやスマホ操作など、同じ姿勢を長時間続ける方に多くみられ、左手に症状が集中することもあります。
胸郭出口の構造と圧迫ポイント
胸郭出口には、腕へ向かう神経や血管が束となって通っています。
圧迫が起こりやすいポイントは以下の3つです。
- 斜角筋の間(首の筋肉のすき間での圧迫)
- 鎖骨と第1肋骨の間(骨格のずれや姿勢不良で狭くなる)
- 小胸筋の下(肩をすくめたり巻き肩になることで圧迫)
このいずれか、もしくは複数の部位で圧迫が起こると、神経や血管の流れが滞り、しびれにつながります。
左手に出やすい典型的な症状
胸郭出口症候群による左手のしびれは、次のような特徴があります。
- 腕を上げたり、荷物を持ったりするとしびれが強くなる
- 指先が冷たくなる、白くなる(血管圧迫による)
- 握力が低下し、ペットボトルのフタが開けにくくなる
- 首や肩の重だるさを伴う
特に左手に出る場合、デスクワークでモニターやマウスを左側に配置している、バッグを左肩にかけるなど、日常生活の癖が大きく関係することもあります。
日常生活で悪化しやすい姿勢や動作
胸郭出口症候群の症状は、姿勢や動作によって悪化することが多いです。
- 長時間の猫背姿勢
- スマホを見続ける下向き姿勢
- 片方の肩に荷物をかけ続ける
- 高い枕で寝る
これらの習慣は首や肩周囲の筋肉を硬くし、神経・血管の圧迫を強めます。
頚椎症と左手のしびれ

頚椎症は、首の骨(頚椎)の老化や変形によって神経や脊髄が圧迫される病気です。特に中高年に多くみられますが、最近ではスマホやパソコンによる「ストレートネック」などで若い世代にも増えています。左手にしびれが出る場合、頚椎から伸びる神経の一部が圧迫されている可能性があります。
頚椎の加齢変化と神経圧迫
頚椎は7つの骨で構成され、クッション役の椎間板や靱帯によって支えられています。加齢や姿勢不良によって次のような変化が起こります。
- 椎間板が薄くなり、神経の出口が狭くなる
- 骨のトゲ(骨棘)ができて神経を圧迫する
- 靱帯が厚くなり、脊髄を圧迫する
これらの変化によって、神経伝達が妨げられ、手のしびれや感覚の低下が生じます。
首の動きで悪化するしびれの特徴
頚椎症によるしびれは、首の動きで悪化しやすいのが特徴です。
- 上を向いたときに腕や手に電気が走るようなしびれが出る
- 長時間下を向いて作業するとしびれが強くなる
- 首を横に倒すと一側のしびれが悪化する
これは、動作によってさらに神経が圧迫されるために起こります。
胸郭出口症候群との見分け方
胸郭出口症候群と頚椎症は症状が似ていますが、次の点で見分ける手がかりがあります。
- 胸郭出口症候群:腕を上げたり荷物を持つと悪化。血流障害による冷感を伴いやすい。
- 頚椎症:首を動かすと悪化。慢性的な首や肩の痛みが伴いやすい。
ただし、両方が併発することも少なくないため、正確な診断には医師の診察と画像検査が欠かせません。
必ず注意したい前兆と症状

左手のしびれは、日常的な疲労や一時的な血行不良でも起こりますが、なかには重大な病気の前兆であることもあります。ここでは「見逃してはいけないサイン」を整理しておきましょう。
しびれの前兆に注意すべき理由
しびれは「体からのSOS」です。特に以下のような特徴がある場合は注意が必要です。
- 急に発症し、時間が経っても改善しない
- 顔や足にも同時にしびれが出ている
- しびれに加えて言葉が出にくい、ふらつくなどの症状がある
- 夜中や朝方に毎日のように繰り返す
こうした場合、脳梗塞や神経疾患の初期症状である可能性があります。
自分の症状を知るためのチェックリスト
セルフチェックの目安として、次のような質問に「はい」が多い場合は受診をおすすめします。
- 片手だけでなく、顔や足にも違和感がある
- 首を動かすとしびれが強まる
- 握力が落ちてきて、物をよく落とす
- 指先が冷たい・白くなることがある
- 数週間たっても症状が改善しない
このチェックは診断そのものではありませんが、受診の判断材料になります。
しびれの進行についての理解
しびれは放置すると進行することがあります。
- 最初は「ピリピリする」程度だったものが、徐々に「感覚が鈍い」「力が入らない」と悪化する
- 神経障害が長期間続くと、感覚が戻りにくくなることもある
- 糖尿病などの持病がある方は特に注意が必要
「そのうち治るだろう」と自己判断せず、早期に適切なケアを受けることが大切です。
左手のしびれに対する受診の重要性
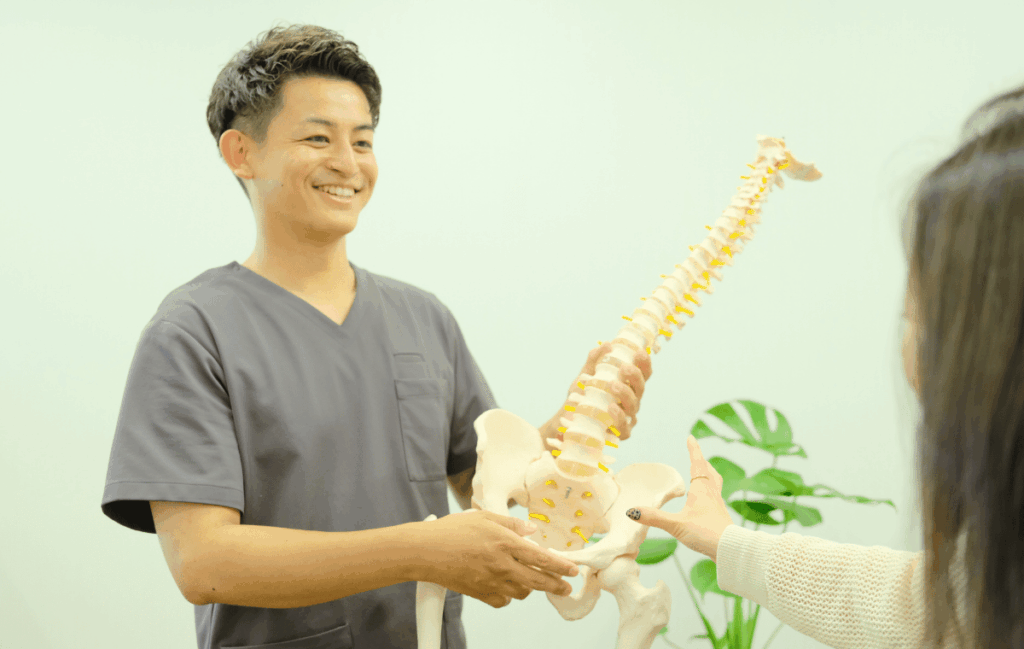
左手のしびれは、軽いものなら一時的な筋肉疲労や血流障害で済むこともあります。しかし、なかには命に関わる病気のサインである場合もあるため、適切なタイミングでの受診がとても大切です。
いつ受診すべきか?
次のような場合は、早めの医療機関受診をおすすめします。
- 数日~数週間続いているしびれが改善しない
- 首や肩の痛みが強く、日常生活に支障をきたしている
- 急に発症し、手だけでなく顔や足にも症状がある
- 握力低下や動かしにくさを伴っている
特に突然のしびれ+言語障害や歩行障害がある場合は、脳血管疾患の可能性があり救急受診が必要です。
医療機関での診察内容とは
整形外科や神経内科を受診すると、次のような流れで診察が行われます。
- 問診:症状の出方、発症時期、生活習慣の確認
- 神経学的検査:反射テスト、筋力・感覚の確認
- 画像検査:レントゲンで骨の変化を確認、MRIで神経や脊髄の状態を評価
これらを総合して、胸郭出口症候群や頚椎症、脳疾患などを鑑別します。
専門医による診断が必要な症例
次のようなケースでは、専門医による詳細な診断が重要です。
- 頚椎症が疑われるが手術の要否を判断する必要がある場合(脊椎外科医)
- 脳梗塞の可能性がある場合(神経内科・脳神経外科)
- 糖尿病や全身疾患に伴うしびれ(内科)
整体やセルフケアでは対応できないケースもあるため、受診の目安を知り、早めに専門家に相談することが安心につながります。
病院に行くべき危険なしびれ症状

左手のしびれは、多くの場合は整形外科や整体で対応できる範囲ですが、なかには 命に関わる重大な病気のサイン のことがあります。以下のような症状がある場合は、迷わず医療機関を受診してください。
心臓・脳疾患が疑われるケース
左手のしびれは、ときに心臓や脳の病気と関連して現れることがあります。
- 狭心症・心筋梗塞:胸の圧迫感や痛みとともに、左腕や左手にしびれが出ることがある
- 脳梗塞・脳出血:顔の片側や足のしびれ、言葉が出にくい、視覚異常を伴うことが多い
これらは時間との勝負であり、一刻も早い受診が回復の鍵となります。
進行性の筋力低下や感覚障害
次のような症状がある場合、神経が強く圧迫されている可能性があります。
- 握力が急激に低下する
- 箸やペンを持ちにくくなる
- 歩行がぎこちなくなり、ふらつく
放置すると神経のダメージが進み、回復が難しくなる恐れがあります。
受診の目安と専門科
- 胸の痛み+左手のしびれ → 心臓内科・循環器内科
- 突然の顔・手・足のしびれ → 神経内科・脳神経外科
- 首や肩の痛みと手のしびれ → 整形外科・脊椎外科
自己判断で様子を見るのではなく、「いつもと違う」「急に出てきた」症状はすぐに受診することが安心につながります。
左手のしびれの治療法

左手のしびれの治療は、原因によって大きく異なります。神経の圧迫なのか、血流の問題なのか、あるいは全身疾患なのかを見極めた上で、保存療法・リハビリ・生活改善・手術などが選択されます。
薬物療法とその効果
医療機関では、症状を和らげるために次のような薬が用いられます。
- 消炎鎮痛薬(NSAIDs):炎症や痛みを抑える
- ビタミンB12製剤:末梢神経の修復をサポート
- 血流改善薬:血液循環を促し、しびれを軽減
薬は対症療法であり、原因そのものを取り除くわけではありませんが、日常生活を送りやすくする効果があります。
リハビリとストレッチの具体的な方法
リハビリやストレッチは、しびれの改善と再発予防に欠かせません。
- 首や肩のストレッチ:胸を開く、肩甲骨を動かす
- 神経モビライゼーション:神経の動きを改善する軽い運動療法
- 体幹の安定トレーニング:姿勢を支える筋肉を鍛える
適切な運動は神経の圧迫を和らげ、血流を改善する効果があります。
手術が必要な場合の判断基準
保存療法を行っても改善せず、次のような状態がある場合は手術が検討されます。
- 強いしびれや痛みが数か月以上続いている
- 筋力低下が進み、日常生活に大きな支障がある
- 脊髄が強く圧迫され、歩行障害や排尿障害が出ている
胸郭出口症候群では肋骨や筋肉を切除する手術、頚椎症では椎弓形成術や椎間板摘出術が行われます。ただし手術後もリハビリは不可欠です。
日常生活での改善策と予防法
- デスクワークでは1時間に1度は肩を回す
- スマホは目の高さに持ち、うつむき姿勢を避ける
- 枕の高さを調整して首に負担をかけない
- 適度な運動(ウォーキングやストレッチ)を習慣にする
これらの習慣改善は、再発防止に大きな効果があります。
整体で改善できる左手のしびれ

薬や手術に頼る前に、整体によってしびれが改善するケースは少なくありません。特に胸郭出口症候群や頚椎症が関与するしびれは、体のバランスを整えることで神経や血管の圧迫を和らげられる可能性があります。
FJAで細部のエラーを見極める
平井塾が提唱する FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ) は、筋膜・関節・神経系のわずかな異常を丁寧に観察し、原因となる「細部のエラー」を修正する手技です。
- 痛みのある部位を無理に押さず、原因の連鎖を探る
- 力任せではなく「手で聴く」ような施術
- 施術者自身の臨床思考を育てる
このアプローチによって、これまで見落とされていた微細な原因を解消し、しびれの改善につなげます。
姿勢循環整体で全身のバランスと循環を整える
FJAで細部を整えたあとは、姿勢循環整体で全身の循環を改善します。
- 骨格のバランスを正し、首や肩にかかるストレスを減らす
- 血流・リンパの流れを促し、神経の働きを助ける
- ルーティン化された施術により安定した効果を得られる
「部分治療」ではなく「全身の治癒力」を引き出すことが目的です。
セルフケア・ストレッチの取り入れ方
整体だけに頼らず、日常生活にセルフケアを組み込むことが大切です。
- 胸を開くストレッチで猫背を防ぐ
- 肩甲骨を動かす体操で肩・首の緊張を和らげる
- 首に負担をかけない姿勢を意識する
整体とセルフケアを組み合わせることで、再発しにくい体づくりが可能になります。
生活習慣と左手のしびれの関連

左手のしびれは、病気だけでなく日常生活の習慣によっても悪化します。特にデスクワークやスマホの長時間使用など、現代的な生活スタイルが大きな要因となっています。ここでは生活習慣としびれの関係を整理しましょう。
ストレスの影響と対処法
精神的ストレスは筋肉を緊張させ、自律神経のバランスを乱すことで血流を悪化させます。その結果、しびれが強く出ることがあります。
- 呼吸を深く意識してリラックスする
- 睡眠の質を整える
- 軽い運動や趣味で気分転換を図る
ストレス対策は、しびれ改善に直結する重要なポイントです。
良い姿勢の維持とその効果
姿勢の乱れは首や肩に負担をかけ、胸郭出口や頚椎を圧迫します。
- デスクワークでは背筋を伸ばし、肘を支えて作業する
- スマホは目の高さに持ち、下を向く時間を減らす
- 枕の高さを調整し、首の自然なカーブを守る
良い姿勢を維持するだけで、神経や血管の圧迫が減り、しびれが軽減することがあります。
運動不足が招くしびれのリスク
長時間の座り仕事や運動不足は、血流を悪化させ、筋肉を硬直させます。
- 1時間ごとに立ち上がり、肩や腕を回す
- 軽いウォーキングで全身の血流を促す
- ストレッチで柔軟性を保つ
定期的な運動習慣は、しびれ予防にとても有効です。
左手のしびれのテクニカルな視点

左手のしびれを理解するためには、「神経」「血流」「末梢神経障害」という専門的な観点も欠かせません。ここでは、少し踏み込んだテクニカルな視点から解説します。
神経の仕組みとしびれの関係
神経は「電気信号のケーブル」のような役割を果たし、脳から手へ運動の指令を送り、手から脳へ感覚を伝えています。
- 神経が圧迫される → 電気信号が乱れ、ピリピリ感や感覚の鈍さが出る
- 長期間障害が続く → 神経そのものがダメージを受け、回復が難しくなる
神経が正常に働くためには、構造(圧迫がないこと)と栄養(血流が良いこと)が両立する必要があります。
血行不良が及ぼす影響
血管が圧迫されると、酸素や栄養が神経に届かなくなります。
- 一時的な圧迫 → 手が冷たくなり、ジンジンする
- 慢性的な圧迫 → 神経が弱り、しびれが続く
特に胸郭出口症候群では「血流性のしびれ」が起こりやすく、指先が白くなる、冷えるといった症状が特徴です。
末梢神経障害についての解説
末梢神経障害は、脳や脊髄から枝分かれした神経が障害を受ける状態です。
- 糖尿病性神経障害
- ビタミン不足による神経障害
- アルコールや薬剤の影響
これらは左手だけでなく、両手や足にもしびれが広がることがあり、全身疾患の一部として現れるケースもあります。
おわりに:左手のしびれを軽視しないために

左手のしびれは、「よくある症状だから大丈夫」と思って放置されがちです。しかし、その背後には神経や血流のトラブル、さらには心臓や脳の病気が隠れている場合もあります。大切なのは、症状を軽く見ず、正しく理解し、必要なときに行動することです。
知識を持つことでできる予防
症状の原因や仕組みを知ることで、生活習慣の改善やセルフケアを積極的に取り入れられるようになります。
- 良い姿勢を意識する
- 運動習慣を身につける
- ストレスをため込まない
知識は「自分の体を守る力」となります。
異常があった場合に知っておくべきこと
- 急に出たしびれ → 脳や心臓の病気の可能性があるため救急受診
- 徐々に悪化するしびれ → 整形外科や神経内科での検査が必要
- 慢性的なしびれ → 整体やリハビリで改善できる可能性あり
症状のタイプを知っておくだけで、適切な判断につながります。
医師とのコミュニケーションの重要性
診察を受けるときは、
- いつから症状があるのか
- どの動作で悪化するのか
- 他にどんな症状を伴っているのか
を具体的に伝えることで、正確な診断につながります。医師や施術者と信頼関係を築くことは、安心して治療を受けるために欠かせません。
投稿者情報:平井 大樹

みゅう整骨院 代表。平井塾 代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。
「患者様の人生に、心からの安心を。」
私は、これまで20年間、延べ10万人を超える患者様と向き合ってきました。その中で最も大切にしてきたのは、「痛みを取る」ことだけではなく、「患者様が心から安心して過ごせる毎日を取り戻す」ことです。
- 長期にわたる信頼:みゅう整骨院には、5年以上通われる方が308名、10年以上通われる方も100名いらっしゃいます。これは、一時的な改善ではなく、患者様が私たちに一生の健康を任せてくださっている証です。
- 根本的なアプローチ:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)、姿勢循環整体という独自の手技で、痛みの箇所だけでなく、その根本原因である身体全体の歪みや動きの不調にアプローチします。
- 平井の予約が取れない理由:開業後、患者様の紹介がメインで予約が満員になりました。2020年以降、新規予約は5年待ちの状態です。現在、新規予約を取る予定はありませんが、みゅう整骨院または、平井塾受講生から同じ施術を受けることができます。
このコラムが、あなたの不調を改善し、より豊かな毎日を送るための一歩となれば幸いです。

