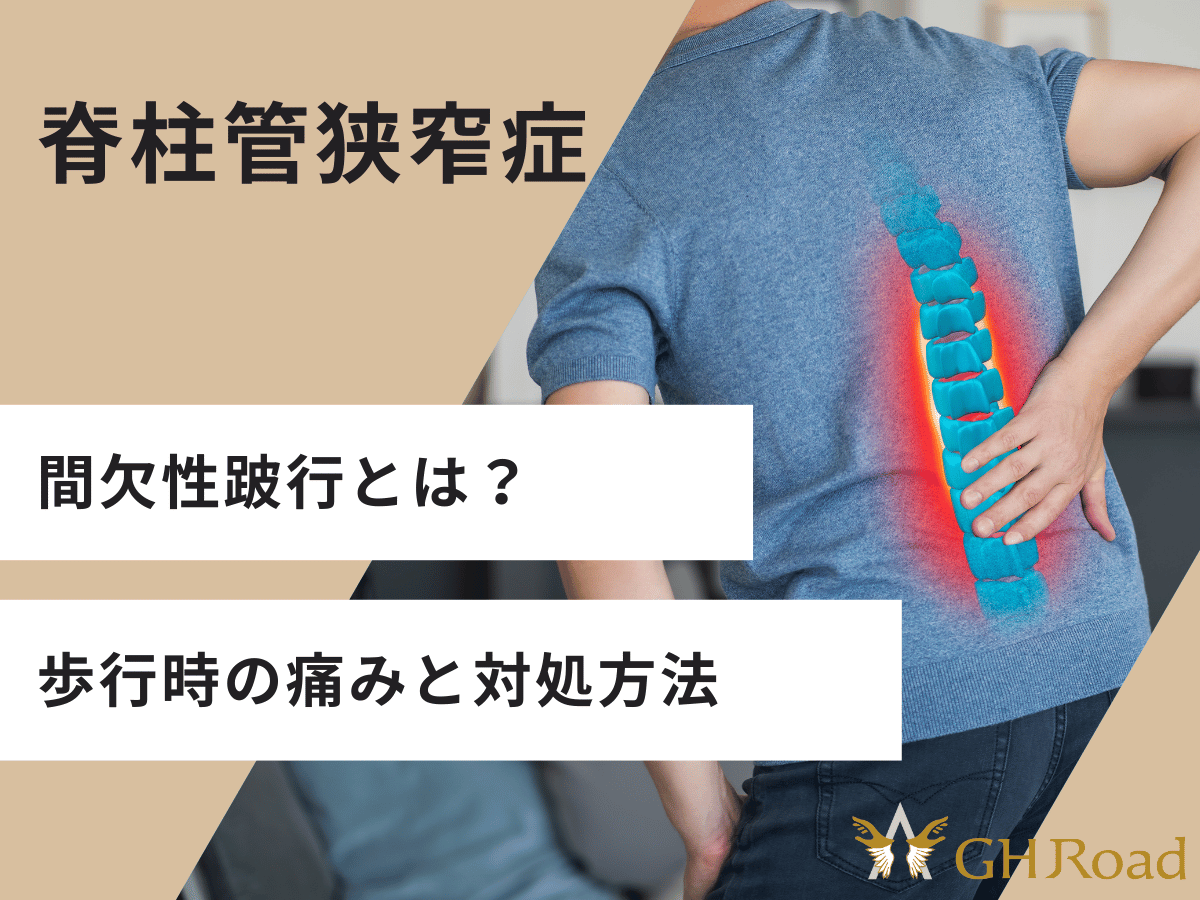「歩いていると腰や足がしびれて、少し休むとまた歩ける」
このような症状を経験している方は、間欠性跛行(かんけつせいはこう)かもしれません。
間欠性跛行は、脊柱管狭窄症に特徴的な症状のひとつであり、歩行中に痛みやしびれが出て休憩すると回復するというサイクルを繰り返します。この症状は「歳のせい」と思われがちですが、実際には神経や血流の問題が関与しており、放置すると生活の質を大きく下げてしまいます。
本記事では、
- 間欠性跛行の定義と症状
- 脊柱管狭窄症との関係と悪化要因
- 診断方法と受診のタイミング
- 保存療法・手術・整体などの改善法
- 日常生活での対策や運動習慣
- 平井塾が実践する「姿勢循環整体」によるアプローチ
について、専門的でありながら分かりやすく解説します。
20年以上の臨床経験と10万回を超える施術を通じて培った平井塾の知見から、「歩行時の痛みをどう軽減するか」「後悔しない治療選びをどうするか」をお伝えします。
目次
間欠性跛行とは?脊柱管狭窄症との関連性

間欠性跛行(かんけつせいはこう)は、一定の距離を歩くと腰や足に痛みやしびれが出て、休むと回復する症状を指します。脊柱管狭窄症に特徴的な症状の一つであり、病気を早期に発見する大きな手がかりとなります。
間欠性跛行の定義と症状
間欠性跛行は以下のような特徴を持ちます。
- 歩行中に腰や太もも、ふくらはぎに痛み・しびれが出る
- 数分間休むと症状が軽快し、再び歩けるようになる
- 長距離歩行が困難になり、生活の質が低下する
これらの症状は「ただの疲れ」や「加齢による衰え」と誤解されることもありますが、明確な医学的サインです。
脊柱管狭窄症のメカニズムと間欠性跛行の関係
脊柱管狭窄症では、背骨の中を通る「脊柱管」が狭くなり、神経や血管が圧迫されます。
- 歩行中 → 筋肉が働き、神経への圧迫が強まる
- 痛み・しびれが発生
- 休憩すると → 筋肉の負担が減り、一時的に血流が回復
このメカニズムによって、「歩くと痛い、休むと楽になる」という間欠性跛行の特徴的な症状が出ます。
間欠性跛行を引き起こすその他の疾患
間欠性跛行は脊柱管狭窄症だけでなく、以下の疾患でも見られます。
- 閉塞性動脈硬化症(PAD):動脈の血流障害による痛み
- 腰椎椎間板ヘルニア:神経の圧迫によるしびれ
- 糖尿病性ニューロパチー:神経障害による異常感覚
そのため、「間欠性跛行=脊柱管狭窄症」とは限らず、医療機関での正しい診断が必須です。
間欠性跛行は「歩行中の痛みと休憩での回復」がキーワード。脊柱管狭窄症の代表症状ですが、他の病気との区別も重要です。
脊柱管狭窄症における間欠性跛行の特徴

脊柱管狭窄症に伴う間欠性跛行は、他の疾患による跛行とは異なる特徴があります。ここでは、典型的な症状や生活への影響、悪化要因を整理します。
典型的な症状と痛みの特徴
- 歩き始めて数分〜数百メートルで腰や足にしびれや痛みが出る
- 前かがみになると症状が軽快しやすい(自転車は比較的楽に乗れる)
- 痛みよりもしびれや重だるさを強く感じることが多い
この「前かがみで楽になる」という特徴は、脊柱管狭窄症特有のサインです。
歩行時の異常とその影響
- 歩行距離が制限されるため、買い物や通勤、散歩が困難になる
- 長時間の外出を避けるようになり、活動量が減少
- 結果として、筋力低下や生活の質の低下につながる
間欠性跛行は単なる「歩行の問題」ではなく、社会生活全体に影響を及ぼす症状です。
間欠性跛行の悪化要因
症状を悪化させる要因には以下があります。
- 長時間の立位や歩行
- 姿勢不良(猫背や反り腰)による神経圧迫の増強
- 運動不足による筋力低下と血流悪化
- 寒冷による血管収縮
悪化を防ぐには、姿勢改善と血流促進が大切です。
脊柱管狭窄症の間欠性跛行は、「歩くと悪化、前かがみで軽快」という特徴があり、生活の質に直結します。放置せず、早めの対策が必要です。
診断方法:間欠性跛行の判別

間欠性跛行は脊柱管狭窄症の代表的な症状ですが、血管系の病気(閉塞性動脈硬化症など)や神経疾患でも起こり得ます。そのため、正確な診断がとても重要です。ここでは診断の流れを整理します。
医療機関での検査方法
- 問診:症状の出方、歩行距離、姿勢との関係を確認
- 身体診察:下肢の筋力や感覚の異常をチェック
- 歩行テスト:実際に歩いて症状の発現パターンを観察
症状の「出方の特徴」が、疾患を判別する大きな手がかりになります。
MRIやCTによる診断の役割
- MRI:脊柱管の狭窄具合や神経圧迫の程度を確認できる
- CT:骨の変形や靭帯の肥厚を評価するのに有効
特にMRIは、脊柱管狭窄症と他の疾患を見分けるうえで重要です。
初期症状の確認と受診のタイミング
以下の症状がある場合は、早めの受診が推奨されます。
- 歩くと足がしびれるが、休むと楽になる
- 前かがみで症状が軽減する
- 最近、歩ける距離が短くなってきた
早期に診断を受けることで、保存療法や整体など手術以外の選択肢を取れる可能性が高まります。
間欠性跛行は「脊柱管狭窄症の特徴的なサイン」ですが、他疾患の可能性もあります。必ず医療機関で検査を受け、正しい診断を得ることが大切です。
間欠性跛行に対する治療法
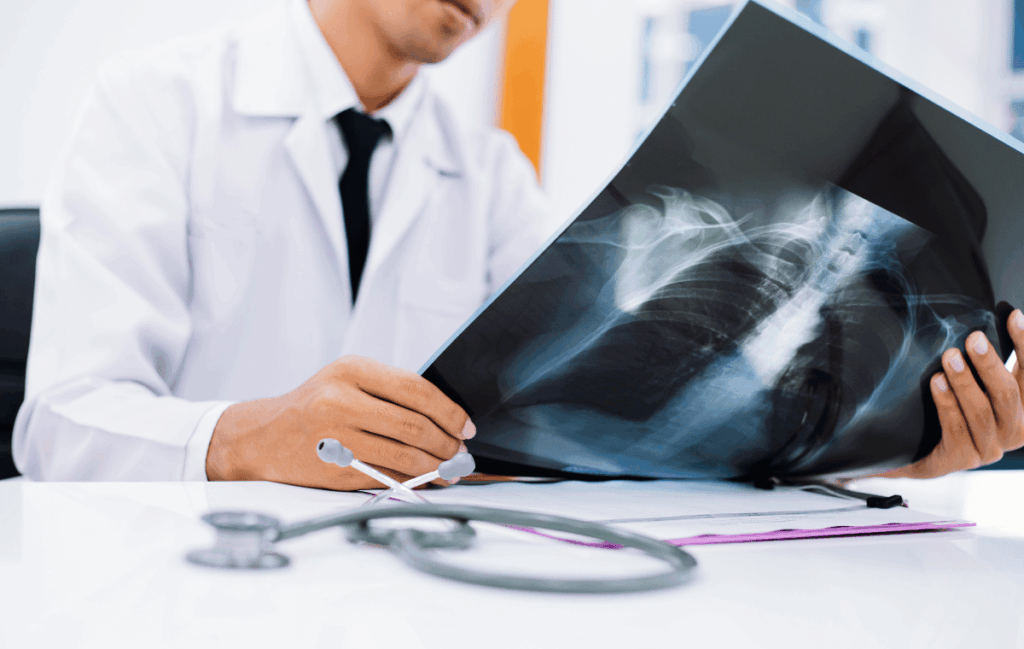
間欠性跛行は脊柱管狭窄症の代表的な症状ですが、治療法はひとつではありません。症状の程度や生活への影響度によって、保存療法から手術まで段階的に選択されます。
保存療法の選択肢
軽度から中等度の場合、まず保存療法が試みられます。
- 薬物療法:消炎鎮痛薬や血流改善薬で症状を和らげる
- ブロック注射:神経の炎症を抑え、一時的に痛みを軽減
- 物理療法:温熱や電気刺激で血流を促進
- 整体・運動療法:姿勢を改善し、循環を整える
保存療法は根治を目的とするものではありませんが、症状を抑え生活の質を維持することに有効です。
リハビリテーションの重要性
リハビリは間欠性跛行改善に欠かせません。
- ストレッチ:腰・股関節を柔らかくして神経圧迫を軽減
- 筋力トレーニング:特にふくらはぎ・太もも・体幹を強化し血流を改善
- 歩行訓練:正しい姿勢で歩く練習を行い、歩行距離を徐々に伸ばす
継続することで、手術を回避できる可能性が高まります。
手術が必要なケースとその効果
以下のような症状がある場合、手術が検討されます。
- 数分の歩行で強いしびれが出て、生活に大きな支障がある
- 尿や便のコントロールが困難になっている
- 保存療法を数か月続けても改善が見られない
手術により神経圧迫を取り除くことで、歩行距離が大幅に改善するケースもあります。ただし再発や術後のリハビリが必要になることを理解しておくことが大切です。
治療の第一選択は保存療法とリハビリ。手術は「最後の手段」ですが、適切な時期に行えば効果的です。
整体によるアプローチとセルフケア

間欠性跛行に対して、整体は「痛みを和らげ、歩きやすい体に導く」サポートとして役立ちます。特に姿勢と血流に着目した整体は、手術以外の改善策を探す方にとって大きな助けになります。
姿勢を整えて血流を改善する整体の考え方
脊柱管狭窄症では、背骨や骨盤の歪みが神経や血管を圧迫し、間欠性跛行の原因になります。整体では:
- 背骨や骨盤のバランスを整える
- 筋膜や関節の動きを調整する
- 姿勢を改善し、神経・血流の通り道を広げる
これにより、痛みやしびれが軽減し歩行がスムーズになる効果が期待できます。
平井塾の「姿勢循環整体」とFJAの特徴
平井塾では、独自の二つの手技を組み合わせて施術を行います。
- FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ):細部の動きを整え、神経や関節のエラーを修正する基礎技術。
- 姿勢循環整体:姿勢全体を整え、血流・リンパ・神経の流れを改善する応用技術。
この二段階のアプローチにより、「部分的な痛みの改善」から「全身の循環改善」へと導くことが可能になります。
自宅でできるストレッチ・歩行改善の工夫
整体と併せて、自宅でできるケアも有効です。
- 前屈ストレッチ:腰を軽く丸めて神経圧迫を和らげる
- 股関節ストレッチ:歩行を安定させるための柔軟性アップ
- 正しい歩き方:小股でリズムよく歩くことで神経の負担を減らす
日常生活の工夫と整体を組み合わせることで、症状の悪化を防ぎ、歩ける距離を少しずつ伸ばせます。
整体は「魔法の治療」ではありませんが、姿勢と血流を改善し、日常生活の質を高める強力なサポートになります。
日常生活における間欠性跛行対策

間欠性跛行の症状を和らげるには、整体や治療だけでなく、日常生活の工夫が欠かせません。生活習慣の見直しは、症状改善と再発予防の両方につながります。
歩き方の工夫とストレッチ法
- 小股でテンポよく歩く:大股で歩くよりも腰や神経への負担が少ない
- 休憩を挟む:無理に歩き続けず、ベンチなどでこまめに休む
- ストレッチ:腰や太もも、ふくらはぎを伸ばすことで神経圧迫を緩和
歩き方を工夫し、適度なストレッチを続けることが症状の悪化を防ぐ鍵となります。
腰部脊柱管狭窄症の管理方法
- 正しい姿勢を意識:デスクワークでは骨盤を立てて座る
- 冷えを防ぐ:血流の低下はしびれを悪化させるため、下半身を温める
- 適度な運動:筋肉を維持することで脊柱への負担を軽減
「姿勢・温める・動く」の3点を意識するだけでも、症状は和らぎやすくなります。
痛みやしびれの軽減につながる生活習慣
- 入浴で血流改善:シャワーだけでなく湯船につかる習慣を持つ
- 睡眠環境の工夫:柔らかすぎないマットレスで腰を安定させる
- 荷物の持ち方に注意:重いものを持つときは腰ではなく膝を使う
日常のちょっとした工夫が、「歩ける距離を伸ばす」ための第一歩です。
整体や治療で整えた体を維持するためには、生活習慣の改善が欠かせません。毎日の積み重ねが、間欠性跛行の症状を大きく左右します。
間欠性跛行を改善するための運動

運動は間欠性跛行の改善に欠かせない要素です。筋肉を強化し、血流を促進することで、歩行距離の延長や痛み・しびれの軽減が期待できます。ここでは効果的な運動方法をご紹介します。
効果的なストレッチとエクササイズ
- 前屈ストレッチ:腰を軽く丸める動作で神経圧迫を緩和
- ふくらはぎストレッチ:第二の心臓と呼ばれる下腿筋を柔軟に保ち血流促進
- 骨盤の傾き改善運動:腰椎への負担を減らし、神経の通り道を広げる
毎日5〜10分でも継続することで、体の柔軟性と血流改善効果が高まります。
閉塞性動脈硬化症との関連性
間欠性跛行は脊柱管狭窄症だけでなく、閉塞性動脈硬化症(PAD)でも見られます。
- 脊柱管狭窄症 → 前かがみで症状が楽になる
- PAD → 前かがみでも改善せず、安静時にも痛みが続く
運動を行っても改善しない場合や安静時痛がある場合は、血管系の疾患の可能性があるため医療機関での検査が必須です。
体を支える筋力を高める方法
- スクワット(無理のない範囲で浅めに)
- かかと上げ運動:ふくらはぎを鍛え血流促進
- 体幹トレーニング:腹筋・背筋を鍛え、姿勢を安定
筋力を強化することで、脊柱への負担を減らし、間欠性跛行の症状が出にくい体作りができます。
ストレッチ+筋トレのバランスが重要です。強すぎる運動は逆効果になることもあるため、自分の体に合った強度で継続することが何より大切です。
患者の体験談と成功事例
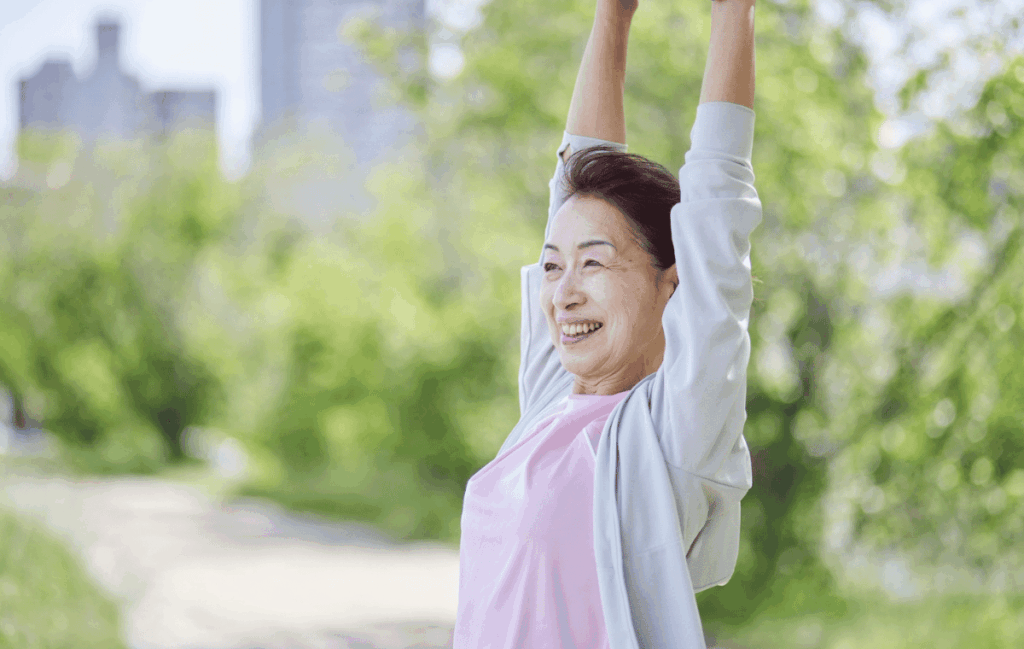
実際に脊柱管狭窄症による間欠性跛行に悩んでいた患者さんが、どのように改善していったのか。その体験談は、同じ悩みを抱える方にとって大きな参考になります。ここでは臨床現場で見られた成功事例を紹介します。
実際の治療経過と改善事例
70代女性は「歩くとすぐに足がしびれて休まないと進めない」という状態でした。
- 整形外科で脊柱管狭窄症と診断
- 手術を勧められたが不安があり保存療法を希望
- 平井塾の整体を取り入れた
結果:姿勢循環整体とFJAで骨盤と腰部を調整し、日常生活での歩行指導を実践。2か月で「休み休みなら30分歩ける」まで改善しました。
患者の声によるリハビリの重要性
60代男性は「手術後の回復が思ったより遅い」と感じていました。
- 術後に整体とリハビリを並行
- 筋力トレーニングと姿勢改善を継続
患者の声:「リハビリを怠らなかったことで、今では買い物や旅行も楽しめるようになった。手術だけではなく、その後の生活改善が大事だと実感した。」
歩行改善の観点からの体験談
50代女性は、長時間のデスクワークで間欠性跛行が悪化。
- 姿勢不良が主な要因と診断
- 平井塾で姿勢循環整体を受けながら、デスクワークの姿勢改善を指導
結果:3か月後には歩行距離が大幅に伸び、「休日に買い物に行くのが苦痛でなくなった」と喜ばれました。
患者さんの共通点は、整体やリハビリを「継続」したこと。短期間での変化ではなく、日常生活の改善と併せて続けたことで、歩行機能が回復しています。
間欠性跛行に関するよくある質問(FAQ)

間欠性跛行については、多くの患者さんが「自分の症状は治るのか?」「再発はあるのか?」といった不安を抱えています。ここではよくある質問に答えていきます。
間欠性跛行は治るのか?
完全に「治る」かどうかは原因によります。
- 軽度の場合 → 保存療法や整体、生活改善で症状が軽減するケースが多い
- 中等度以上 → 改善は見込めるが、長期的な管理が必要
- 重度で神経障害が進んでいる場合 → 手術による改善が選択肢となる
ポイント:早期の対策で、手術を回避できる可能性が高まります。
再発リスクとその管理方法
脊柱管狭窄症に伴う間欠性跛行は、一度改善しても再発することがあります。
- 再発要因:姿勢不良、運動不足、筋力低下、加齢
- 予防策:正しい姿勢の習慣化、筋力維持、整体による定期的な調整
再発を防ぐには「治療+セルフケア+予防」が不可欠です。
医師への相談が必要な症状
次のような症状がある場合は、自己判断せずにすぐに医師へ相談しましょう。
- 安静時にも強い痛みがある
- 尿や便のコントロールができない
- 歩行距離が急激に短くなった
- 下肢の筋力低下が進んでいる
これらは神経障害の進行サインであり、早急な治療判断が必要です。
ポイント:FAQを理解することで、間欠性跛行への不安を軽減し、適切な行動をとることができます。
まとめ:間欠性跛行と上手に向き合うために

間欠性跛行は、脊柱管狭窄症を代表する症状の一つであり、歩行の質を大きく低下させます。しかし、症状の特徴を正しく理解し、早めに適切な対策を取れば、生活の質を守りながら改善を目指すことができます。
脊柱管狭窄症の代表症状を理解する大切さ
- 「歩くと痛い・しびれる、休むと楽になる」 → これが間欠性跛行の典型的なサイン
- 自覚した時点で放置せず、医療機関での診断を受けることが重要
手術以外の改善法を知る安心感
- 保存療法(薬・リハビリ・ブロック注射)
- 姿勢や血流を整える整体
- 日常生活の工夫(歩き方・ストレッチ・生活習慣改善)
これらを組み合わせることで、多くの方が手術を避けながら症状の軽減を実感しています。
専門家と二人三脚で歩行改善を目指す
- 医師による診断で安心を得る
- 整体で姿勢と循環を整え、体を回復しやすくする
- 自分自身の生活習慣を見直し、セルフケアを継続する
間欠性跛行は決して「年齢のせい」ではありません。信頼できる専門家と一緒に歩みながら、後悔のない治療選びと、再び歩ける喜びの回復を目指していきましょう。
関連記事
さらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
👉 脊柱管狭窄症は姿勢が原因?手術以外で改善するための整体アプローチ
👉 猫背はなぜ腰に悪い?姿勢と腰痛の深い関係
👉 血流が悪いと痛みは強くなる?整体で循環を改善する考え方
👉 冷えとしびれの関係|整体でできる血流改善の方法
👉 脊柱管狭窄症の手術で後悔しないために|保存療法と整体という選択肢
投稿者情報:平井 大樹

みゅう整骨院 代表。平井塾 代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。
「患者様の人生に、心からの安心を。」
私は、これまで20年間、延べ10万人を超える患者様と向き合ってきました。その中で最も大切にしてきたのは、「痛みを取る」ことだけではなく、「患者様が心から安心して過ごせる毎日を取り戻す」ことです。
- 長期にわたる信頼:みゅう整骨院には、5年以上通われる方が308名、10年以上通われる方も100名いらっしゃいます。これは、一時的な改善ではなく、患者様が私たちに一生の健康を任せてくださっている証です。
- 根本的なアプローチ:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)、姿勢循環整体という独自の手技で、痛みの箇所だけでなく、その根本原因である身体全体の歪みや動きの不調にアプローチします。
- 平井の予約が取れない理由:開業後、患者様の紹介がメインで予約が満員になりました。2020年以降、新規予約は5年待ちの状態です。現在、新規予約を取る予定はありませんが、みゅう整骨院または、平井塾受講生から同じ施術を受けることができます。
このコラムが、あなたの不調を改善し、より豊かな毎日を送るための一歩となれば幸いです。