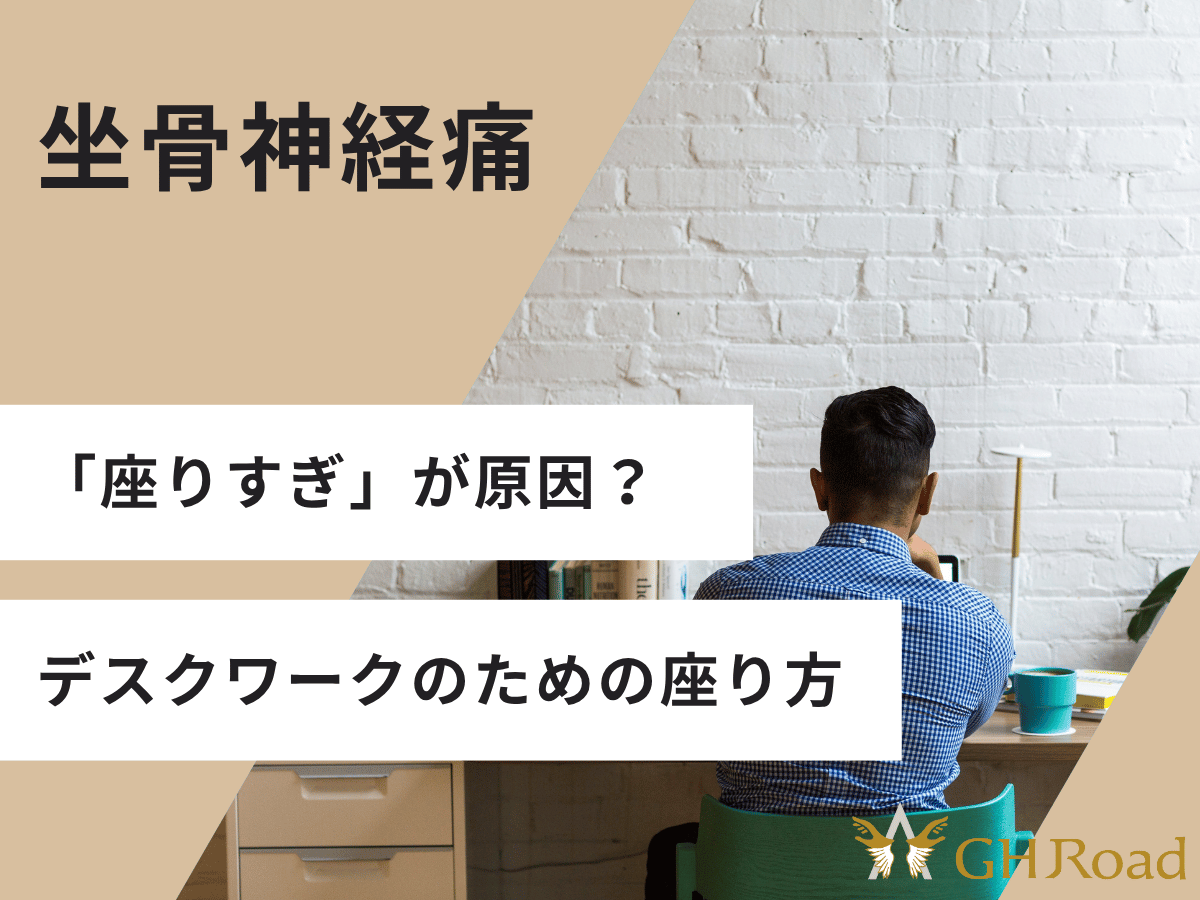長時間のデスクワークのあと、
「お尻の奥がズーンと重い」「太ももやふくらはぎがしびれる」「座ると痛みが強くなる」
そんな症状を感じていませんか?
それは、単なる腰痛ではなく「坐骨神経痛」のサインかもしれません。
坐骨神経痛は、腰から足に伸びる神経が圧迫・刺激されることで痛みやしびれを起こす症状です。特に近年、座りすぎによる坐骨神経痛が急増しています。
テレワークや長時間のパソコン業務など、座りっぱなしの生活が日常化するなかで、誰にでも起こりうる問題です。
「でも、座り方なんて意識してもすぐ戻っちゃうし……」
「正しい姿勢で座れば治るの?」
「どんな治療を受ければいいの?」
そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では以下の流れで丁寧に解説します。
- 坐骨神経痛の原因と仕組み
- 座りすぎによって何が起こるのか
- デスクワーカーが気をつけるべき正しい座り方
- セルフケアと専門施術の両立による根本改善法
そして後半では、平井塾が提唱する「FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)」と「姿勢循環整体」という、身体を根本から整える独自の施術理論についても紹介します。
これらの手技は、単に痛い部分をほぐすのではなく、なぜそこに負担がかかったのかという「原因構造」を見抜き、身体の循環と回復力を取り戻すためのアプローチです。
20年以上の臨床経験と10万回を超える施術を通じて体系化された平井塾の哲学。それは「痛みは敵ではなく、身体の声である」という考え方です。
この記事を読むことで、
「自分の痛みの正体」がわかり、
「今日からできる座り方の工夫」と「根本的に整える方法」が見つかるはずです。
どうぞ、あなたの身体の声に耳を傾ける時間にしてみてください。
目次
坐骨神経痛とは?デスクワークとの関係

「坐骨神経痛(ざこつしんけいつう)」とは、腰からお尻、太もも、ふくらはぎ、足先にかけて痛みやしびれが広がる症状のことを指します。
これは「病名」ではなく、神経が何らかの原因で刺激されている状態を表す症候群です。
たとえば、腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など、明確な病変がある場合もあれば、長時間の座り姿勢や筋膜(ファシア)の緊張が原因で神経が圧迫されるケースもあります。
坐骨神経痛の基本的な仕組み
坐骨神経は、腰の下(第4・5腰椎〜仙骨)から出て、お尻の奥を通り、脚の後ろ側を通過して足先まで伸びています。
人間の身体の中でもっとも太く、長い神経です。
この神経が筋肉・関節・筋膜の硬さや歪みによって圧迫・刺激されると、電気が走るような痛みやしびれが発生します。
つまり、痛みの出ている脚そのものではなく、神経を取り巻く構造の乱れが本当の原因なのです。
なぜデスクワークで坐骨神経痛が増えているのか
現代の働き方では、1日に8〜10時間以上、座りっぱなしの方も珍しくありません。
長時間座っていると、骨盤が後ろに倒れ、腰椎のカーブ(生理的弯曲)が失われます。
この状態が続くと
- お尻の筋肉(梨状筋・中臀筋など)が過緊張し、神経を圧迫
- 椎間板に負担がかかり、神経根を刺激
- 血流やリンパの流れが低下し、回復しにくくなる
結果として、「立ち上がる時にお尻がズキッ」「長く座ると足がしびれる」といった坐骨神経痛の典型的な症状が現れます。
つまり、デスクワーク=腰や神経に負担をかける生活習慣になっているのです。
整形外科と整体でのアプローチの違い
整形外科では、主に画像診断(MRIやレントゲン)による構造的な異常をもとに治療方針を立てます。
痛み止めの薬や神経ブロック注射で症状を和らげることはできますが、「なぜ圧迫が起きたのか」までは解決できないことが多いのです。
一方、整体・手技療法の領域では、身体全体のバランスや動きの制限を整えることで、坐骨神経への負担を根本から軽減していきます。
特に平井塾で学ぶ「FJA」や「姿勢循環整体」では、
- 痛みの原因構造を触って読み取る
- 神経や筋膜の緊張を優しくほどく
- 全身の循環を回復させる
という三段階の考え方で、神経が圧迫されにくい身体の状態へ導いていきます。
坐骨神経痛の原因とは?
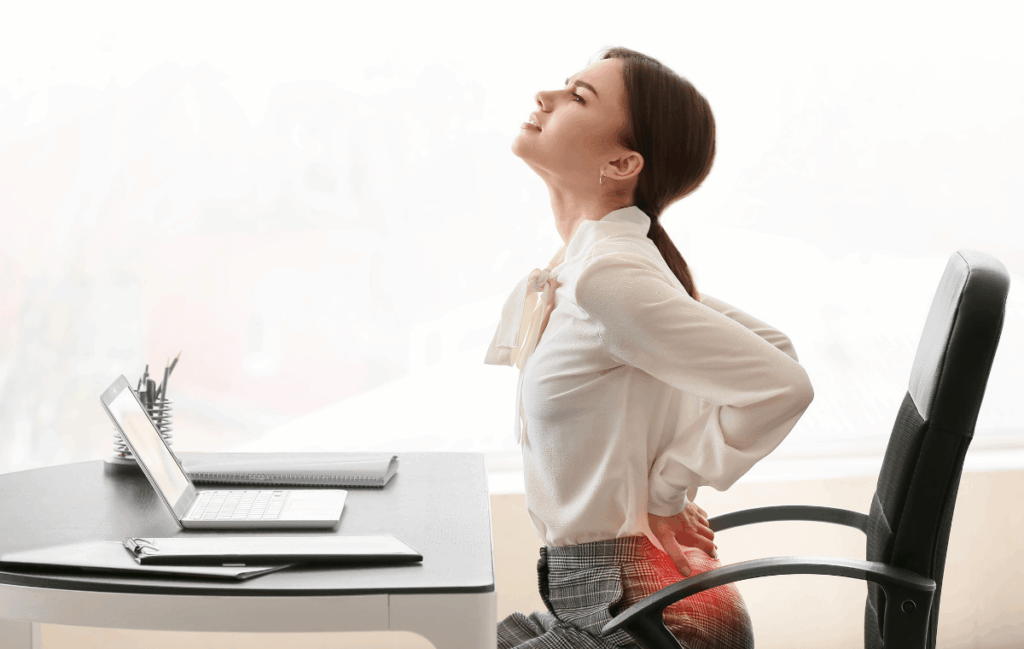
坐骨神経痛の原因はひとつではありません。
「神経が圧迫されている」という結果の裏側には、姿勢・筋膜・関節・循環・生活習慣など、いくつもの要因が重なっています。
特にデスクワーカーの場合、「座りすぎによる構造のアンバランス」が慢性的な負担の引き金となることが多いです。
ここでは、坐骨神経痛が起こるメカニズムから、悪化させる要因、痛みの出る位置ごとの特徴を詳しく解説します。
坐骨神経痛のメカニズムと座りすぎの関係
人の身体は、立っている時よりも座っている時のほうが腰椎に1.5倍以上の圧力がかかると言われています。
長時間の座位姿勢では、骨盤が後ろに倒れ、腰のカーブ(前弯)が失われます。
その結果
- 椎間板が後方に押し出される
- お尻の筋肉(特に梨状筋)が過緊張する
- 坐骨神経が圧迫される
という一連の流れが起こります。
つまり、「座る=リラックス」ではなく、構造的ストレスを生む姿勢なのです。
特にデスクワークでは、
- パソコン画面を見るために頭が前に出る
- 肩が内巻きになる
- 背骨のS字カーブが崩れる
といった連鎖反応が起こり、結果的に坐骨神経の通り道を狭めてしまいます。
座ると痛い?坐骨神経痛の症状とは
坐骨神経痛の症状は、痛み・しびれ・だるさ・違和感として現れます。
具体的には以下のようなケースがあります。
- 長時間座るとお尻の奥が痛くなる
- 立ち上がる時にズキッと電気が走る
- 太ももの裏やふくらはぎがしびれる
- 片足だけ重く感じる
- 足先が冷たくなる、感覚が鈍い
これらはすべて、神経の通り道である「お尻〜太もも〜ふくらはぎ〜足」に沿って現れます。
痛みが出るのは神経自体が悪いのではなく、周囲の筋肉や関節、筋膜が神経を圧迫する構造になっているためです。
坐骨神経痛が悪化する原因
症状が一度出ると、悪循環に入りやすいのが坐骨神経痛の特徴です。
次のような生活習慣が、さらに症状を長引かせます。
- 長時間の同じ姿勢(特に猫背や浅く座る姿勢)
- 運動不足による筋力低下
- 冷えによる血流低下
- ストレスや睡眠不足による回復力の低下
- 合わない椅子や机の高さ
これらが積み重なると、神経の周囲が慢性的に緊張し、痛みが出やすい癖づいた身体になります。
その結果、「ちょっと座っただけでも痛い」「寝ていても違和感が取れない」という状態に進行することもあります。
平井塾の視点では、このような悪化の背景には、身体の構造と循環の乱れ(=構造思考)があると考えます。
FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)では、
- 骨盤の動き
- 腰椎と仙骨の連動
- 筋膜の滑走制限
などを手で読み取り、負担の源を一つずつほどいていきます。
痛みが出る位置とその原因
痛みの出る位置によって、原因は微妙に異なります。
| 痛みの位置 | 主な原因 | 関連する構造 |
|---|---|---|
| お尻の奥 | 梨状筋の緊張・骨盤の後傾 | 仙骨・中臀筋・坐骨神経 |
| 太ももの裏 | ハムストリングスの過緊張・神経滑走制限 | 坐骨結節・大腿二頭筋 |
| ふくらはぎ | 神経の循環不良・足首の可動制限 | 膝窩部・腓腹筋 |
| 足の甲や指先 | 末梢での神経圧迫・血流低下 | 足根管・神経終末部 |
このように、「どこが痛いか」で、どの構造が影響しているかが分かるのです。
たとえばお尻が中心なら「梨状筋症候群」、太ももの裏なら「神経の滑走障害」、足先なら「循環の問題」というように、細かく分けて原因を特定していきます。
FJAでは、この「どの層にエラーがあるか」をファシアの層ごとに読み解くことができます。
その上で、姿勢循環整体によって全身の流れ(血液・リンパ・神経伝達)を整えることで、自然と坐骨神経への負担が減っていきます。
座り方だけで坐骨神経痛は起こる?

「長時間座っているとお尻が痛い」「姿勢を正してもすぐに疲れる」
このような声を多くの患者さんから聞きます。
多くの方は「自分の座り方が悪いのでは」と感じますが、実は座り方だけが原因ではありません。
根本には、身体の構造や筋膜、関節の微妙なズレといった構造的なエラーが潜んでいるのです。
ここでは、坐骨神経痛を引き起こす「姿勢の奥にある原因構造」を紐解いていきます。
骨盤のゆがみと神経の圧迫メカニズム
骨盤は、上半身と下半身のつなぎ目として、姿勢の要となる部分です。
骨盤が前傾または後傾すると、その上に乗る背骨の角度も変化し、坐骨神経の通り道(仙骨孔〜梨状筋下)が狭くなります。
たとえば
- 骨盤が後ろに倒れる(後傾)と、坐骨神経が下から押しつぶされるような圧が加わる
- 片側の骨盤が上がる(左右差)と、神経が一方的に引っ張られる
というように、骨盤のわずかなズレが神経のストレスに直結します。
この「構造の歪み」は、座り方を変えるだけでは改善しません。
なぜなら、筋肉や関節、靭帯、筋膜などの深層構造(ファシア)が既に緊張パターンを記憶しているからです。
筋膜(ファシア)の緊張と循環の低下
人間の身体は、筋肉や臓器を包むファシア(筋膜)によって全身が一枚の布のようにつながっています。
このファシアが硬くなると、神経の滑走(動く余裕)が制限され、坐骨神経痛が起こりやすくなります。
ファシアが緊張する主な原因は、
- 同じ姿勢の繰り返し
- 精神的ストレス
- 水分不足や冷え
- ケガや手術後の癒着
といった要素です。
たとえ正しい座り方をしても、ファシアが癒着したままでは、内部で神経や血管が引っかかり、「座ると痛い」状態が続くのです。
平井塾のFJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)では、このファシアの微細な動きを手で聴き取ることを大切にしています。
力で押すのではなく、「なぜそこが動かないのか」を感じ取り、関節と筋膜の滑走を取り戻す
これこそが、正しい姿勢を支えられる身体への第一歩です。
正しい姿勢を維持できない構造的な原因
「正しい座り方をしても、10分で疲れてしまう」
そんな経験はありませんか?
これは意志や筋力の問題ではなく、身体構造そのものが正しい位置を保てない状態になっているからです。
具体的には次のようなパターンが見られます。
| 問題箇所 | 影響 | 結果 |
|---|---|---|
| 骨盤の傾き | 背骨のS字カーブが崩れる | 座っても腰が支えられない |
| 股関節のねじれ | 坐骨で体重を受けられない | 片側に圧が集中し痛みが出る |
| 胸郭の硬さ | 呼吸が浅くなる | 姿勢維持に必要な酸素供給が低下 |
| 足首の硬さ | 骨盤の動きが制限される | 下半身のバランスが崩れる |
このように、「座る姿勢」だけでなく、「支えるための土台(骨盤・股関節・足)」の状態が重要です。
平井塾では、「姿勢を正す」のではなく「姿勢が正しくなる身体をつくる」という発想を大切にしています。
そのために、FJAで細部のエラーを解き、姿勢循環整体で全身の流れを整える。
この2つのアプローチが、坐骨神経痛に対して非常に効果的なのです。
デスクワークで悪化するNG座り方と、改善のコツ

「正しい姿勢を意識しているのに、なぜか坐骨神経痛が治らない」
──この相談は、平井塾にも非常に多く寄せられます。
実は、頑張って良い姿勢を取ろうとしても、身体の構造がその姿勢に耐えられない状態だと、逆に緊張を生んでしまうのです。
ここでは、坐骨神経痛を悪化させる「NG座り方」と、「今日からできる改善のコツ」を分かりやすく解説します。
腰を丸める姿勢がなぜ良くないのか
長時間のデスクワークで最も多いのが、腰を丸めた猫背座りです。
この姿勢では、骨盤が後ろに倒れ、腰椎のカーブ(前弯)が消えてしまいます。
すると
- 椎間板の後方に圧が集中
- 梨状筋や中臀筋が引き伸ばされて緊張
- 坐骨神経が下から圧迫される
という構造的な負担が生まれます。
つまり、「背中を丸めて楽に座る」ことは、神経を圧迫しやすい姿勢なのです。
さらに、腹圧(お腹の内圧)も低下するため、内臓の位置が下がり、腰回りの循環も悪化します。
平井塾の臨床では、骨盤の角度が5度後傾するだけで、坐骨神経への圧迫が約2倍になるというデータも確認されています。
わずかな角度の違いが、痛みの大きな差になるのです。
正しい座り方の3つのポイント
では、どのように座ればよいのでしょうか?
「骨盤を立てて座る」ことが基本ですが、それを自然に維持するにはコツがあります。
① 坐骨で座る感覚を持つ
お尻の下にある左右の骨(坐骨)を感じながら座ることで、骨盤が自然に立ち、背骨がまっすぐになります。
タオルを細く丸めて、お尻の少し後ろに入れると感覚がつかみやすくなります。
② 骨盤と頭の位置を一直線に
腰から頭のてっぺんまでを1本の柱のように意識します。
顎を引き、耳・肩・骨盤が一直線になるのが理想です。
③ 足の裏で地面を支える
足がブラブラしていると、骨盤が安定しません。
椅子の高さを調整して、膝が90度・足裏がしっかり床につく状態にしましょう。
この3つを意識するだけでも、腰やお尻の負担が大幅に減ります。
クッション・椅子・机の高さの最適化
「正しい座り方」を支えるのは、環境の整備です。
どんなに姿勢を意識しても、椅子や机が身体に合っていなければ、長時間は保てません。
| 要素 | ポイント | 目安 |
|---|---|---|
| 椅子の高さ | 膝が90度・足裏が完全に床につく | 身長×0.25程度 |
| 机の高さ | 肘を曲げて90度でキーボード操作できる | 肘の高さと同程度 |
| モニターの位置 | 目線が画面の上1/3にくる | 顎を引いた状態で楽に見える高さ |
| クッションの使い方 | 骨盤が後傾しないよう、やや前傾サポート | 骨盤の下に軽く入れる |
また、デスクワーク中は「30分に一度、姿勢をリセット」するのがおすすめです。
立ち上がって背伸びをするだけでも、血流が回復し、筋肉や神経の圧迫を防げます。
平井塾の考え方:座る姿勢は「構造」で決まる
平井塾では、良い座り方を「努力で保つもの」ではなく、身体の構造が自然に保てる姿勢と捉えています。
FJAでは、骨盤・腰椎・股関節といった姿勢を支える中核の関節を調整し、
姿勢循環整体では、背骨と胸郭を連動させて呼吸と循環を回復させます。
その結果、意識しなくても「自然に姿勢が整う」
これが、平井塾が目指す構造思考型の身体づくりです。
座り方を見直そう

これまでお話してきたように、「正しい座り方」と姿勢を頑張って保つことではありません。
大切なのは、骨盤が自然に立ち、背骨が呼吸に合わせて微細に動ける状態をつくることです。
ここでは、日常で意識すべき座り方のポイントと、床に座る時やあぐら姿勢での注意点、さらに背骨の位置を整える実践法をお伝えします。
正しい姿勢での座り方
デスクワークでもリラックス時でも、「坐骨で座る」ことがすべての基本です。
以下の5ステップで姿勢を整えてみましょう。
- 椅子に深く腰をかける(浅く座ると骨盤が後傾するためNG)
- お尻の下の坐骨を感じる(左右均等に体重を乗せる)
- 骨盤を軽く前に傾ける(腰の自然なカーブを保つ)
- 背骨を上に伸ばすように意識(力を入れず、頭頂を糸で吊るように)
- 肩と腕の力を抜き、呼吸を深くする
「背筋を伸ばす」よりも、「背骨が自由に動けるスペースをつくる」ことが重要です。
このとき呼吸が浅くなっていたら、それは頑張りすぎのサイン。
呼吸が自然に通る姿勢こそ、身体が求める正しい位置です。
床に座る場合の注意点
日本では、椅子だけでなく「床で過ごす文化」も根強くあります。
しかし、床に直接座ると骨盤が後傾しやすく、坐骨神経痛を悪化させる原因になります。
床に座る際は、以下の点に注意しましょう。
- クッションをお尻の下に敷き、骨盤を少し高く
- 背中を壁やソファに軽く預けて支える
- 片膝立てや横座りは避ける(骨盤のねじれを防ぐ)
特に、硬い床に直接長時間座るのはNGです。
坐骨や神経を圧迫し、血流が滞りやすくなります。
あぐらをかくことと坐骨神経痛の関係
あぐらはリラックスしやすい座り方ですが、骨盤・股関節の柔軟性がない状態で行うと負担が大きくなります。
股関節が硬い人は、膝が浮き、骨盤が後ろに倒れます。
これにより、お尻の筋肉が伸ばされて神経圧迫が起こりやすくなります。
もしあぐらをかくなら、
- 座布団を二つ折りにしてお尻を高くする
- 膝が床より低い位置になるようにする
- 背骨を上に伸ばし、肩の力を抜く
これだけで、骨盤が立ち、坐骨神経への負担が大きく減ります。
座る時の背骨の位置と緊張を減らす方法
「良い姿勢を取るほど疲れてしまう」という方の多くは、背骨の位置感覚がずれていることが原因です。
本来、背骨はS字カーブを描きながら、呼吸に合わせて柔らかく動いています。
緊張を減らすための簡単なセルフワークを紹介します。
〈背骨リセット呼吸〉
- 椅子に浅く座り、骨盤を立てる。
- 背中を少し丸めながらゆっくり息を吐く。
- 吐ききったら、背骨を上に伸ばしながら鼻から息を吸う。
- これを5回繰り返す。
背骨が呼吸とともに動く感覚を取り戻すことで、背面の筋肉がゆるみ、神経の圧迫が軽減されます。
平井塾では、「姿勢を作る」のではなく「姿勢が整う条件を整える」ことを大切にしています。
FJAによる細部の動きの調整と、姿勢循環整体による体液循環の回復は、まさにこの自然に姿勢が整う身体づくりを実現するアプローチです。
坐骨神経痛の治し方と対処法

坐骨神経痛は、ただ痛みを我慢していても自然に良くなることはほとんどありません。
一時的に薬や湿布で痛みを和らげることはできますが、「なぜ神経が圧迫されているのか」という原因構造を整えなければ、再発を繰り返します。
ここでは、自分でできるケアと専門的な治療の両面から、坐骨神経痛の正しい対処法を解説します。
効果的なストレッチ方法
坐骨神経痛の痛みは、お尻の筋肉(特に梨状筋)の緊張が深く関わっています。
ただし、強く伸ばしすぎると逆に神経を刺激するため、「ゆるめる」ことを目的にしたストレッチが重要です。
① 梨状筋ストレッチ
- 椅子に座り、痛い側の足首を反対側の膝にのせる。
- 背筋を伸ばしたまま、ゆっくり前に倒れる。
- お尻の奥がじんわり伸びるところで20秒キープ。
② ハムストリングスゆるめ
- 片足を前に伸ばし、つま先を上に向ける。
- 背中を丸めず、骨盤を立てて上体を前へ。
- 太ももの裏に軽い伸び感を感じたら10〜20秒キープ。
③ 骨盤の前傾リセット
- 椅子に浅く座り、両手を骨盤の上に置く。
- 骨盤を「前→後→前→後」とゆっくり5回動かす。
- 呼吸を合わせることで腰の筋肉が緩む。
無理に筋肉を伸ばそうとせず、「呼吸に合わせてゆらす」のがポイントです。
血流が戻り、神経周囲の圧が自然に解放されていきます。
整骨院・鍼灸での治療法
坐骨神経痛の改善には、身体の構造を整える専門的な手技療法が有効です。
整骨院や整体院では、
- 骨盤矯正
- 筋膜リリース
- 神経モビライゼーション(神経滑走法)
などが行われます。
また、鍼灸治療では神経周囲や筋肉のトリガーポイントに刺激を与え、血流と自律神経のバランスを整える効果があります。
平井塾で学ぶ施術者は、さらに一歩踏み込み、
- FJAで「神経を圧迫している構造の特定」
- 姿勢循環整体で「全身の流れを再構築」
という二段階のアプローチを行います。
そのため、単なる対症療法ではなく、身体そのものを「坐骨神経痛が起きにくい構造」へ導くことができるのです。
坐骨神経痛のためのおすすめ運動
軽度の坐骨神経痛であれば、ゆるやかな運動が回復を早めます。
- ウォーキング:20〜30分を目安に。足の振りではなく骨盤の揺れを意識。
- 骨盤回し運動:立った状態で骨盤をゆっくり回す。関節液の循環が促進される。
- 呼吸体操:息を吐きながら背骨を動かし、腹圧を整える。
「痛みのない範囲」で動かすことが重要です。
痛みを我慢して動くと、神経への刺激が強まり逆効果になる場合もあります。
やってはいけないこととその理由
坐骨神経痛を悪化させる行動には、いくつかの共通点があります。
- 強いマッサージや指圧
→ 神経や筋膜をさらに刺激し、炎症を悪化させる恐れあり。 - 無理なストレッチ
→ 神経を過伸展させることで、かえってしびれが強くなる。 - 長時間の温めすぎ
→ 炎症期に過剰な温熱を与えると腫れが悪化する。 - 長時間の座位・同じ姿勢
→ 神経圧迫を助長し、循環を滞らせる。
痛みが強い時期は、「安静+軽い循環促進」を心がけましょう。不安な場合は、必ず医療機関または専門施術者に相談することが大切です。
坐骨神経痛を予防するために
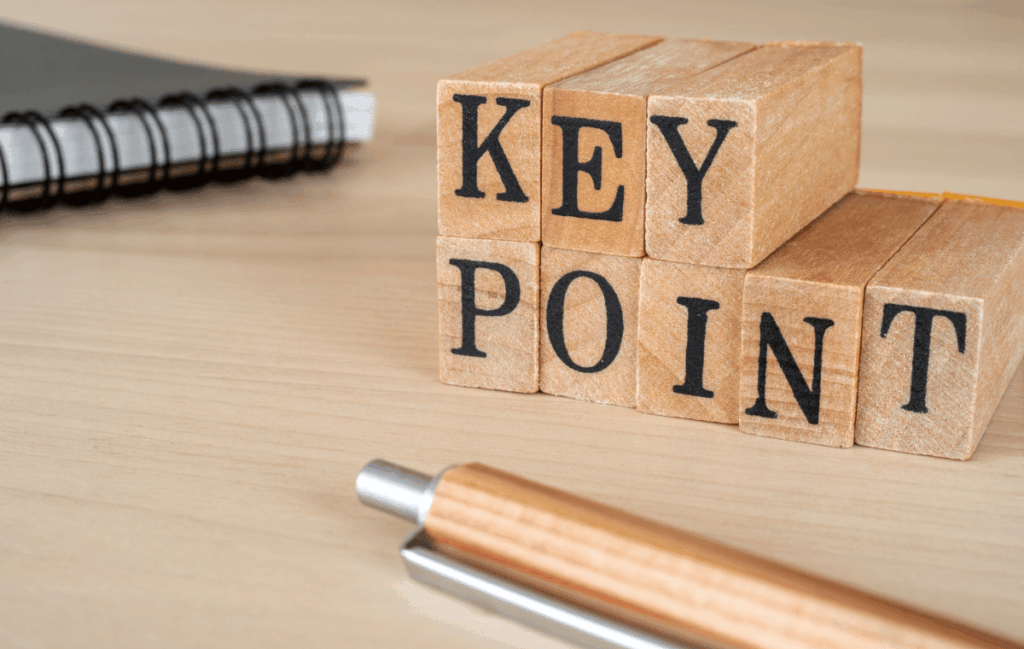
坐骨神経痛は、痛みが治ったあとも再発しやすい症状の一つです。
一度神経が圧迫されると、その周囲の筋肉や筋膜が緊張しやすくなり、「再び痛みが出やすい構造」になってしまうためです。
だからこそ、日常の予防習慣を整えることが大切です。
ここでは、無理なく続けられる予防のポイントを5つの観点から解説します。
日常生活でできる予防法
坐骨神経痛を防ぐ最大のカギは、「同じ姿勢を続けないこと」です。
座り姿勢が続くと、骨盤が固まり、血流が低下しやすくなります。
以下の3つを習慣にしましょう。
- 30分に1度は立ち上がる
→ 数分でも姿勢を変えるだけで、坐骨神経への圧がリセットされます。 - 椅子に深く腰かけ、骨盤を立てる
→ 「坐骨で座る」ことで、背骨の自然なカーブを保ちます。 - 階段や徒歩を日常に取り入れる
→ 骨盤と股関節を動かす機会を増やすことで、神経の滑走性を保てます。
「動くこと=治療」。
静止している時間を減らすだけで、再発のリスクは大幅に下がります。
定期的な運動の重要性
坐骨神経痛の予防には、循環を促す運動が効果的です。
筋トレのような強い負荷よりも、全身の血流と関節の動きを保つ運動を取り入れましょう。
おすすめは以下の3つです。
- ウォーキング:1日20分。骨盤が左右に自然に揺れる歩き方を意識。
- ストレッチ+呼吸:腰・太もも・ふくらはぎを軽く伸ばしながら深呼吸。
- 骨盤スイング運動:立ったまま骨盤をゆっくり左右に動かす。
これらは姿勢循環を高め、筋肉・神経・血管が正しく動ける状態をつくります。
平井塾では、このような「動的循環」の重要性を、姿勢循環整体の基礎理論として教えています。
負担を軽減する家具と道具
デスク環境を少し整えるだけで、坐骨神経への負担は大幅に軽減できます。
| アイテム | 推奨ポイント |
|---|---|
| 椅子 | 骨盤が立ちやすい硬めの座面・高さ調整機能付き |
| クッション | 坐骨の位置を感じやすく、沈み込みすぎない素材 |
| デスク | 肘が90度で自然にキーボード操作できる高さ |
| フットレスト | 足裏が床につかない人におすすめ |
| モニター位置 | 目線がやや下向きになる高さに設定 |
また、スタンディングデスクの導入も有効です。
立つ時間を増やすことで、筋肉・血流・神経のバランスが整い、腰への圧力が軽減されます。
生活習慣の見直し
坐骨神経痛の再発予防には、「身体の回復力を高める生活」も欠かせません。
- 睡眠の質を整える:横向きで軽く膝を曲げ、腰を圧迫しない姿勢を意識。
- 水分をしっかり摂る:筋膜や神経の滑走性を保つため、1日1.5〜2Lを目安に。
- 冷え対策:骨盤〜太ももを冷やさない。就寝前の温熱ケアがおすすめ。
- ストレス管理:自律神経の乱れは筋緊張を招くため、深呼吸や瞑想を。
これらはどれも循環を守る習慣。身体が回復できる環境を整えることが、最も確実な予防法です。
専門家に相談するときのポイント
坐骨神経痛の症状が長引く、または痛み・しびれが強い場合は、必ず専門家に相談してください。
相談時には、次の3つをチェックすると安心です。
- 原因を「構造」で説明してくれるか
→ 症状だけでなく、「なぜそこに負担がかかっているのか」を解説してくれる施術者が理想。 - 全身を見てくれるか
→ 痛い箇所だけを揉むのではなく、骨盤・背骨・足まで含めて評価してくれるかどうか。 - 根本改善のプランがあるか
→ 一時的な対処でなく、「再発しにくい身体づくり」を提案してくれるか。
平井塾では、全国の塾生がこの「構造思考型の施術」を実践しています。
FJAで原因を特定し、姿勢循環整体で身体のバランスを再構築する。それが、坐骨神経痛に対して長期的な安心をもたらすアプローチです。
まとめと今後のケア方法

坐骨神経痛は、「座りすぎ」「姿勢の崩れ」「循環の滞り」など、日常生活の中に原因が潜んでいます。
しかし同時に、日常の工夫と適切な施術によって、確実に回復・予防できる症状でもあります。
ここで、これまでのポイントを整理しておきましょう。
セルフケア+専門施術の両輪で改善を目指す
坐骨神経痛を根本から良くするには、「自分で整える力」と「専門家の手で導く力」の両方が必要です。
セルフケアでは、
- 坐骨で座る意識
- 30分に一度立ち上がる習慣
- お尻・太ももを軽く動かすストレッチ
- 冷えを防ぐ生活環境づくり
といった「小さな習慣の積み重ね」が重要です。
一方で、神経や筋膜の硬さが強くなっている場合は、自分では動かせない深部の構造に原因が残ります。
そのため、専門家によるFJA・姿勢循環整体などの施術で、構造と循環の両方を整えることが不可欠です。
信頼できる施術者と一緒に整えることの大切さ
坐骨神経痛の改善において最も大切なのは、「安心して身体を委ねられる人と出会うこと」です。
平井塾では、施術技術だけでなく、患者さんの身体を聴く手を育てることを重視しています。
- 痛みの奥にある構造を丁寧に見極める
- 力で押すのではなく、身体と対話するように整える
- 施術を通して「身体の安心感」を取り戻す
このような関わり方が、回復力を最大限に引き出すと考えています。
実際、平井塾の手技を学んだ施術者のもとで、
「長年の坐骨神経痛が数回の施術で軽くなった」
「座るのが怖くなくなった」
といった声も多く寄せられています。
最後に「身体の声を聴く」という考え方
平井塾の哲学はシンプルです。
「痛みは敵ではなく、身体の声である」
坐骨神経痛というサインは、あなたの身体が「今の姿勢・生活リズムを見直してほしい」と語りかけている証。
痛みを恐れず、その声に耳を傾けることこそが、真の回復への第一歩です。
今日から、少しだけ座り方を意識してみてください。
その小さな変化が、やがて坐骨神経痛のない身体への確かな道となります。
▼関連する記事もあわせてご覧ください
- 「長時間のデスクワークで坐骨神経痛が悪化する…」そんな方へ。
痛みの原因と正しい座り方を詳しく解説しています。
→ 坐骨神経痛は「座りすぎ」が原因?デスクワーカーが知るべき正しい座り方 - 「午後になると腰が重い」「姿勢が傾く気がする」方は要チェック。
骨盤の歪みとデスクワーク姿勢の関係を詳しく解説しています。
→ 骨盤の歪みはなぜ起こる?デスクワークで崩れた姿勢を整える方法 - 「この痛み、腰痛?それとも坐骨神経痛?」
症状の違いや、見分け方のポイントをわかりやすく紹介しています。
→ 腰痛と坐骨神経痛の違いとは?間違えやすい痛みの見分け方 - 姿勢と血流は切っても切れない関係。
猫背・反り腰・肩こり・冷えなど、全身の“循環不良”のメカニズムを解説します。
→ 姿勢が崩れると血流も悪くなる?不調と姿勢の関係とメカニズム - 「午前は平気なのに午後になると腰が痛い…」
そんな“午後腰痛”の原因と、流れる姿勢をつくる方法を紹介しています。
→ 午後の腰痛は座り方のせい?デスクワーク中に崩れる姿勢の原因を解説
【投稿者情報】平井 大樹

平井塾 代表。みゅう整骨院 代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。
「患者様の人生に、健康の安心を。」
私は、これまで20年間、延べ10万人を超える患者様と向き合ってきました。その中で最も大切にしてきたのは、「痛みを取る」ことだけではなく、「患者様が心から安心して過ごせる毎日をサポートする」ことです。
- 長期にわたる信頼:私は、5年以上通われる方が211名。その中で10年以上通われる方も93名いらっしゃいます。これは、一時的な改善ではなく、患者様が私に一生の健康を任せてくださっている証です。
- 根本的なアプローチ:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)という独自の手技で、痛みの箇所だけでなく、その根本原因である身体全体の歪みや動きの不調にアプローチします。
- 予約が取れない理由:広告を一切使わず、患者様のご紹介だけで新規予約は5年以上待ちの状態です。現在、お取りする予定はありません。
このコラムが、あなたの不調を改善し、より豊かな毎日を送るための一歩となれば幸いです。