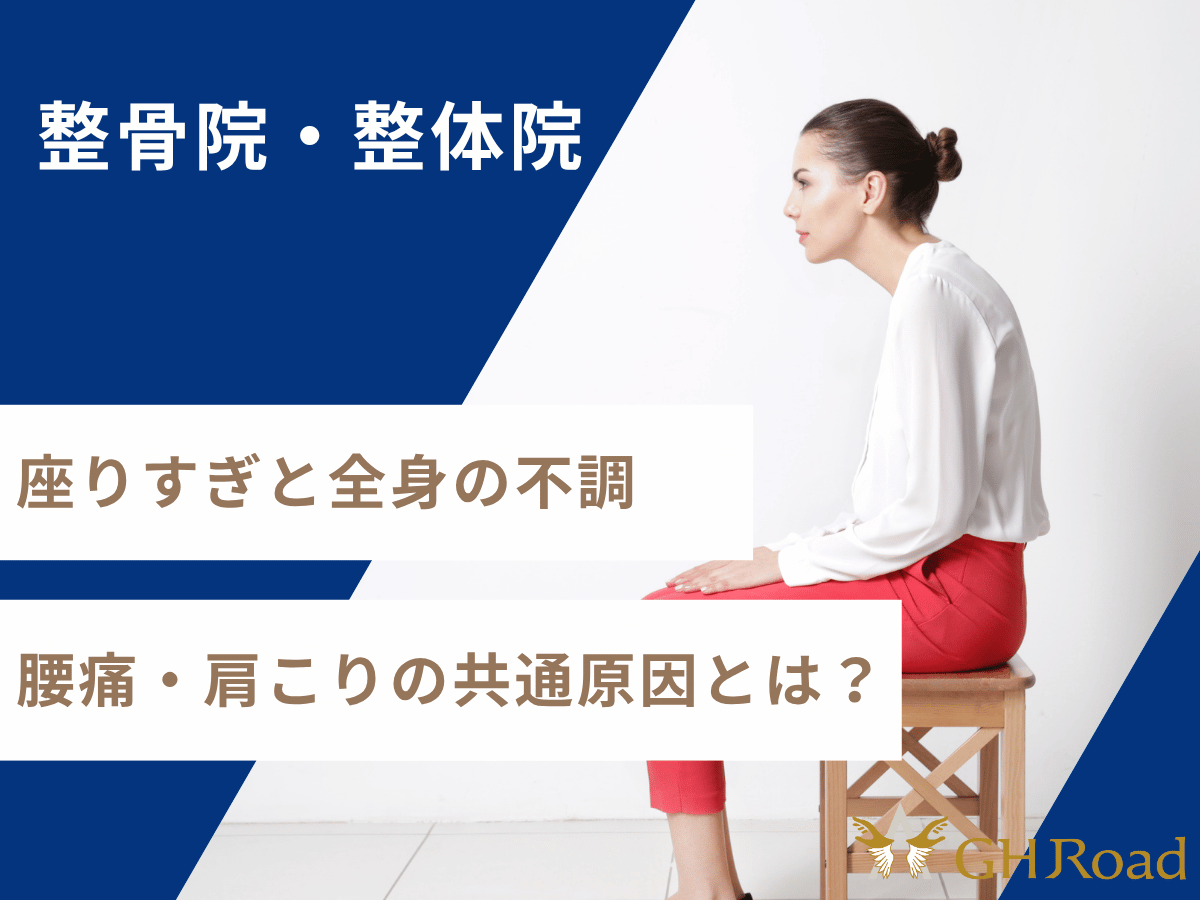「一日座っているだけなのに、なぜこんなに体が重いのだろう。」
「腰が痛い、肩が張る、足がむくむ──全部つながっている気がする。」
デスクワークやリモートワークが増えた現代、こうした声を訴える方が急増しています。
私たちは座るという行為を「楽な姿勢」と思いがちですが、実は長時間の座りすぎこそが、体に最も大きな負担をかけているのです。
座りすぎによる腰痛・肩こり・むくみといった不調は、単に運動不足や加齢が原因ではありません。
それらの根底には、「姿勢の崩れ」と「血流の滞り」という、身体の構造的な問題が潜んでいます。
平井塾では、このような不調を「部分の問題」ではなく、身体全体の循環リズムが乱れた姿勢循環の崩れと捉えています。
姿勢が崩れると、
骨盤の傾き → 筋膜のねじれ → 呼吸の浅さ → 血流の停滞 → 自律神経の乱れ…
という連鎖が起こり、全身のバランスが静かに崩れていきます。
その結果として現れるのが、腰の重さ、肩のこわばり、足のむくみ、慢性的な疲労感です。
逆にいえば、姿勢と循環を整えれば、体は自然に回復へと向かうということ。
これは「正しい姿勢を意識する」だけではなく、身体全体が流れる構造を取り戻すことを意味します。
本記事では、
- なぜ座りすぎると身体は不調になるのか
- 腰痛・肩こり・むくみの共通原因とは
- デスクワーク中でもできる改善法と予防策
を、平井塾の「構造思考」と「姿勢循環整体」の視点からわかりやすく解説します。
身体の不調を部分の痛みとしてではなく、流れの乱れとして見直すことができれば、痛みや重さだけでなく、心身の軽さまでも取り戻せるはずです。
座りすぎで止まってしまった身体の流れを、もう一度動かしていくための第一歩を、ここから始めましょう。
目次
座りすぎがもたらす全身の不調とは?

「ただ座っているだけなのに、どうしてこんなに体がつらいのか。」
多くのデスクワーカーが感じるその疑問の答えは、「座りすぎが全身の構造と循環を止めてしまう」という事実にあります。
人間の身体は本来、立ち・歩き・呼吸などの動きの中で筋肉と関節がポンプのように働き、血液やリンパを全身に巡らせています。
しかし、長時間座ったまま動かない状態が続くと、この循環ポンプが停止し、体内の流れが滞ります。
その結果、酸素や栄養が届かず、老廃物の排出もうまくいかなくなり、筋肉は硬直し、関節は固まり、神経が圧迫されていくのです。
これが、腰痛・肩こり・むくみといった不調を同時に引き起こす「座りすぎの構造的メカニズム」です。
腰痛・肩こり・むくみの原因
腰が重い、肩が張る、足がむくむ、一見バラバラに見えるこれらの症状は、実は同じ原因から始まっています。
長時間の座位姿勢によって、
・骨盤が後ろに倒れ(骨盤後傾)
・背骨のS字カーブが失われ
・呼吸が浅くなり
・下半身の血流が停滞する
この連鎖が起こることで、筋肉は硬く、関節は動きにくく、内臓の位置までも下がっていきます。
骨盤が歪むと、上半身の重心が崩れ、首や肩に余分な緊張が生じます。
それにより肩こりや頭痛が起こり、同時に下半身の静脈やリンパが滞ることで足がむくみやすくなるのです。
平井塾では、これを「姿勢循環の破綻」と呼びます。
つまり、骨格・筋肉・血流・呼吸が本来の連動を失った状態。その回復には、流れを戻す構造調整が必要です。
座りすぎが健康に与える影響
座りすぎが与える影響は、筋肉や関節だけにとどまりません。
血流の低下は自律神経や代謝機能にも波及します。
- 代謝の低下:エネルギー消費量が落ち、体温が下がる
- ホルモンバランスの乱れ:自律神経が乱れ、睡眠の質が悪化
- 集中力の低下:脳への酸素供給不足
- 免疫力の低下:体内の老廃物が溜まりやすくなる
身体の「流れ」が滞ると、心のリズムまでも乱れていく。
平井塾では、こうした慢性疲労・ストレス反応を、循環の止まりが引き金となる身体構造の乱れと捉えています。
デスクワークと体への負担
デスクワークは、現代人にとって欠かせない作業スタイルですが、その一方で、身体にとっては「動かない時間が続く最も過酷な環境」です。
平均的なオフィスワーカーは、1日7〜9時間を座って過ごすと言われています。
この時間、骨盤は常に圧迫され、太もも裏の血管は押しつぶされ、下肢の血液は心臓に戻りにくくなります。
さらに、モニターを見続けることで頭が前に出て、首や背中が硬くなり、「ストレートネック」「巻き肩」「猫背」などの姿勢不良が進行します。
これらの姿勢の崩れは、見た目だけでなく、血液・リンパ・神経・呼吸の流れを阻害する原因です。
デスクワークの疲れは、筋肉の疲れではなく流れの止まり。姿勢を整えることは、血流と呼吸を整えることでもあります。
座りすぎと腰痛の関係

「長く座っていると腰が痛くなる」「立ち上がる瞬間にズキッとする」
こうした症状を訴える方は非常に多くいます。しかし、この腰痛は単に「腰の筋肉が硬い」から起こるのではありません。
本当の原因は、座る姿勢によって体の構造バランスが崩れ、血流が滞ることにあります。
つまり、腰痛は「動かないことの結果」ではなく、「流れを止めた姿勢の結果」なのです。
腰痛のメカニズムを理解する
腰痛は、骨や神経の異常だけではなく、日常の姿勢や呼吸の乱れが積み重なって起こる「構造性の痛み」です。
座りすぎることで、
- 骨盤が後ろに倒れ(骨盤後傾)
- 背骨の自然なS字カーブが失われ
- 腰椎が過度に圧迫される
このとき、腰まわりの筋肉(腸腰筋・大殿筋・脊柱起立筋など)が常に緊張状態となり、血流が悪化。酸素不足に陥った筋肉が「痛み物質(ブラジキニン)」を放出することで、慢性的な腰痛が発生します。
また、腰部の深層筋には自律神経が密集しており、血流が滞ることで交感神経が過剰に働き、「常に腰が重い」「朝起きたときが一番つらい」といった状態を引き起こします。
平井塾では、腰痛を筋肉の問題としてではなく、姿勢と循環のバランスが崩れた結果として捉えています。
座り方が及ぼす影響
実は、腰痛の原因の多くは「座り方」にあります。
どんなに良い椅子を使っても、姿勢が崩れれば負担は増す一方です。
悪い座り方の典型例は次の3つです。
- 背中を丸めて座る(猫背型)
骨盤が後傾し、腰椎のカーブが消える。内臓も圧迫され、血流が滞る。 - 反り腰で座る(腰椎過伸展型)
腰椎が反りすぎ、筋肉が常に引っ張られた状態になる。 - 足を組む・片側に体重をかける(左右非対称型)
骨盤がねじれ、腰の片側に慢性的な緊張が起こる。
どの座り方も共通しているのは、「骨盤が動かない=循環が止まる」ということ。
骨盤が固まると、血流とリンパの流れが鈍くなり、その上にある腰椎・背骨・肩・首までも影響を受けます。
反り腰と猫背の関係
一見、正反対に見える「反り腰」と「猫背」。
しかしこの二つも、実は同じ構造上の連鎖反応でつながっています。
猫背になると骨盤が後傾し、背骨の下部が丸まります。
すると、頭の重さを支えるために首が前へ出て、バランスを取ろうと腰を反らす。これが「反り腰猫背」の典型パターンです。
つまり、猫背と反り腰は対立ではなく共存しているのです。
どちらも原因は、骨盤の安定が失われていることにあります。
この状態では、呼吸も浅くなり、横隔膜が硬くなります。
結果として、呼吸・姿勢・血流という3つの循環軸がすべて乱れてしまうのです。
平井塾の姿勢循環整体では、骨盤と呼吸の動きを再び連動させることで、
この「反り腰⇔猫背」の悪循環を断ち切ります。
腰を治すには、腰だけを見てはいけない。
骨盤の動き、呼吸の深さ、全身の流れ、それらが整って初めて、腰は軽くなるのです。
腰痛・肩こり・むくみに共通する循環の乱れ

「腰も痛いし、肩もこる。しかも足までむくむ、これって全部つながってるの?」
実は、その答えは「はい」です。
身体は部位ごとにバラバラに働いているようでいて、実際は「筋膜」「血流」「神経」「呼吸」などのネットワークで全身がひとつの循環システムとして動いています。
つまり、どこか一箇所で流れが止まると、全身のバランスが連鎖的に崩れてしまうのです。
これが、腰痛・肩こり・むくみを同時に引き起こす共通の構造的要因=循環の乱れです。
全身をつなぐ筋膜と血流の関係
筋膜とは、筋肉や内臓を包む身体の全身タイツのような膜構造。
この筋膜が硬くなったり、ねじれたりすると、血管やリンパ、神経の通り道が圧迫され、流れが滞ります。
特に座りすぎによって骨盤や太もも周囲の筋膜が緊張すると、下半身の血流が心臓に戻りにくくなり、むくみや冷え、だるさが生じやすくなります。
同時に、背中の筋膜が引きつれて肩甲骨の動きが悪くなると、首や肩の血流が低下し、肩こり・頭痛が出やすくなります。
平井塾のFJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)は、この筋膜の流れを取り戻すための繊細な技法。
触れるように調整し、全身の微細な動きを再びつなげます。
姿勢の固定がもたらす神経・リンパの圧迫
長時間同じ姿勢で座り続けると、筋肉だけでなく、神経やリンパの流れも止まってしまいます。
特に骨盤周辺には坐骨神経・大腿神経・リンパ節など、下半身の交通の要所が集まっています。
ここが圧迫されると、
・足のしびれ
・お尻の痛み
・脚のむくみ
などが生じ、全身の代謝が低下します。
さらに、リンパの滞りは「免疫力の低下」にもつながります。
つまり、座りすぎによる姿勢固定は、筋肉・血管・神経・免疫のすべてに影響を与えるのです。
血流が滞ると起こる自律神経の乱れ
血流の低下は、身体だけでなく「心」にも影響を及ぼします。
血液の流れが悪くなると、脳や内臓への酸素供給が不足し、自律神経の働きが乱れやすくなります。
その結果、
- 呼吸が浅くなる
- 冷え・ほてりが交互に起こる
- 夜の眠りが浅い
- 集中力が続かない
など、慢性的な不調が現れます。
平井塾の「姿勢循環整体」では、骨盤と胸郭、呼吸のリズムを調整することで、この自律神経のバランスを構造的に整えます。
自律神経は心の血流。
姿勢を整えることは、心の流れを整えることでもあるのです。
放置するとどうなる?慢性化のメカニズム
循環の乱れを放置すると、身体は少しずつ「固まる方向」に進みます。
筋膜が硬くなり、血流が滞り、神経が過敏になる。
結果、少しの動作でも痛みを感じやすくなり、「常に重い・だるい・疲れが抜けない」といった慢性症状へと移行します。
特に、座りすぎによる慢性腰痛や肩こりは、「筋肉が弱っているから」ではなく、流れが止まっているから起こっているのです。
流れを取り戻すためには、無理なストレッチやマッサージではなく、身体の動きのリズムを再教育することが重要です。
それが、平井塾が提唱する「構造思考による循環回復」の基本です。
座りすぎ腰痛の対策

座りすぎによる腰痛を改善するためには、「痛みを取る」ことだけでなく、流れを戻すという発想が欠かせません。
マッサージで一時的に楽になっても、また痛みが戻るのは、構造(姿勢)と循環(血流)が正しく整っていないからです。
平井塾では、腰痛対策を次の三段階で考えます。
- 姿勢を整える(構造の回復)
- 流れを戻す(循環の回復)
- 習慣として定着させる(再発予防)
ここでは、今日からできる実践法を紹介します。
腰痛ストレッチの効果と注意点
まずは、座りすぎで固まった筋肉や関節をほぐし、「動ける状態」に戻すことが第一歩です。
代表的なストレッチは次の3つです。
- 骨盤前後スイング
椅子に座り、骨盤を前後にゆっくり動かす。
腰椎・仙骨の連動を取り戻し、腰部の血流を促す。 - 太ももの裏(ハムストリング)伸ばし
片脚を前に出してかかとを床につけ、背筋を伸ばしたまま前屈。
座り姿勢で短縮したハムストリングを伸ばし、骨盤の動きを改善。 - 胸を開くストレッチ
両手を後ろで組み、肩甲骨を寄せるように胸を広げる。
呼吸が深くなり、腰への負担を和らげる。
ただし、強く伸ばしすぎないことが大切です。
痛みを感じるほどのストレッチは逆効果で、筋膜が防御反応を起こしてより硬くなることがあります。
平井塾の考え方では、「緩める」とは力を抜くことではなく、動きのリズムを取り戻すことです。
そのためのストレッチは「優しく」「呼吸とともに」が鉄則です。
デスク環境の調整方法(姿勢が変わるだけで流れも変わる)
姿勢を支える環境づくりも、腰痛対策に欠かせません。
どんなに良い姿勢を意識しても、机や椅子の高さが合っていなければ、腰への負担は続きます。
理想的なデスク環境のポイントは次の通りです。
- 椅子の高さ:膝と腰が同じ高さになるように調整(膝が高いと骨盤が後傾)
- 足裏の接地:足裏が床につかない場合はフットレストを使用
- 背もたれ:腰の自然なカーブを支えるランバーサポートを活用
- モニターの位置:目線の高さと画面上端を合わせ、首の前傾を防ぐ
特に重要なのは、骨盤を立てて座ること。骨盤が立つことで背骨が自然なカーブを描き、呼吸も深くなり、腰への圧迫が減ります。
デスクを変えることは、姿勢の土台を変えること。
環境が整えば、身体は自然に正しい位置を思い出します。
効果的なクッション・サポートグッズの選び方
座りすぎ腰痛の軽減には、骨盤を安定させるクッションも有効です。
ただし、「柔らかすぎるクッション」は逆効果。
選ぶポイントは次の3点です。
- やや硬めで沈み込みすぎない素材
骨盤を支え、長時間の座位でも姿勢が崩れにくい。 - 前傾サポート型
前方が少し高い形状は、骨盤が自然に立ち、腰椎のカーブを保ちやすい。 - 通気性の良さ
熱がこもると筋肉が硬くなり、血流が滞りやすくなるため。
また、最近は「姿勢矯正チェア」や「骨盤サポートクッション」も多数ありますが、大切なのは形を矯正することではなく、流れを支えること。
平井塾では、補助具を身体の学習のきっかけとして活用することを推奨しています。
筋トレで腰痛を予防する方法
「筋肉を鍛えると腰痛が良くなる」と言われますが、目的は「力で支えること」ではなく、「動かせる身体を取り戻すこと」です。
おすすめは以下のような姿勢筋の活性化トレーニング。
- 骨盤のニュートラルバランス保持
仰向けで膝を立て、骨盤を前後にゆっくり揺らす。
小さな動きでインナーマッスル(腸腰筋・多裂筋)を活性化。 - 呼吸連動ドローイン
息を吐きながらお腹をへこませ、吸いながら緩める。
横隔膜と骨盤底筋の連動を取り戻し、体幹を安定させる。 - 軽いウォーキング
脚の筋肉が「血液のポンプ」として働き、下半身の血流を回復。
強く鍛えるより、「しなやかに動かす」ことを意識するのがポイントです。
平井塾の姿勢循環整体では、この動的安定を育てるためのトレーニングを重視しています。
姿勢循環から見た流れる身体のつくり方

腰痛や肩こり、むくみなど、座りすぎによって起こる不調の多くは、
身体のどこかで流れが止まっていることから始まります。
その流れを戻すためには、単に筋肉を動かすのではなく、姿勢そのものを「流れる構造」に整えることが必要です。
平井塾が提唱する「姿勢循環整体」は、身体を「形」としてではなく、「流れのシステム」として捉える独自の理論です。
この考え方は、長年の臨床経験から生まれた“構造思考”の実践でもあります。
FJAで微細な歪みを整える
姿勢循環整体の基礎となるのが、平井塾独自の手技「FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)」です。
FJAは、関節と筋膜(ファシア)に存在する“動きの誤差”を見つけ出し、それを力ではなく触覚による観察と微調整で整える技法です。
たとえば、長時間座ることで骨盤や股関節の可動が失われると、その歪みは腰や背中、肩にまで波及します。
FJAでは、こうした細部のエラーを手で聴くように探り、筋膜と関節の滑走を取り戻していきます。
施術者は「押す」ことをせず、身体が自然に戻ろうとする方向へほんの少し誘導するだけ。
すると、深部の緊張がほどけ、血流・神経・リンパの流れが再び動き始めます。
FJAは「押す手」ではなく「聴く手」。
身体の声に耳を傾けることが、最も深い治療になるのです。
姿勢循環整体で呼吸と骨盤をつなぐ
FJAで細部の動きを整えた後、次に行うのが姿勢循環整体です。
これは、骨盤・背骨・胸郭・頭部を「呼吸のリズム」に合わせて調整する手技。
座りすぎで固まった身体は、呼吸のたびに動くべき部分(胸郭や骨盤)が止まっている状態にあります。
この呼吸の停滞こそが、全身の血流低下と自律神経の乱れを引き起こしているのです。
姿勢循環整体では、患者さんの呼吸に合わせて関節をわずかに誘導し、横隔膜・骨盤底筋・背骨をつなぐ循環のリズムを回復させます。
施術後には、「呼吸が深くなった」「体がポカポカする」「腰が軽い」といった変化が現れます。
これは、身体の流れる構造が再起動した証拠です。
姿勢循環整体は、「形を戻す整体」ではなく「流れを戻す整体」。
呼吸が通れば、血も巡り、姿勢は自然に整います。
「押さない・戻さない」平井塾のアプローチ
多くの施術は、硬い部分を押したり、歪みを無理に正しい位置へ戻そうとします。
しかし、それは身体にとって外からの強制であり、根本的な流れの回復にはつながりません。
平井塾の哲学は一貫しています。
「身体は、気づけば自ら整う。」
施術者がすべきことは、身体の自然な動きを感じ取り、その流れを妨げないよう導くこと。
力ではなく観察と呼吸の同調によって、身体自身がバランスを取り戻すのを手助けします。
この「押さない・戻さない」姿勢は、患者さんにとっても安心できる治療であり、心身の緊張がゆるむことで、循環の回復がさらに加速します。
姿勢を意識しなくても保てる構造とは
本当に整った姿勢とは、「頑張って正す姿勢」ではなく、何も意識しなくても自然に保たれる姿勢です。
それは、筋肉の力で固めるのではなく、重力・呼吸・骨格のバランスが調和した動く安定の状態。
姿勢循環整体によってこの状態が戻ると、
- 長時間座っても疲れにくい
- 肩や腰がこらない
- 呼吸が深く、体が温かい
- 集中力が続く
といった、日常の中での「軽さ」や「安定感」を実感できるようになります。
姿勢を作るのではなく、思い出す。
身体が本来持っている流れる構造を取り戻すことが、真の改善です。
血流が整うと変わる!座りすぎ不調からの回復サイン

「姿勢が整ったら、身体が軽くなった」
「呼吸が深くなって、頭がスッキリする」
これは、単なる気分の変化ではありません。
血流が回復し、身体の循環システムが再び働き始めた証拠です。
座りすぎによって止まっていた流れが戻ると、身体は本来の自然治癒力を取り戻し、静かに、しかし確実に変化していきます。
手足の冷え・だるさが消える理由
座りすぎによって圧迫されていた骨盤周囲の血管やリンパが開放されると、まず感じるのが「温かさの回復」です。
手足の末端まで温かくなるのは、血流が滞っていた部分に酸素と栄養が再び届いたサイン。
同時に、老廃物や二酸化炭素の排出がスムーズになり、体のだるさや重さが軽減します。
平井塾では、この現象を「流れの再起動」と呼びます。
血が巡り始めた瞬間から、筋肉も神経も「生きた組織」として動き出すのです。
温かさは、流れが戻った証拠。血流は生命のリズムそのものです。
腰や肩の重さが軽くなる仕組み
腰痛や肩こりの多くは、「循環の滞り」と「筋膜の癒着」が原因です。
姿勢循環整体で流れが整うと、筋膜が滑らかに動くようになり、負担が一点に集中しなくなります。
これにより、
・腰の張りが抜ける
・肩が自然に開く
・首の可動域が広がる
といった変化が現れます。
興味深いのは、痛みがなくなっても何をしたのか分からない感覚になること。
それは、外からの強制ではなく、身体自身の力で整ったからです。
「施術で治す」のではなく、「身体が治る方向に戻る」。
これが平井塾の構造思考の真髄です。
集中力・睡眠の質の変化
血流の改善は、脳と自律神経にも大きな影響を与えます。
デスクワークによる慢性的な循環不良は、脳への酸素供給を減らし、集中力や思考力を低下させます。
しかし、姿勢循環整体で呼吸が深くなり、血流が安定すると、脳が十分に酸素を受け取れるようになります。
結果として、
- 午後の眠気が減る
- 思考がクリアになる
- 夜の眠りが深くなる
などの変化が現れます。
また、副交感神経が優位になり、「寝ても疲れが取れない」という状態が自然に改善していきます。
呼吸と血流が整えば、脳も休む力を取り戻します。
姿勢循環とは、頭と体が再び同じリズムで働く状態なのです。
自律神経が安定し「呼吸が深くなる」身体へ
姿勢と血流の改善が進むと、最後に整うのが「呼吸」です。
これは、身体が完全に安心モードに入ったサイン。
血流が正常化すると、心拍が穏やかになり、呼吸が自然とゆっくりになります。
深い呼吸ができることで副交感神経が活性化し、ストレス耐性・免疫力・回復力が高まります。
平井塾では、この状態を「流れる安定」と呼びます。
努力して姿勢を保つのではなく、自然に呼吸が通ることで姿勢が整っている。そんな安定のかたちです。
流れる身体は、頑張らない身体。
呼吸が整うと、全ての動きが楽になる。
このように、血流が整うことによって、体の温かさ・軽さ・呼吸の深さ・集中力・睡眠など、あらゆる機能が自然に回復していきます。
つまり、「座りすぎによる不調を治す」とは、「流れを取り戻す」ということ。
平井塾が伝える姿勢循環の哲学は、単なる整体技術ではなく、身体の本来の働きを思い出すための学びなのです。
日常生活でできる予防策

腰痛や肩こり、むくみなど、これらの座りすぎ不調を防ぐ最大のポイントは、「同じ姿勢を続けないこと」です。
多くの人は「良い姿勢をキープすること」を意識しますが、実際に大切なのは、姿勢を動かし続けること。
身体は「止まる」と硬くなり、「流れる」と回復するようにできています。
つまり、座りすぎの予防とは、動く姿勢を取り戻すことなのです。
座りすぎを減らす習慣
平井塾では、姿勢を崩す原因の多くは「習慣の固定」にあると考えています。
座る時間そのものを減らす工夫をするだけで、身体の循環は見違えるように変わります。
今日から実践できる習慣をいくつか紹介します。
- 30分に一度は立ち上がる
立ち上がるだけで骨盤が動き、下半身の血流が促進されます。 - 通勤や移動で一駅分歩く
ふくらはぎは第二の心臓。歩くことで全身の血流が整います。 - 会議中は立って聞く・メモを取る
立ち仕事を少し取り入れるだけでも腰の負担は大幅に軽減します。 - 階段を使う習慣をつくる
階段の昇降運動は、骨盤と背骨の連動を自然に促します。
このように、生活の中の小さな動きが、身体の流れを守る最大の予防策です。
座る時間を減らすことは、「身体を休める」のではなく、「流れを守る」行為です。
姿勢を改善するためのポイント
座りすぎの影響を軽減するには、姿勢の整え方も重要です。
ここで意識すべきなのは、形ではなくバランス。
良い姿勢を保つための3つのコツを紹介します。
- 骨盤を立てる
背もたれに寄りかからず、坐骨で座る意識を持つ。これだけで姿勢の軸が整います。 - 頭を背骨の真上に乗せる
頭の位置が前に出ると、首から腰まで全てに負担がかかります。 - 呼吸と姿勢を連動させる
息を吸うときに背筋を伸ばし、吐くときに肩の力を抜く。
この「呼吸の動き」こそが、姿勢を支える本当の力になります。
良い姿勢は作るものではなく、呼吸の流れで自然に保たれるもの。
定期的なストレッチの重要性
いくら環境や姿勢を整えても、長時間のデスクワークでは筋肉の動きが制限されがちです。
そのため、定期的に身体を伸ばすことが必要になります。
おすすめは次のような簡単な動きです。
- 立ち上がって背伸びをする(1分間)
肩甲骨を動かし、呼吸を深める。 - 太もも前側のストレッチ(左右30秒ずつ)
座ることで縮んだ腸腰筋を伸ばし、骨盤の動きを改善。 - 軽いスクワット(5〜10回)
股関節を動かし、下半身の血流をリセット。
特に大切なのは、伸ばすことよりも動かすこと。
関節や筋膜が動くことで、体液や血液が流れ始め、姿勢循環が自然に働き出します。
平井塾では「ストレッチ=流れの再起動」と考えます。
それは、身体を変える入り口なのです。
流れる姿勢を維持するための生活リズム
予防の最終目標は、「姿勢を意識しなくても整う身体」をつくることです。
そのためには、日々の生活リズムを見直すことが欠かせません。
- 朝の深呼吸で身体をリセット
- 昼の軽いストレッチで流れを維持
- 夜のゆっくりした呼吸で回復モードへ
この「1日の循環リズム」を意識するだけで、筋肉や神経がリズムよく働き、自然と姿勢が安定していきます。
まとめ

長時間のデスクワーク、止まらない座り姿勢。
現代人の多くは、一日の大半を「動かない時間」に費やしています。
しかし、腰痛・肩こり・むくみといった不調は、座ることそのものではなく、「流れが止まること」によって起こります。
人間の身体は、本来、流れるように動きながら働く構造を持っています。
それが止まると、血流・呼吸・神経・筋膜の連動が乱れ、やがて痛みや疲れとして現れるのです。
座りすぎ不調の本当の原因は「流れの停滞」
腰痛や肩こりを単なる筋肉の疲れと考えると、対処法も「ほぐす」「温める」「ストレッチする」にとどまりがちです。
しかし、根本的な原因は「身体の循環システムが止まっている」こと。
つまり、構造(姿勢)と機能(血流)がかみ合っていない状態です。
平井塾の構造思考では、症状は結果であり、原因は常に「流れの滞り」にあると考えます。
したがって、解決策は「押す」「矯正する」ことではなく、流れを整えることなのです。
姿勢を整えることは血流を整えること
姿勢を意識して背筋を伸ばす。それは一時的な姿勢の修正にすぎません。
本当に整った姿勢とは、何も意識せずに保たれる自然な状態です。
その姿勢をつくるのが、「姿勢循環」の考え方です。
骨盤・背骨・呼吸・筋膜・血流、これらがひとつの循環として動くとき、
身体は「疲れにくく」「痛みにくく」「軽やかに」働けるようになります。
つまり、姿勢を整える=血流を整えるということ。
それが、平井塾が伝える健康の本質です。
平井塾が伝える「構造から整える健康法」
平井塾が提唱する「FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)」と「姿勢循環整体」は、単なる技術ではなく、身体の見方そのものを変える学びです。
・押さない・戻さない優しい手技で、身体の自然治癒を引き出す
・部分ではなく、全身の構造と流れを見て施術する
・「信頼」「安心」「回復」の循環を患者さんと共に育てる
これは、長年の臨床から導き出された「構造思考型」の治療哲学。
だからこそ、一時的な痛みの緩和ではなく、再発しない身体をつくることを目指しています。
痛みを取ることが目的ではなく、身体が自ら整う力を取り戻すこと。
それが、平井塾の伝える姿勢循環の本質です。
今日からできる第一歩
姿勢を整えることも、血流を改善することも、特別なことをしなくても、「小さな意識の変化」から始められます。
- 30分に一度立ち上がる
- 呼吸を深くする
- 骨盤を立てて座る
- 夜はスマホを置いて、5分間だけ何もしない時間をつくる
これだけで、身体の流れは確実に変わります。
座りすぎをやめるのではなく、「流れる時間」をつくること。それが、健康の第一歩です。
おわりに
もし今、あなたが「慢性的な腰痛や肩こり」に悩んでいるなら、その原因は姿勢の悪さではなく、循環の止まりかもしれません。
身体の声を聴き、流れを取り戻せば、痛みや疲れは静かに消えていきます。
平井塾の理念は、「身体を変えるのではなく、思い出す。」
私たちは、誰もが元々流れる身体を持っています。
その自然なリズムを取り戻すことで、日常はもっと軽やかに、呼吸はもっと深く、心はもっと穏やかに。
座りすぎの時代にこそ、「流れる身体」を取り戻すことが、本当の健康への近道です。
▼関連する記事もあわせてご覧ください
- 「長時間のデスクワークで坐骨神経痛が悪化する…」そんな方へ。
痛みの原因と正しい座り方を詳しく解説しています。
→ 坐骨神経痛は「座りすぎ」が原因?デスクワーカーが知るべき正しい座り方 - 「午後になると腰が重い」「姿勢が傾く気がする」方は要チェック。
骨盤の歪みとデスクワーク姿勢の関係を詳しく解説しています。
→ 骨盤の歪みはなぜ起こる?デスクワークで崩れた姿勢を整える方法 - 「この痛み、腰痛?それとも坐骨神経痛?」
症状の違いや、見分け方のポイントをわかりやすく紹介しています。
→ 腰痛と坐骨神経痛の違いとは?間違えやすい痛みの見分け方 - 姿勢と血流は切っても切れない関係。
猫背・反り腰・肩こり・冷えなど、全身の“循環不良”のメカニズムを解説します。
→ 姿勢が崩れると血流も悪くなる?不調と姿勢の関係とメカニズム - 「午前は平気なのに午後になると腰が痛い…」
そんな“午後腰痛”の原因と、流れる姿勢をつくる方法を紹介しています。
→ 午後の腰痛は座り方のせい?デスクワーク中に崩れる姿勢の原因を解説
【投稿者情報】平井 大樹

平井塾 代表。みゅう整骨院 代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。
「患者様の人生に、健康の安心を。」
私は、これまで20年間、延べ10万人を超える患者様と向き合ってきました。その中で最も大切にしてきたのは、「痛みを取る」ことだけではなく、「患者様が心から安心して過ごせる毎日をサポートする」ことです。
- 長期にわたる信頼:私は、5年以上通われる方が211名。その中で10年以上通われる方も93名いらっしゃいます。これは、一時的な改善ではなく、患者様が私に一生の健康を任せてくださっている証です。
- 根本的なアプローチ:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)という独自の手技で、痛みの箇所だけでなく、その根本原因である身体全体の歪みや動きの不調にアプローチします。
- 予約が取れない理由:広告を一切使わず、患者様のご紹介だけで新規予約は5年以上待ちの状態です。現在、お取りする予定はありません。
このコラムが、あなたの不調を改善し、より豊かな毎日を送るための一歩となれば幸いです。