目次
胸郭出口症候群と頚椎症の基本知識

手のしびれや痛みが続くと、「自分はどんな病気なのだろう?」と不安になる方が多いです。特に、整形外科で「胸郭出口症候群」と診断されたり、別の病院で「頚椎症」と言われたりすると、混乱してしまいますよね。まずは、この二つの病気について、基礎的な部分から整理していきましょう。
胸郭出口症候群とは?
胸郭出口とは、首の付け根から胸にかけての「神経や血管の通り道」のことを指します。
ここで筋肉や骨格のバランスが崩れると、神経や血管が圧迫されてしまい、腕から手にかけてしびれや痛みが出ます。
特徴的なのは、腕を上げたり長時間同じ姿勢をしたときに症状が強くなることです。デスクワークやスマートフォン操作、重い荷物を持つ動作で悪化することが多いです。
頚椎症とは?
一方、頚椎症は首の骨(頚椎)の老化や変形によって、神経や脊髄が圧迫される病気です。
加齢による椎間板の変性や、骨のトゲ(骨棘)が原因で起こります。
症状は肩や首の痛みだけでなく、手のしびれや握力低下、重症化すると歩行障害など全身に広がることもあります。胸郭出口症候群よりも「首そのものの変化」に由来しているのが特徴です。
胸郭出口症候群と頚椎症の原因の違い
- 胸郭出口症候群:筋肉や姿勢の崩れによる「通り道の圧迫」
- 頚椎症:加齢や椎間板の変性による「骨の変化・神経圧迫」
つまり、同じ「手のしびれ」でも、発生している場所やメカニズムが異なるのです。
これらの病気が併発する可能性について
実は、胸郭出口症候群と頚椎症は「どちらか一方」だけではなく、両方が同時に関わっているケースも珍しくありません。
たとえば、頚椎の変性で神経が弱っているところに、胸郭出口でさらに圧迫が加わると、症状は強く出ます。
このため「診断が分かれる」のではなく、「両方の要素がある」という場合も考えられるのです。
だからこそ、症状を単純に“病名”で分けるのではなく、身体全体の構造を見極める視点が大切になります。
共通の症状とその違い

胸郭出口症候群と頚椎症は、どちらも「手のしびれ」や「腕の痛み」を引き起こすため、患者さんにとってはとても区別がつきにくい病気です。ここでは、それぞれの特徴的な症状を整理しながら、両者の違いをわかりやすく見ていきましょう。
胸郭出口症候群の主な症状
胸郭出口症候群では、神経や血管が首の付け根で圧迫されるため、以下のような症状が出ます。
- 腕を上げるとしびれや痛みが悪化する
- 肩や首の重だるさを感じる
- 握力が弱くなり、物を落としやすい
- 指先が冷える、手が白くなる(血流障害による症状)
特に「姿勢や動作で症状が変化する」という点が特徴的です。
頚椎症の主な症状
一方、頚椎症は首そのものの構造変化によって神経が圧迫されるため、次のような症状が出ます。
- 首を動かすとしびれや痛みが悪化する
- 首や肩の慢性的な痛み
- 手のしびれや感覚の鈍さ
- 重症化すると歩行障害や排尿障害など全身に影響することもある
胸郭出口症候群よりも「首の動き」によって症状が左右されやすいのが特徴です。
病気ごとのしびれや痛みの違い
- 胸郭出口症候群:肩から腕、手にかけて広がるしびれ。特に「腕を上げる・長時間同じ姿勢」で悪化しやすい。
- 頚椎症:首の動作で症状が変わりやすく、しびれだけでなく首の痛みが強く出ることも多い。
つまり、症状だけで「どちらか一方」と判断するのは難しく、両者が混ざったように現れることも少なくありません。そのため、正確な評価と全身の視点でのチェックが重要となります。
診断方法の比較

手のしびれや痛みがあると、多くの方が整形外科を受診します。しかし、同じ症状でも「胸郭出口症候群」と診断されることもあれば「頚椎症」と言われることもあります。診断が分かれるのは、検査の着眼点や症状の出方が複雑に重なっているためです。ここでは、それぞれの診断方法を整理してみましょう。
胸郭出口症候群の診断に必要な検査
胸郭出口症候群では、主に身体所見(徒手検査)が重視されます。
- アドソンテスト:首を後ろに反らして深呼吸すると、脈が弱まるかどうかを確認
- ライトテスト:腕を外側に広げると症状が悪化するか確認
- モーリーテスト:腕を上げ下げしてしびれや痛みが出るかチェック
画像検査(レントゲンやMRI)では大きな異常が見つからないことも多いため、問診と徒手検査で判断されることが多いのが特徴です。
頚椎症の診断方法
頚椎症では、画像検査が中心となります。
- X線検査(レントゲン):骨の変形や椎間板の狭さを確認
- MRI:神経や椎間板の圧迫の程度を確認
- CT:骨の微細な変化を確認
症状と画像所見を合わせて、「神経の圧迫がどの程度あるのか」を診断します。
異常所見を確認するためのテスト
どちらの病気でも、神経の働きを確かめるテストが行われることがあります。
- 反射テスト(腱反射が弱い・強い)
- 感覚テスト(触覚・痛覚が鈍くなっていないか)
- 筋力テスト(握力や腕の力の低下がないか)
こうした検査で「どの神経が影響を受けているのか」を見極めます。
なぜ整形外科で診断が分かれるのか
胸郭出口症候群と頚椎症は、症状が似ているため混同されやすい病気です。さらに、どちらも同時に存在することがあるため、医師によって診断の切り口が異なるのです。
つまり「診断名が違う=どちらかが誤診」というわけではなく、症状の一部をそれぞれの病態が引き起こしている可能性があるということなのです。
治療アプローチとリハビリテーション

胸郭出口症候群や頚椎症と診断された方にとって、最も気になるのは「どう治していけばいいのか」という点だと思います。実際の治療は、病院での保存療法や薬物療法、必要に応じて手術が検討されますが、多くの方はまず保存的な治療とリハビリから始めます。ここでは、整体を含めたアプローチの違いと、平井塾が大切にしている考え方をご紹介します。
整体での胸郭出口症候群の対応
胸郭出口症候群の場合、首や肩まわりの筋肉が硬くなり、神経や血管を圧迫しているケースが多く見られます。整体では、
- 鎖骨や肋骨、肩甲骨の位置を整える
- 首や肩の筋肉の過緊張を緩める
- 姿勢習慣の改善につながるアドバイス
といったアプローチを行い、神経や血管の通り道を広げることを目指します。
頚椎症に対する整体アプローチ
頚椎症の場合は「骨の変形」そのものを元に戻すことはできません。しかし、周囲の筋肉や関節の負担を減らすことで、症状を大きく改善できるケースがあります。
- 首にかかるストレスを軽減する姿勢調整
- 肩甲骨や胸椎の動きを改善し、首の負担を分散
- 神経の通りを助けるようなリリース手技
頚椎だけを診るのではなく、全身の連動性を整えることが大切です。
平井塾のFJAで“細部のエラー”を見極める
平井塾で学ぶ「FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)」は、筋膜・関節・神経のつながりを細かく観察し、身体の“見落とされがちなエラー”を見つけ出す手技です。
- 痛い場所を直接押すのではなく、なぜそこに負担が集まったのかを探る
- 力任せではなく、施術者の「手で聴く」ような観察を重視
- 根本の原因にアプローチすることで、持続的な改善を目指す
「処置型」ではなく「構造思考型」の施術であることが大きな特徴です。
姿勢循環整体で全身の循環を整える
FJAで細部を整えた後は、「姿勢循環整体」によって全身の循環を改善します。
- 姿勢のバランスを調整することで、血液やリンパの流れを促進
- 内臓や神経系を含めた全身の回復力を引き出す
- ルーティン化された手技により、安定した効果を実感できる
部分的な対処だけでなく、全体の治癒力を高めることがポイントです。
ストレッチや運動の重要性
整体だけでなく、患者さん自身が日常的に取り組めるケアも大切です。
- 胸を開くストレッチ
- 肩甲骨を動かす軽い体操
- 正しいデスクワーク姿勢
こうしたセルフケアを取り入れることで、施術の効果を長持ちさせ、再発の予防にもつながります。
手術の必要性とそのリスク

胸郭出口症候群や頚椎症の治療を受けていると、「手術をしないと治らないのでは?」と不安に思う方が少なくありません。確かに、重症例では手術が検討されることもありますが、多くの患者さんは保存療法や整体などの保存的アプローチで改善できる可能性が高いのです。ここでは、病気ごとに手術の考え方とリスクについて整理します。
胸郭出口症候群の手術は必要か?
胸郭出口症候群では、鎖骨や肋骨の間で神経や血管が圧迫されているケースがあります。重症化すると、
- 指先の血流が極端に悪くなる
- 神経麻痺によって筋肉が萎縮する
といった深刻な症状に進行することもあります。
このような場合には、肋骨の一部を切除する「肋骨切除術」や、圧迫している筋肉を取り除く手術が選択されることがあります。
ただし、手術後も完全に症状がなくなるわけではなく、術後リハビリや姿勢改善の取り組みが欠かせません。
頚椎症の手術の考え方
頚椎症では、椎間板の変性や骨棘によって神経が強く圧迫され、次のような症状が出た場合に手術が検討されます。
- 歩行障害が進行している
- 排尿・排便に影響が出ている
- 手足の筋力低下が強く、日常生活に支障がある
代表的な手術法には、「椎弓形成術」や「椎間板摘出術」などがあります。これらは神経の圧迫を解除するための処置ですが、やはり術後のリハビリと生活習慣の見直しが不可欠です。
手術前に試すべき保存療法
実は、胸郭出口症候群も頚椎症も、多くの方は手術をせずに改善することが可能です。
- 薬物療法(消炎鎮痛薬、筋弛緩薬など)
- 物理療法(牽引、温熱療法など)
- 整体やリハビリによる姿勢・循環改善
これらの保存療法を十分に行った上で、どうしても症状が改善しない場合に初めて手術が検討されます。
日常生活における予防策と対策

胸郭出口症候群や頚椎症は、一度症状が出ると長引きやすい病気です。しかし、日常生活の中で姿勢や動作を工夫することで、再発や悪化を防ぐことができます。ここでは、それぞれの病気に合わせた予防方法と共通の生活習慣の改善ポイントをご紹介します。
胸郭出口症候群の予防方法
胸郭出口症候群は「姿勢の崩れ」によって起こりやすいため、日常の体の使い方がとても重要です。
- 猫背を防ぐ:背筋を伸ばし、胸を軽く開く姿勢を意識する
- 長時間同じ姿勢を避ける:デスクワークでは1時間に一度は腕や肩を動かす
- 荷物の持ち方を工夫する:片方の肩にバッグをかけ続けない
こうした工夫で、首や肩の神経・血管の通り道が圧迫されにくくなります。
頚椎症の予防策
頚椎症は加齢変化が原因の一つですが、生活習慣で進行を遅らせることが可能です。
- 正しい枕を選ぶ:高すぎず低すぎない枕で首の自然なカーブを保つ
- スマホ首を防ぐ:うつむいたまま長時間スマホを操作しない
- 首に優しい運動習慣:軽いストレッチやウォーキングで血流を改善
首に過度な負担をかけない生活を心がけることが大切です。
デスクワークや家事で気をつけたい姿勢習慣
共通して言えるのは、首や肩に余計な負担をかけない生活です。
- パソコン画面は目の高さに調整する
- 肘や前腕を机にしっかり乗せてタイピングする
- 掃除や料理の際は腰を曲げすぎず、膝を使う
こうした日常の小さな工夫の積み重ねが、症状の予防に大きくつながります。
専門医への受診を考える
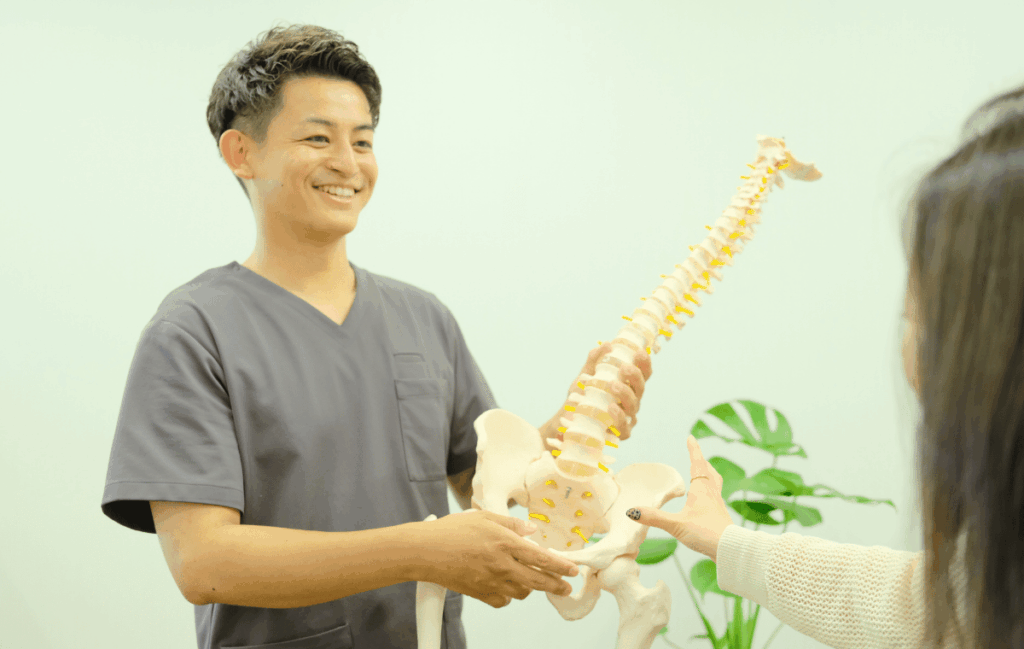
胸郭出口症候群や頚椎症は、整体やリハビリで改善するケースが多い一方で、医療機関での診察や検査が欠かせない場合もあります。「整体でなんとかなるかな」と思っていても、症状が進行しているケースでは専門医のサポートが必要です。ここでは、受診の目安と医療機関との上手な使い分けについて解説します。
どのタイミングで受診すべきか
次のような症状がある場合は、早めに整形外科や神経内科などの専門医を受診しましょう。
- 手足のしびれが日に日に強くなる
- 握力や筋力が低下し、日常生活に支障が出ている
- 歩行がぎこちなくなったり、つまずきやすくなった
- 排尿や排便のコントロールに変化がある
これらは神経への圧迫が進んでいるサインで、放置すると取り返しのつかない症状につながることもあります。
専門医紹介と受診の流れ
医療機関では、まずレントゲンやMRIなどの画像検査が行われます。その結果をもとに、
- 薬物療法
- リハビリ(理学療法)
- 必要に応じて手術の検討
といった治療が提示されます。整体でのアプローチと並行して医療を受けることで、より安心して症状改善を目指すことができます。
整体と医療機関の役割の違い
- 医療機関:画像検査で構造的な異常を確認し、手術や薬で強い症状に対応
- 整体:日常の体の使い方や全身のバランスを整え、根本的な回復力を引き出す
この両者をうまく組み合わせることで、最も安全かつ効果的に回復へ向かうことができます。平井塾では「必要なときは必ず医療機関にかかること」を患者さんにお伝えし、安心できる環境を整えています。
患者の体験談と改善事例

胸郭出口症候群や頚椎症は、病名を聞いただけで不安になりやすいものです。しかし実際には、整体やリハビリで改善した方が数多くいらっしゃいます。ここでは、平井塾で学んだ技術を活かした施術現場から、患者さんの声と改善事例をご紹介します。
胸郭出口症候群体験者の声
40代女性・事務職
「デスクワークで長時間パソコンを使うと、腕のしびれがひどくて仕事に集中できませんでした。整形外科では胸郭出口症候群と診断され、薬を出されましたが改善せず…。整体で肩や鎖骨のまわりを整えてもらうと、徐々にしびれが減っていき、今では仕事を続けられるようになりました。」
→ この方の場合、鎖骨周囲の筋肉バランスを整えることで神経の通り道が広がり、症状が軽快しました。
頚椎症の改善事例
50代男性・営業職
「首を回すと激しい痛みと腕のしびれがあり、MRIでは頚椎症と言われました。手術も視野に入れていましたが、整体で背中から肩の動きを改善してもらううちに、首の負担が軽減。半年後にはしびれが気にならない程度になり、手術は不要になりました。」
→ 頚椎症のように骨の変化がある場合でも、周囲の筋肉や関節の負担を軽くすることで症状を和らげることが可能です。
整体で症状が軽快したエピソード
- 手の冷えとしびれで夜眠れなかった方が、姿勢循環整体で循環が改善し、ぐっすり眠れるようになった
- 握力が低下していた方が、FJAによる調整で力が戻り、日常生活の不安が減った
- 「仕事を辞めるしかない」と考えていた方が、改善を実感し、再び前向きに生活できるようになった
これらの事例からもわかるように、診断名に惑わされず、体全体の構造を見直すことが改善のカギになります。
胸郭出口症候群や頚椎症について理解を深めるためには、信頼できる医療情報や学術的な資料に触れることが大切です。
まとめ|診断名に惑わされず、根本から整える選択を

胸郭出口症候群と頚椎症は、とても似た症状を示すため、診断が分かれることも少なくありません。しかし大切なのは「病名」そのものに振り回されるのではなく、体のどこで不調が起こり、それがどう全身に影響しているのかを理解することです。
- 胸郭出口症候群は「首の付け根の通り道」での圧迫
- 頚椎症は「首の骨そのものの変化」による神経圧迫
それぞれ原因は違っても、症状は重なり合います。だからこそ、部分的な治療だけではなく、全身のバランスや循環を見直すことが重要です。
整体やリハビリは、こうした「全体の構造」を整えるための有効なアプローチとなります。さらに、医療機関と連携することで、安心して回復への道を歩むことができます。
平井塾の学びと実践から得られた知見
平井塾では、20年以上にわたる臨床経験と10万回以上の施術を通じて、胸郭出口症候群や頚椎症の改善事例を積み重ねてきました。
- FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)による細部の調整
- 姿勢循環整体による全身の循環改善
- 医療機関との連携による安全性の担保
これらの実践知は、単なる理論にとどまらず、多くの患者さんの回復を支えてきた「生きた情報」として活かされています。
信頼できる整体師と共に、安心の未来を
胸郭出口症候群や頚椎症の改善には、単に技術を持つだけでなく、患者さんの体の声を丁寧に聴き、根本から整えていく「構造思考」が欠かせません。
平井塾では、20年以上・10万回以上の臨床経験から培われた知識と技術を体系化し、全国の施術家が学んでいます。
- FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)で細部の原因を見抜く力を育む
- 姿勢循環整体で全身の循環を整え、自然治癒力を引き出す
- 医療機関との連携を前提とした「安全で信頼できる施術家」を育成
平井塾で学んだ受講生は、地域の患者さんに安心と回復を届ける存在となり、多くの信頼を得ています。
もしあなたが「本当に患者さんの役に立てる整体師になりたい」と思うなら、平井塾での学びはきっと力になるはずです。
投稿者情報:平井 大樹

みゅう整骨院 代表。平井塾 代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。
「患者様の人生に、心からの安心を。」
私は、これまで20年間、延べ10万人を超える患者様と向き合ってきました。その中で最も大切にしてきたのは、「痛みを取る」ことだけではなく、「患者様が心から安心して過ごせる毎日を取り戻す」ことです。
- 長期にわたる信頼:みゅう整骨院には、5年以上通われる方が308名、10年以上通われる方も100名いらっしゃいます。これは、一時的な改善ではなく、患者様が私たちに一生の健康を任せてくださっている証です。
- 根本的なアプローチ:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)、姿勢循環整体という独自の手技で、痛みの箇所だけでなく、その根本原因である身体全体の歪みや動きの不調にアプローチします。
- 平井の予約が取れない理由:開業後、患者様の紹介がメインで予約が満員になりました。2020年以降、新規予約は5年待ちの状態です。現在、新規予約を取る予定はありませんが、みゅう整骨院または、平井塾受講生から同じ施術を受けることができます。
このコラムが、あなたの不調を改善し、より豊かな毎日を送るための一歩となれば幸いです。

